尿検査

ぺんさん
「尿検査」は経験があると思います。
尿検査は腎臓や尿路の疾患や糖尿病などの発見に役立つ検査です。
いろいろな項目があるのですが、「検尿」とか「尿検査」いうと、「尿の定性検査」を意味することが多いと思います。では、この尿の定性検査ではどんなことがわかるのでしょう。
尿の検査の中の「定性検査」について考えます。
定性検査について
定性検査とは
「尿の定性検査」は試験紙を使って尿に含まれる様々な成分を調べる検査です。
試験紙は数社から出されており、測定機専用のもの、目視判定専用のもの、検査項目数が1項目から10項目程度のもの、また測定項目の組み合わせも数種類あり、全体で様々な種類の試験紙があります。
また、医療機関で使用されるものだけでなく、薬局などで一般に購入できるものもあります。
試験紙による検査は、一部の項目を除いて「半定量検査」となっていて、(-)、(±)、(1+)、(2+)、(3+)などと判定し、それぞれがある幅を有する目安値を示します。
尿定性検査の主な項目
尿試験紙の項目
- 尿比重
比重は、尿中のナトリウムや尿素、クレアチニン、その他の固形成分の含有量を示します。腎臓の水分量の調節機能、つまり尿の濃縮度を確認することができます。基準範囲は1.015~1.025。1.030以上は濃縮尿(濃い尿)とされ、脱水症、嘔吐、下痢、糖尿病など、水分喪失状態が疑われます。1.010以下は希釈尿(薄い尿)とされ、尿崩症、急性腎不全、飲水過多な、腎臓での尿の濃縮障害が考えられます。
- 尿pH
pHは、尿の酸性度、アルカリ性度を示します。基準範囲は4.5~7.5。食事や運動、薬物などによって変動します。体内の酸塩基平衡(酸性とアルカリ性を保つバランス)の指標とされます。異常高値(アルカリ性)では尿路感染症、嘔吐、過呼吸などが、異常低値(酸性)では発熱、脱水、糖尿病、腎炎、痛風、過度の肉食などが疑われます。
- 尿蛋白
尿蛋白は、尿中の蛋白質の有無を調べる検査です。基準値は(-)。健康でも尿中にごく微量の蛋白が排泄されていますが、試験紙による定性検査では検出されません。一日の総蛋白排泄量が150㎎/日を超えると病的蛋白尿とされます。尿蛋白が陽性(+)になる要因は、腎臓に異常はなく悪性腫瘍や感染症などが原因となる「腎前性」、腎機能障害などの「腎性」、膀胱、前立腺、尿管などに問題がある「腎後性」があります。また、激しい運動や精神的ストレスなど生理的な要因で陽性になることもあります。
- 尿糖
尿中のブドウ糖の有無を調べる検査です。基準値は陰性(-)。主に糖尿病のスクリーニング、診断、治療効果の判定などに利用されています。健康でも微量なブドウ糖が排泄されますが、試験紙による検査では検出されません。血液中のブドウ糖は糸球体で濾過され、大部分が尿細管で再吸収されるため尿中には検出されないのですが、血糖値が160㎎/dL~180mg/dLを超えると、糸球体での濾過量が尿細管での再吸収量を超えるため、尿中にブドウ糖が排泄されることになります。ただし、糖排泄閾値が低下する腎性糖尿の場合は、血糖値は正常でも尿糖が陽性を示します。
- 尿ウロビリノゲン
ウロビリノゲンはビリルビンの最終代謝産物です。ビリルビンは肝臓から胆汁として十二指腸に排泄され、腸内細菌によって還元されることでウロビリノゲンが生成されます。ほとんどは便として排泄されますが、一部は血液を介して腎臓から尿中に排泄されます。基準値は(±)。健康でも少量は尿に排泄されるので、陰性は異常ということになります。大量に尿中に排泄された場合陽性(+)となり、肝臓の機能低下や溶血性貧血、便秘、腸閉塞などが疑われます。ビリルビンが肝臓から十二指腸に排泄されないとウロビリノゲンは陰性(-)となりますが、この場合、閉塞性胆道疾患、下痢、抗生物質製剤投与による腸内細菌の著減などが考えられます。
- 尿ビリルビン
尿中のビリルビンの有無を調べる検査です。基準値は陰性(-)。ビリルビンは赤血球が120日間の寿命後に破壊されて作られます。肝臓で処理された後、大部分が胆管に排泄され腸内細菌によってウロビリノゲンに還元されますが、一部は腸管で再吸収され門脈から肝臓に戻り再びビリルビンとなります。血中のビリルビンが増加して腎臓での排泄閾値(2mg/dL~3mg/dL)を超えると尿中に排泄されます。したがって尿中にビリルビンが認められた場合、肝障害、閉塞性黄疸などが疑われます。肝臓や胆道系疾患のスクリーニング、補助的診断に利用されます。
- 尿ケトン体
尿中のケトン体の有無を調べる検査です。基準値は陰性(-)。ケトン体は脂肪酸の分解によって作られる物質です。重症糖尿病、絶食、嘔吐、下痢、飢餓状態、過度の糖質制限など、糖質が不足している状態で脂肪を分解してケトン体が生成され、エネルギー源となります。尿ケトン体は血中のケトン体の増加を反映します。血中にケトン体が増加した状態をケトーシス、ケトン体の増加によって血液が酸性に傾いた状態をケトアシドーシスと呼び、急激な呼吸困難、意識障害、昏睡が生じますが、尿ケトン体はこれらのスクリーニングとして有用とされています。健康でも尿ケトン体は排泄されていますが、試験紙では検出できません。
- 尿潜血
尿中の赤血球のヘモグロビンの有無を調べる検査です。基準値は陰性(-)。尿潜血は、腎蔵、尿路系の出血のスクリーニング検査として重要とされています。血尿には、目視で認識できる肉眼的血尿と、目視でが認識できない微量の血尿である顕微鏡的血尿がありますが、潜血の検査はどちらも検出することができます。肉眼的にはわからない微量の血尿を検出可能であることは重要です。また、筋肉の破壊によって生じるミオグロビン尿でも陽性となります。陽性の場合、腎、尿管、膀胱、前立腺などの炎症、結石、腫瘍、外傷性筋肉損傷、多発性禁煙、クラッシュ症候群、溶血性貧血などの疾患が疑われます。
- 亜硝酸塩
亜硝酸塩の検出をする検査です。基準値は陰性(-)。尿中に排泄された硝酸塩は、細菌の亜硝酸塩還元酵素によって亜硝酸塩となります。亜硝酸塩を検出することで、間接的に腎尿路系の細菌感染の有無を調べることができます。この検査には、膀胱内に4時間以上溜まった尿が必要とされます。陽性の場合、尿路感染症の主な原因菌である大腸菌、肺炎桿菌などの感染が疑われます。
- 白血球エステラーゼ
白血球が持つ酵素である白血球エステラーゼの有無を調べる検査です。基準値は陰性(-)。白血球エステラーゼは、白血球が細菌などの異物と戦う際に放出されます。尿中の白血球エステラーゼの検出は、尿中に白血球が多く存在することを意味します。尿路感染症のスクリーニング検査として有意義とされています。陽性の場合、尿路感染症が疑われます。亜硝酸塩と同時に陽性となった場合、細菌による尿路感染症の可能性が高まります。
尿定性検査の影響を与える要因
尿定性検査は、尿に試験紙を浸して反応させ、色調の変化を判定します。
判定の仕方は、専用機器で測定する場合と目視判定をする場合があります。
色調の判定には、項目によって尿に浸してからの時間が決まっていて、「直ちに」から「120秒」程度まで、正しく守って判定することが必要です。
尿定性検査は色調の変化を判定するため、着色尿は注意が必要になります。また、薬剤や食事などが検査結果に影響を与える場合があることが知られています。
ビタミンC(アスコルビン酸)は尿糖、尿潜血、尿ビリルビンなどの項目に影響を与えるとされています。
また、パーキンソン病の治療薬L-DOPA、ステロイド剤、一部の抗リウマチ薬なども尿定性検査の結果に影響を与えることがあると言われています。
食事の影響としては、ビタミンCや硝酸塩を多く含む飲料や食品があり、それらの大量の摂取は、一部の項目に影響を与える可能性があります。
この他、激しい運動は尿蛋白や尿潜血の結果に影響を与える場合があり、また生理中の尿は血液が混入するため正しい結果が得られない可能性があります。
尿定性検査に影響する主な因子
- ビタミンC
- L-DOPA、ステロイド剤、抗リウマチ薬
- ビタミンC、硝酸塩を多く含む食品
- 激しい運動
- 生理中
尿検査の正しい結果のために
尿検査の有用性
尿検査は、一般的に、検体の採取に痛みを伴うことがなく比較的容易に検査でき、多くの情報を得ることができます。
また、検体採取から最短では5分程度の短時間で結果を得ることができます。
尿検査は、糖尿病や腎臓、尿路系、肝臓、胆管系、その他、さまざまな疾患のスクリーニング検査として有用です。
しかし、正しい検査結果を得るためには、検査の内容を正しく理解していることが大切です。
尿検査の有用性
- 検体の採取に痛みを伴わない
- 検査が容易
- 情報量が多い
- 短時間で結果が得られる
- スクリーニング検査として有用
正しい結果のために
例えば、ビタミンCは検査結果に影響を与える可能性があると言われています。大量摂取でなければ問題ない場合もありますが、サプリメントなどで日常的に摂取している時には、検査の際に伝えていただくことも必要だと思います。
生理中の場合も申し出ていただくことで、結果を参考値にしたり、その日の検査は中止にし次回に検査する、などの対応をとることもできます。
また、採尿の仕方も、特に指示がない場合は「中間尿」をきちんと採取することも重要です。採尿 [尿検査のこと1]
簡単な検査でも、きちんと検査内容を理解して受診することが、正しい結果を得るためには重要といえます。
尿検査に関して、もし疑問や心配なこと、納得できないことなどがありましたら、担当医師に相談していただくのが良いと思います。
本記事は診断や治療を目的としたものではありません。あくまでも臨床検査に対する理解を深めていただくための情報や知識の提供の場です。疑問や不安がある場合は必ず医師にご相談ください。


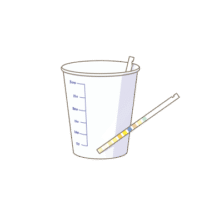


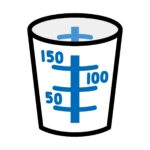

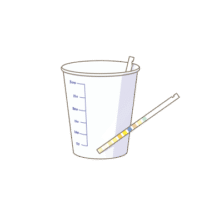






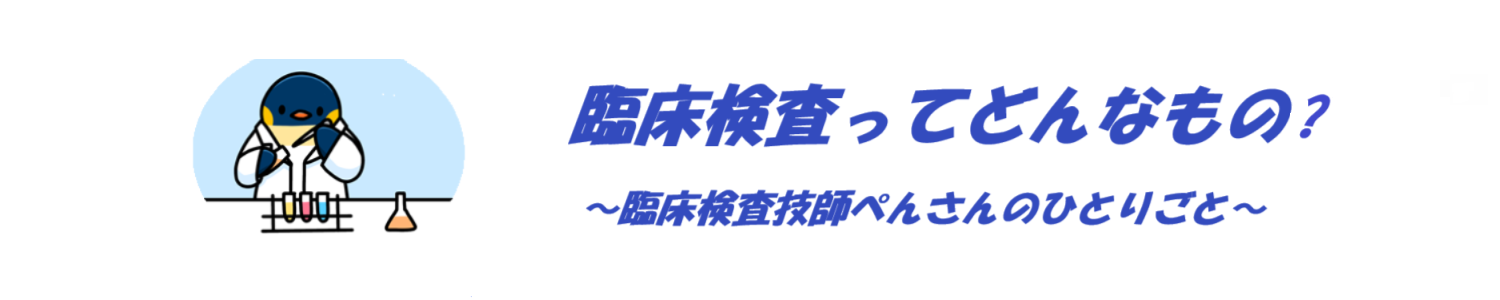


コメント