心機能検査

心臓の機能も血液検査でわかるのかな・・・?
「心機能」つまり心臓の働きの評価は、どのような検査で行うと思いますか。
ここでは心臓に関する血液検査について考えます。

心機能に関わる検査
心臓の検査
心臓の検査というと、やはり、心電図や心臓超音波検査が思い浮かぶでしょうか。
これ以外にも運動負荷心電図、ホルター心電図、CT検査、MRI検査、心臓カテーテル検査などがあります。また、聴診や血圧測定も心機能に関連する検査です。
もちろん血液検査の中にも関連する検査があります。
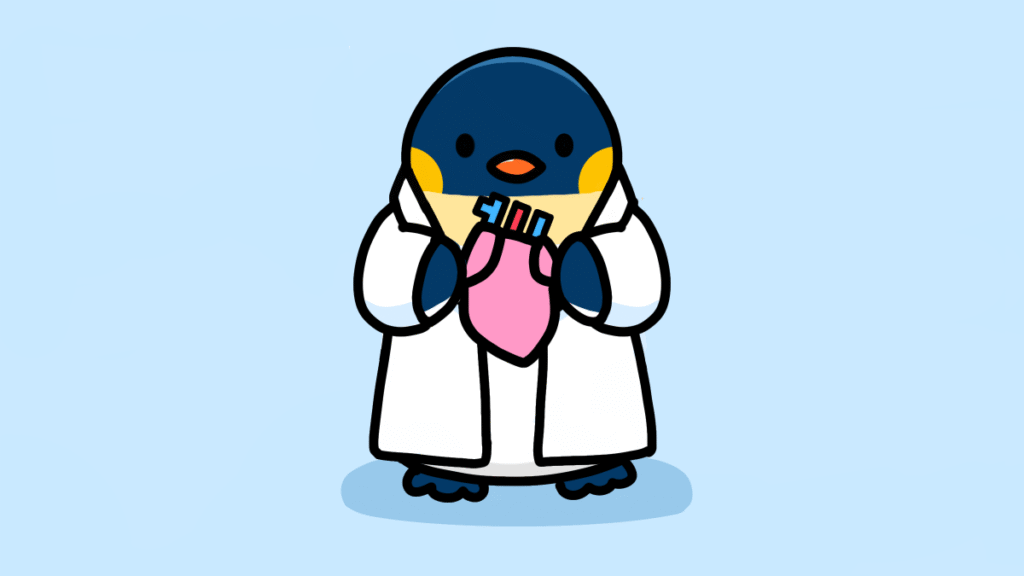
心臓に関連した血液検査
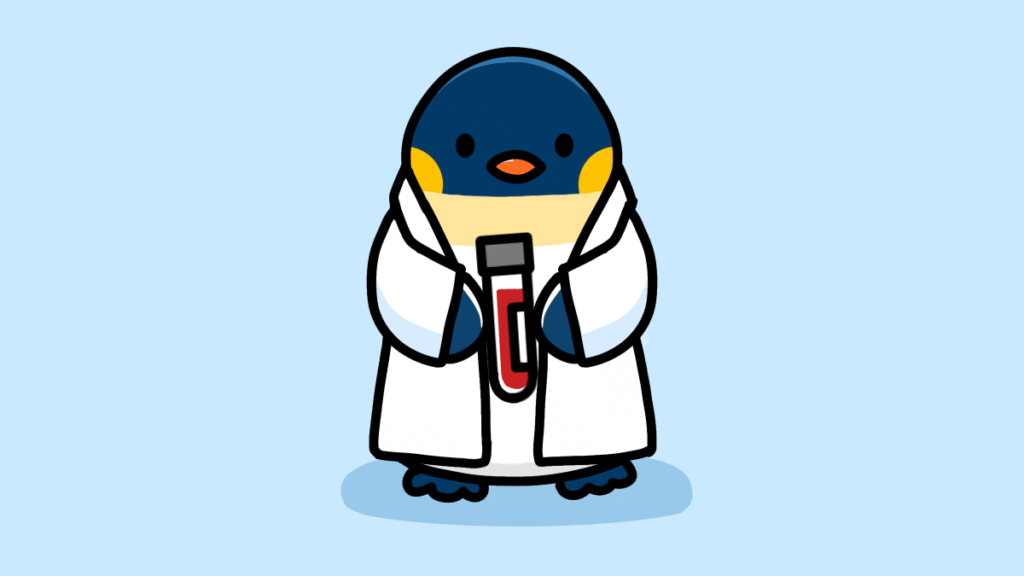
心機能に関わる検査には、
心筋が損傷をうけると血液中に漏出する酵素や、
心不全の状態を示すホルモンなどの検査があります。
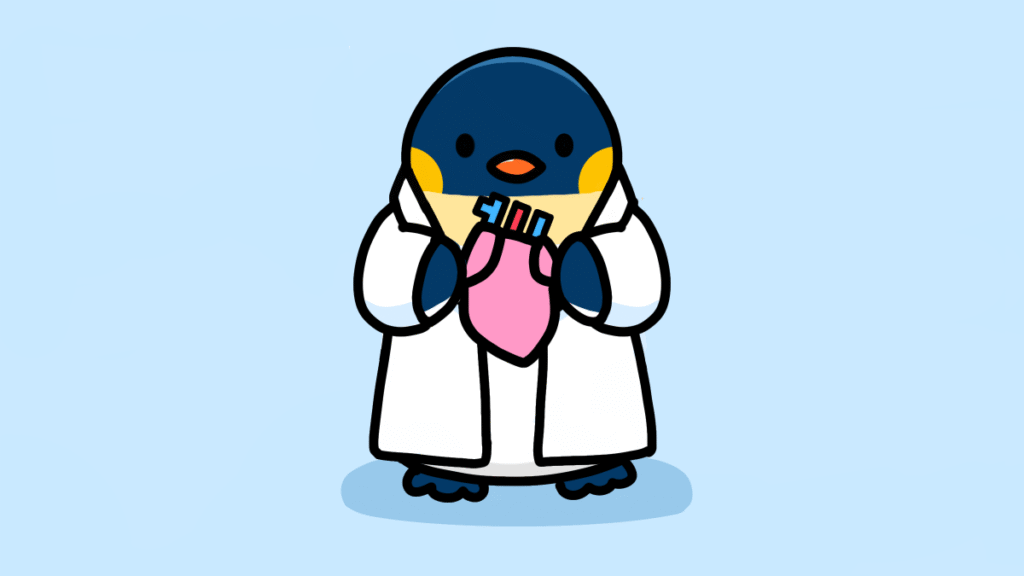
心電図や心臓超音波検査は、心臓の電気的な活動や不整脈の有無、形や大きさ、弁の機能などを評価することができますが、血液検査も、心筋梗塞や心不全の早期発見、重症度の評価などに欠くことはできません。
心機能検査に関わる代表的な項目をあげてみます。
心機能の検査項目の考え方
AST、LD、CK
AST、LD、CKは、細胞が破壊されることで血液中に放出される逸脱酵素です。心臓以外の場所にも存在しているため、血中濃度の上昇は、必ずしも心筋の損傷だけを意味しているわけではありません。
一方CK のアイソザイムであるCKMBは特に心臓に多く含まれるため、その上昇は心筋の損傷を意味します。
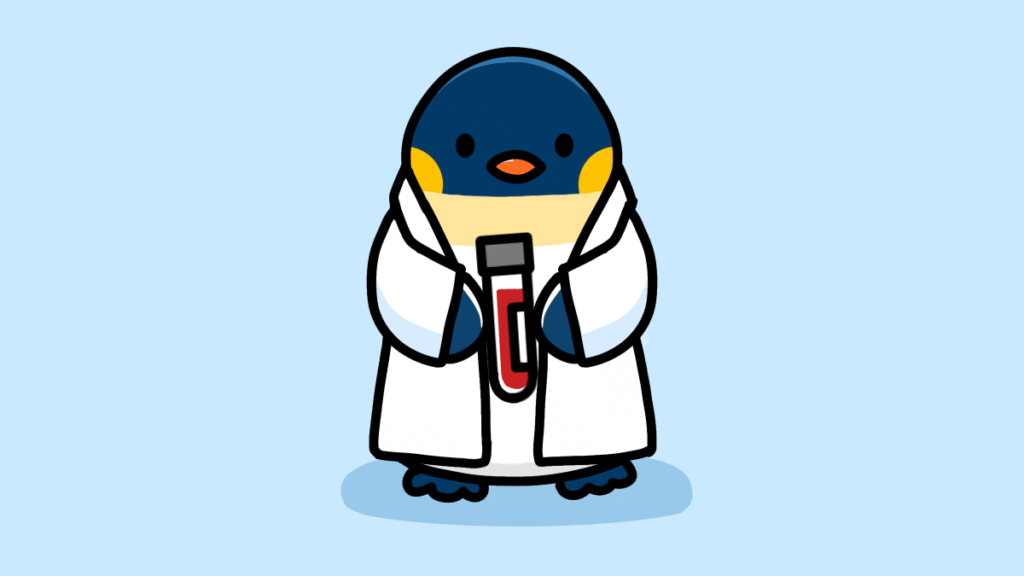
血液検査をする場合、ASTやLDを単項目で検査依頼することはまずありません。
多くの場合、AST、ALT、LD、ALPをはじめとした酵素系の項目、総蛋白やアルブミン、UN、クレアチニン、その他、いろいろな項目を組み合わせて検査をします。そして、どのような項目が異常値なのかを見極めて、次の方針を決めていくことになります。
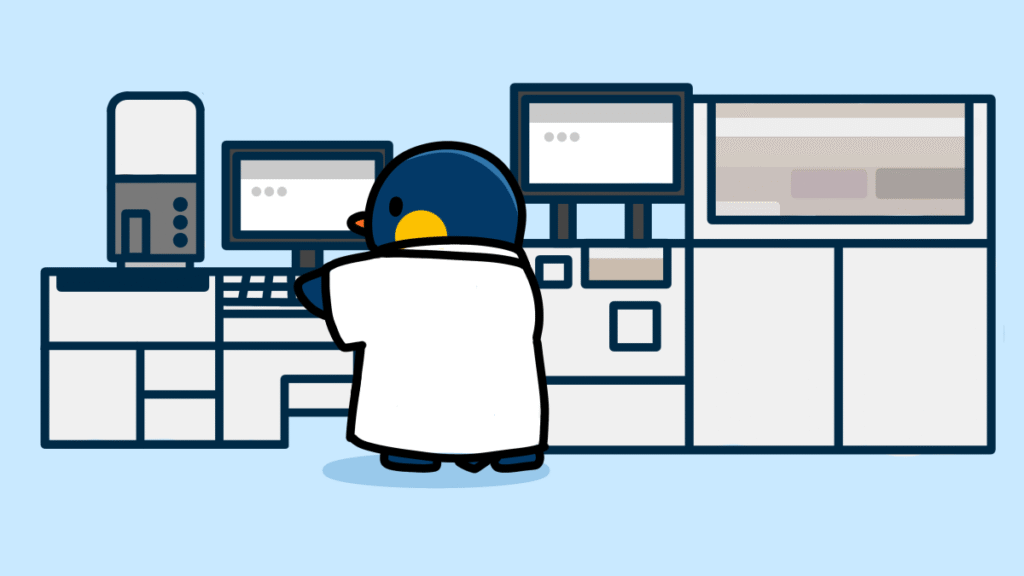
たとえば、AST、LD、CKが高ければ心臓の疾患を疑い、CKMBを追加で検査する、といったことが行われます。
心電図などの検査も並行して実施されますが、CKMBが高ければ心筋梗塞を疑ってさらに検査を進めていきます。
また、これらの項目は、その値の上昇の仕方で病状の程度を推測することもできます。

BNP、NT-proBNP
BNPとNT-proBNPは、心臓への負担の大きさを表すと言われています。心不全の診断や重症度の評価に用いられます。
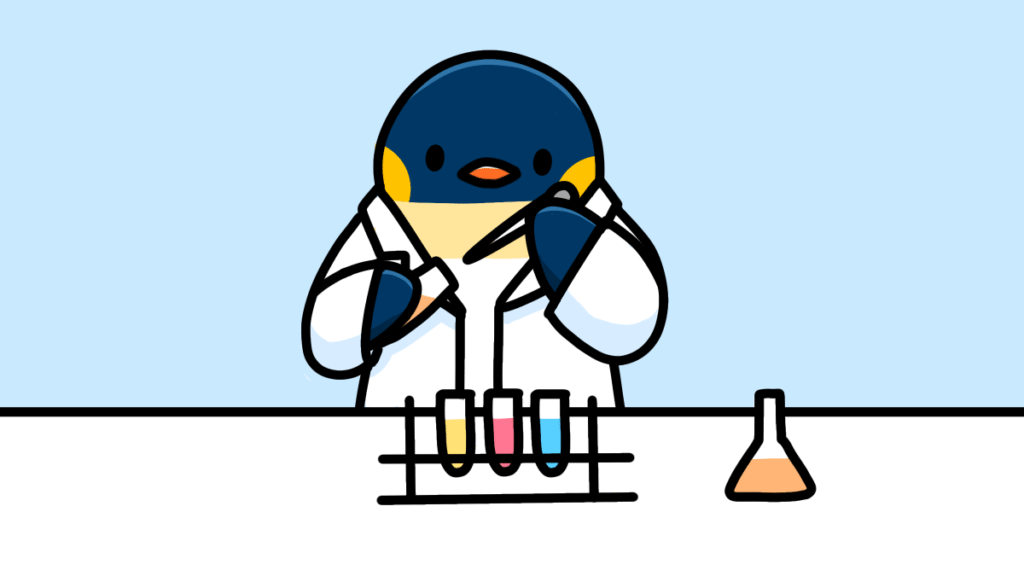
BNPは腎機能の影響を受け難いのですが、NT-proBNPは腎機能の低下によって値が上昇する傾向があると言われていて、これは注意が必要な点です。
また、BNPはEDTA血漿を検体とするのに対し、NT-proBNPは血清で測定します。これは、検査をする上では重要な注意点です。
NT-proBNPは通常の生化学検査の検体と同じ血清で測定できますが、BNPは別にEDTAの採血管での採血が必要になるのです。
トロポニン
トロポニンは心筋障害の診断に重要と言われています。
心筋梗塞などで胸痛が現れてから比較的早期に上昇するので、心筋梗塞の早期診断に役立つとされています。
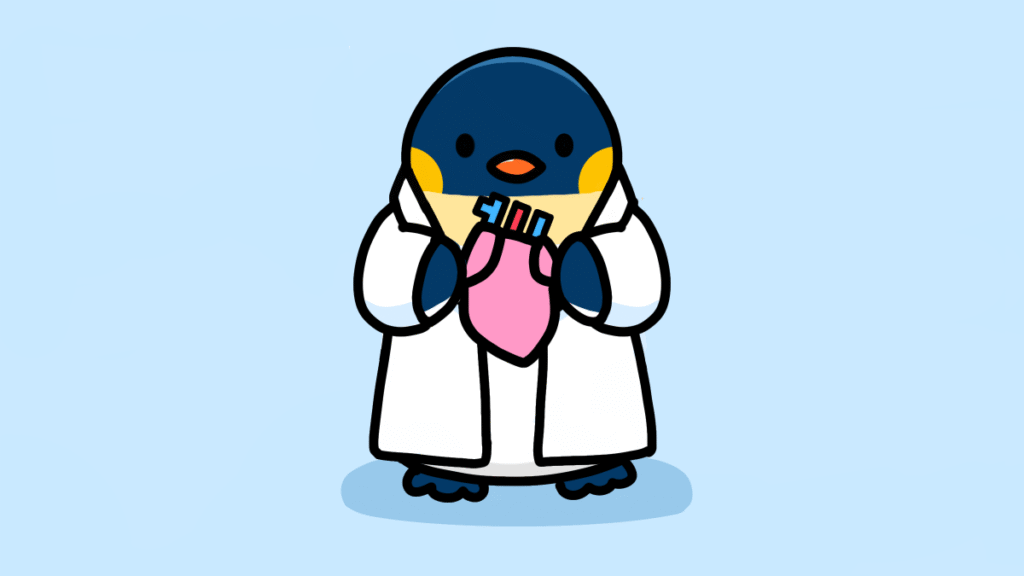
以前はCKMBが心筋梗塞の診断に重要とされていましたが、現在ではトロポニンの方がより推奨されています。
トロポニンは腎臓で排泄されるため、腎機能が低下すると高値となるので注意が必要です。
また、トロポニンは心筋梗塞発症後、数日から数週間高値が持続するので、経過観察などにも利用されています。

心臓のために
心機能検査の役割
心機能を確認する検査はいろいろあります。
たとえば心電図は、疾患に特徴的な結果を得ることで、その検査だけで診断にかなり近づくことができます。
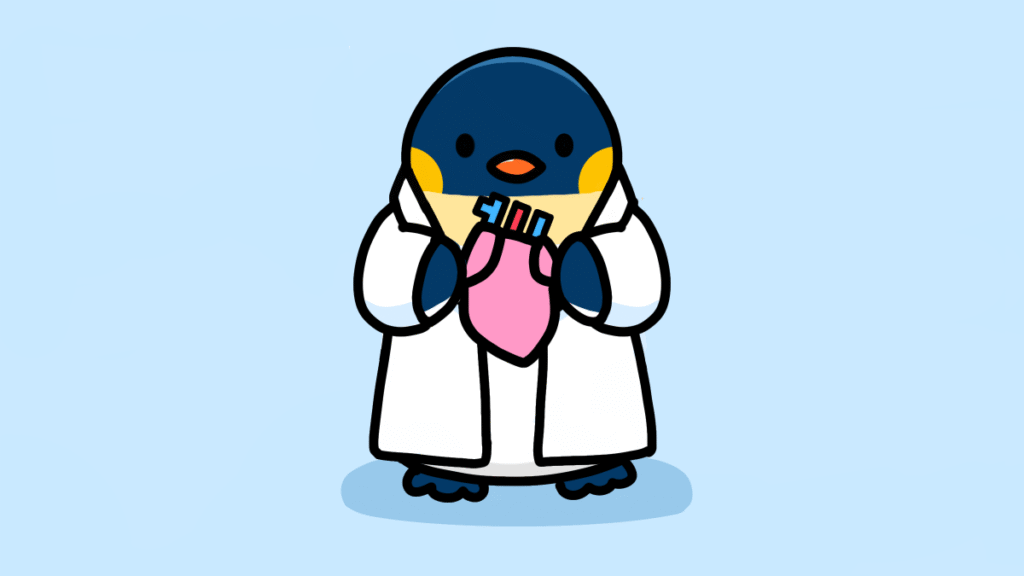
しかし血液検査の場合は、1項目で診断できることはほぼありません。何項目かを組み合わせて、障害をうけている臓器を、またその程度を判断することになります。
もちろん特異性の高い検査項目もあり、診断や経過観察に役立っています。

心臓が悪い場合には何らかの自覚症状が認められると思いますが、それで直ちに受診するケースばかりではありません。
別の目的での受診、あるいは健康診断などで、はじめて指摘される場合も少なくありません。
また、残念ながら、突然倒れるなどして病院に運ばれるという事例も耳にすることがあると思います。
自覚症状がなかったとしても、血液検査でいろいろな項目を検査することによって、心機能の低下や心筋の損傷が発見され、適切な治療を開始することができます。
心疾患と血液検査
心臓に関する疾患は、心不全、虚血性心疾患、心臓弁膜症、不整脈、心筋症など、さまざまなものがあります。
心不全は、心臓が血液を十分に送り出すことができなくなった状態を指すので、虚血性心疾患や弁膜症、心筋症、不整脈などが悪化した結果、心不全に至る、ということもできます。
自覚症状には、息切れ、動機、むくみ、胸痛、脱力感などです。
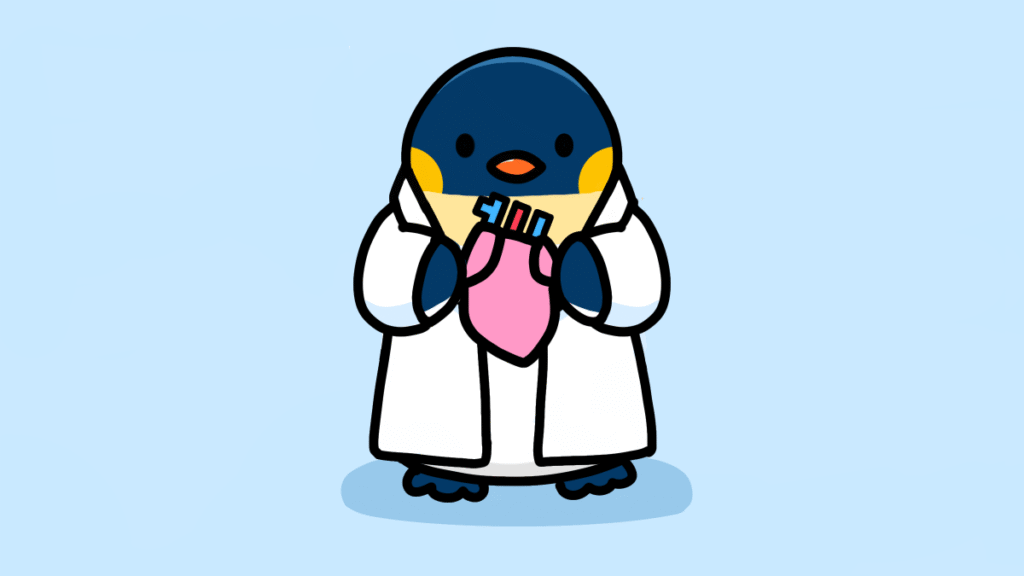
死因の上位を占める心疾患は、血液検査から発見できることもあり、経過観察には血液検査が欠かせないものです。
健康診断で異常を指摘された場合はもちろんのこと、自覚症状があったら放置せず、
また一過性の症状であっても無視せずに、医療機関を受診することが重要です。
検査結果を考えるとき大切なことです
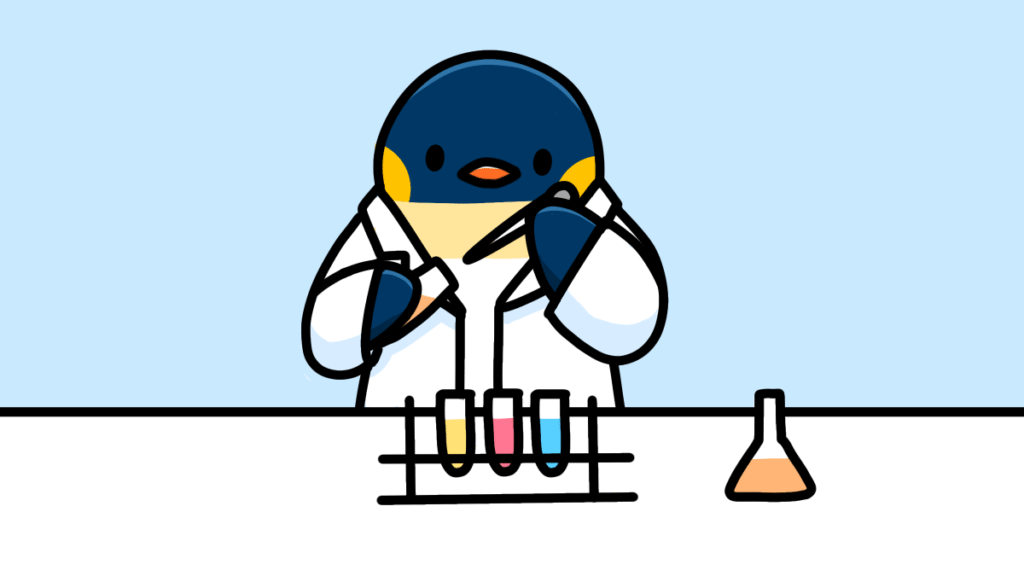
ほかの検査結果に関する記事はこちらからどうぞ

厚生労働省の関連サイトです
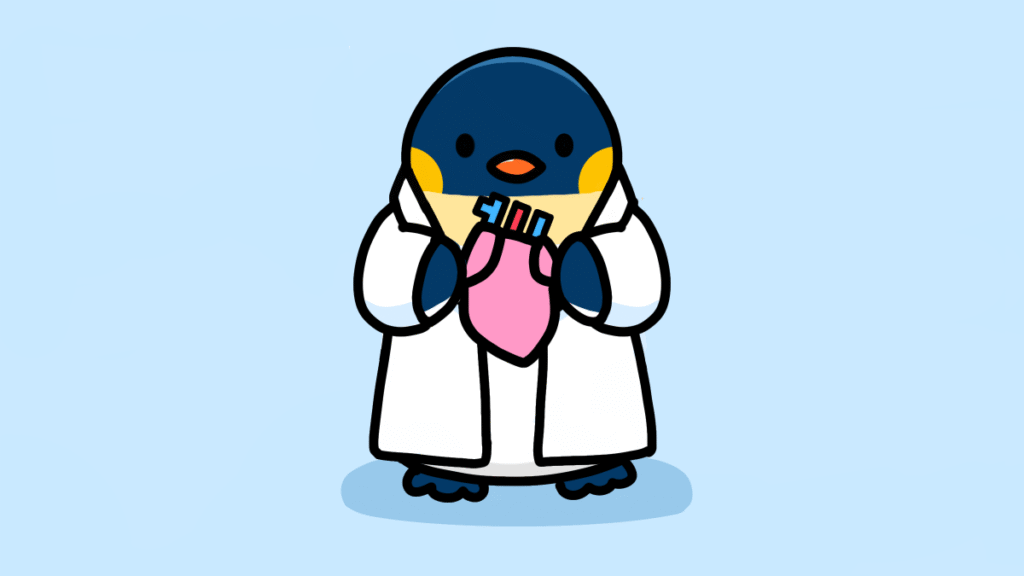

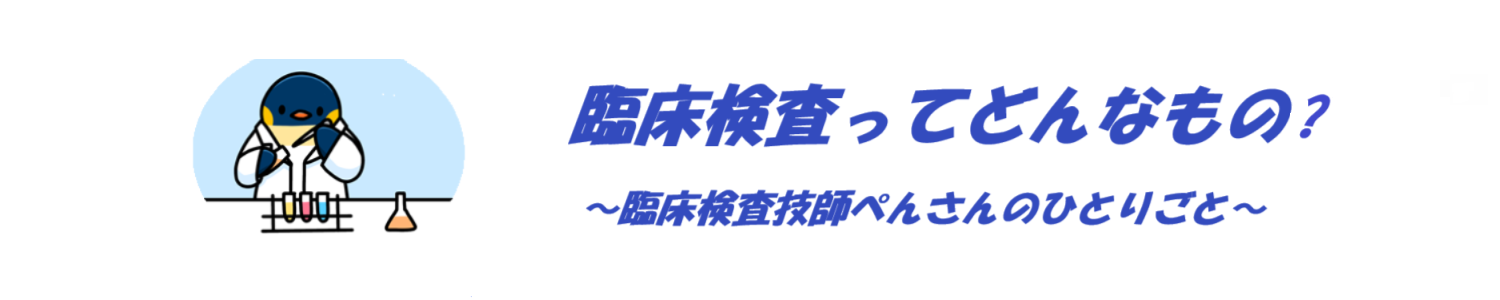


コメント