肝機能検査

肝機能って何をみればわかるのかな?
「肝機能がちょっと良くないですね・・・」と言われたけど、そもそも検査項目の内容が分かり難いと感じたことはありませんか。
ここでは、肝機能に関わる血液検査について少し考えてみようと思います。

肝機能に関わる項目
肝臓
肝臓は体内で最も大きい臓器の一つで、栄養素の代謝、解毒、胆汁の生成などさまざまな機能を担っています。
しかし「沈黙の臓器」とも呼ばれ、異常があっても初期段階では症状が出難いと言われています。健康診断や病院での血液検査の結果をきっかけとして、自覚症状がない段階での肝臓の異常が発見されることは少なくありません。

「肝機能」、つまり肝臓の働きや状態を調べる検査は、採血以外にも、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、また肝生検など、いろいろな検査があります。
肝機能を調べる血液検査
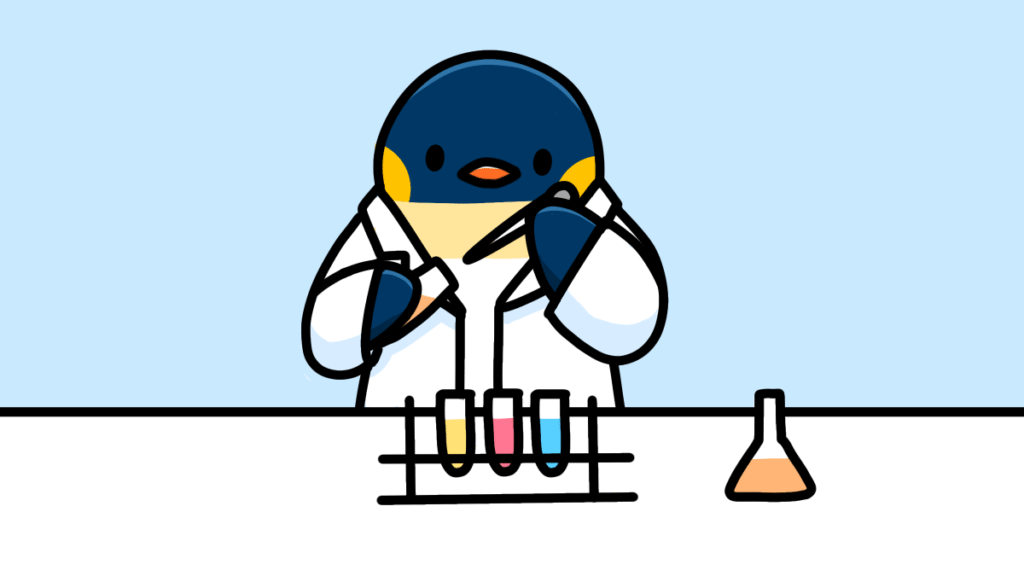
肝機能を確認するための血液検査の項目はいくつかあります。
よく耳にするのはAST、ALT、γ-GTあたりでしょうか。
これらは「逸脱酵素」とも呼ばれます。
「逸脱酵素」は通常は細胞内に存在する酵素が、細胞の損傷などで血液中に放出されたものです。
つまり、肝臓の細胞内にあるこれらの酵素の血中濃度が高いということは、肝臓の障害が疑われるということになります。

酵素は多くの場合、肝臓だけに存在するわけではありません。他の臓器や赤血球内などにも存在する場合があります。
したがって、1つの酵素が高値だからといって、すぐに肝臓の疾患を疑うわけではありません。さまざまな検査項目の組み合わせで判断していくことになります。
いくつかの項目について簡単に説明します。
肝機能検査の結果の考え方
肝機能検査に関わる項目の中で、AST、ALT、γ-GT、ALP、LDは逸脱酵素です。したがって肝臓に障害があると高値となると考えられます。
しかし、ASTやLDは心臓にも存在するため、たとえばこの2項目のみ高値だったら、肝臓の障害の可能性は少ないかもしれません。
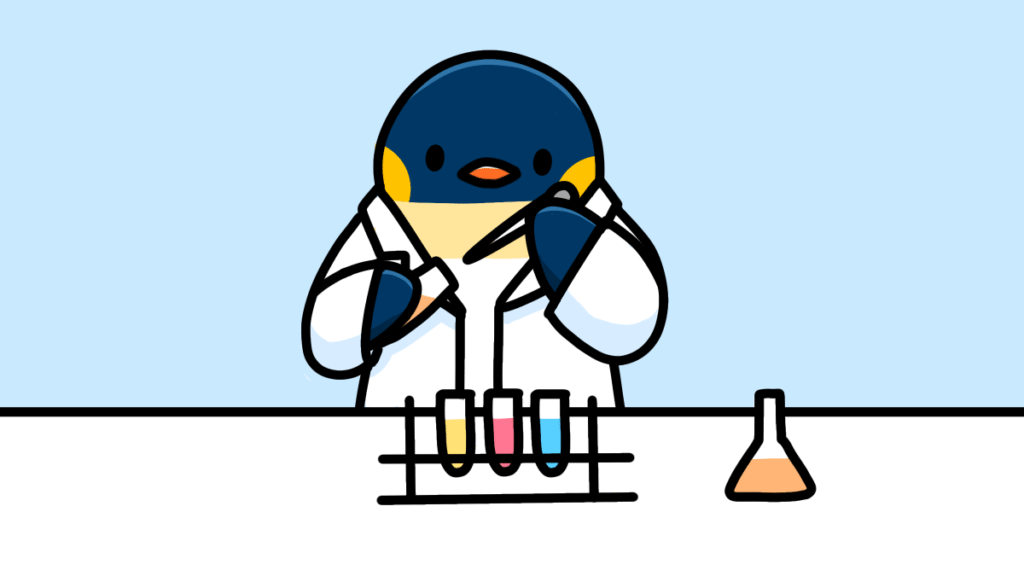
ALPやγ-GTは肝臓に存在するのですが、胆道系の障害をより強く反映する傾向にあります。
またγ-GTは、肝臓の障害の中でもアルコールの影響を受けやすいとされています。
一方、ALTは肝臓特異性が高いとされてるので、ASTより顕著に肝臓の障害を反映すると考えられます。
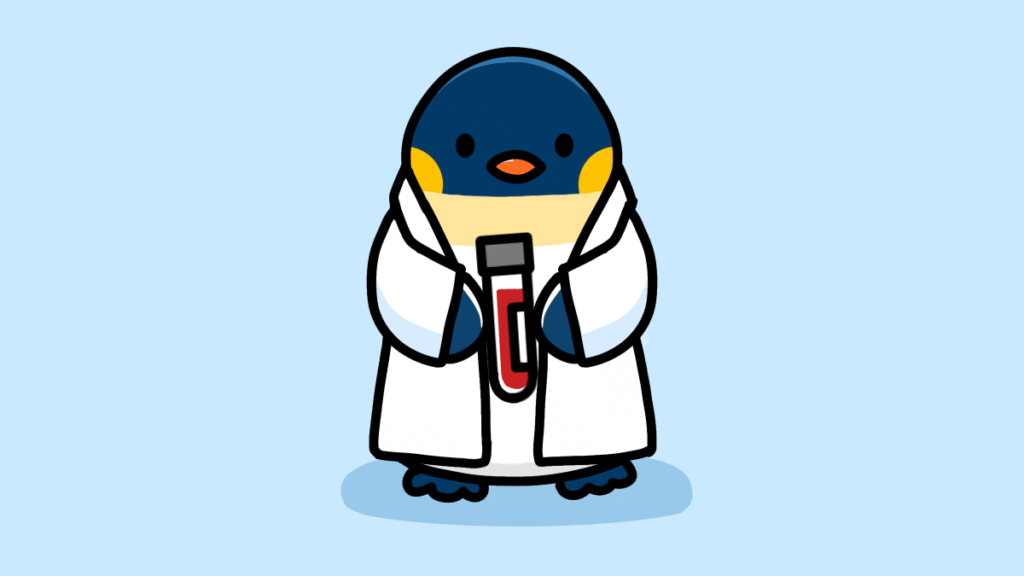
総蛋白やアルブミンは肝臓で合成されるため、肝臓に障害があってうまく機能していないと、血中の値は低くなります。ただ、低値となる理由は他の要因もあるので注意が必要です。

血小板も肝臓に障害があると、破壊が亢進したり生産が減少し、結果として低値となります。
血小板数は肝機能検査として捉えていない場合も多いかもしれませんが、肝臓の疾患の初期の段階から、血小板の低下は少しずつ起こっていると言われています。
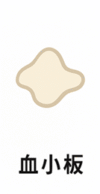
HBs抗原やHCV抗体は、肝炎の原因となるウイルス関連の検査です。健康診断などでも検査されることがあると思います。
陽性の場合、必ず肝機能が低下しているというわけではありませんが、詳細な検査が必要になります。
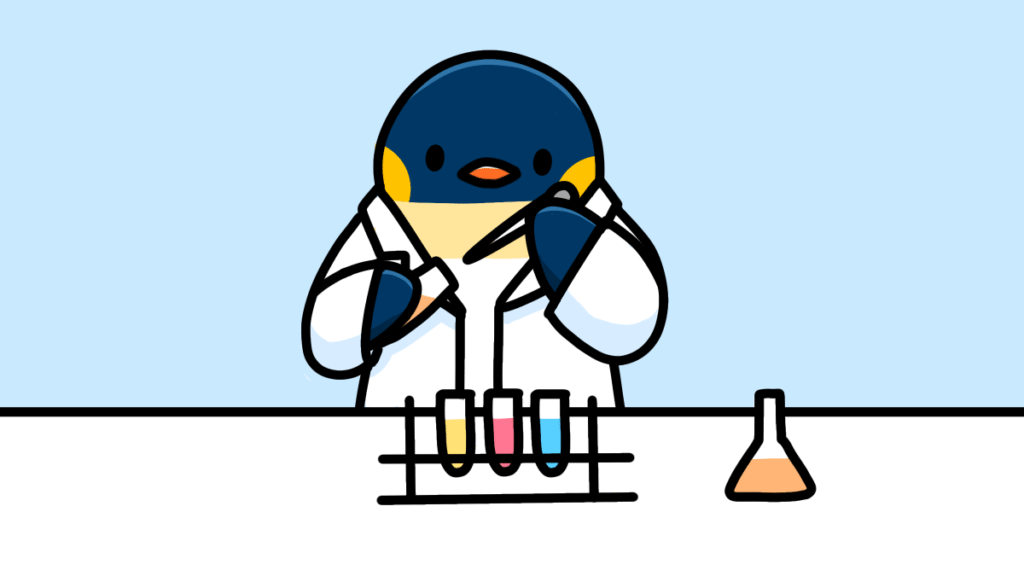
いずれの検査項目も単独の結果で肝機能を評価できるわけではなく、いくつかの項目を組み合わせて判断し、その結果によって次の方針を決めることになります。
こんなことがありました
γ-GTは肝臓の逸脱酵素の一つです。肝臓や胆道系に障害がある場合高値となることが知られています。特に、アルコールの影響を受けやすいと言われています。

健康診断の結果を見て「あっ」と思ったことがある方も多いかもしれません。毎日飲酒をしているような人は、γ-GTの結果が基準値以上の高値を示し、禁酒をすることによって急速に低下すると言われています。
これはもちろん高値の原因がほぼ飲酒によるものの場合です。その他にもさまざまな要因が絡んでいる場合は、禁酒以外の治療なども必要となります。
ところで、飲酒による高値という観点で、こんな経験があります。
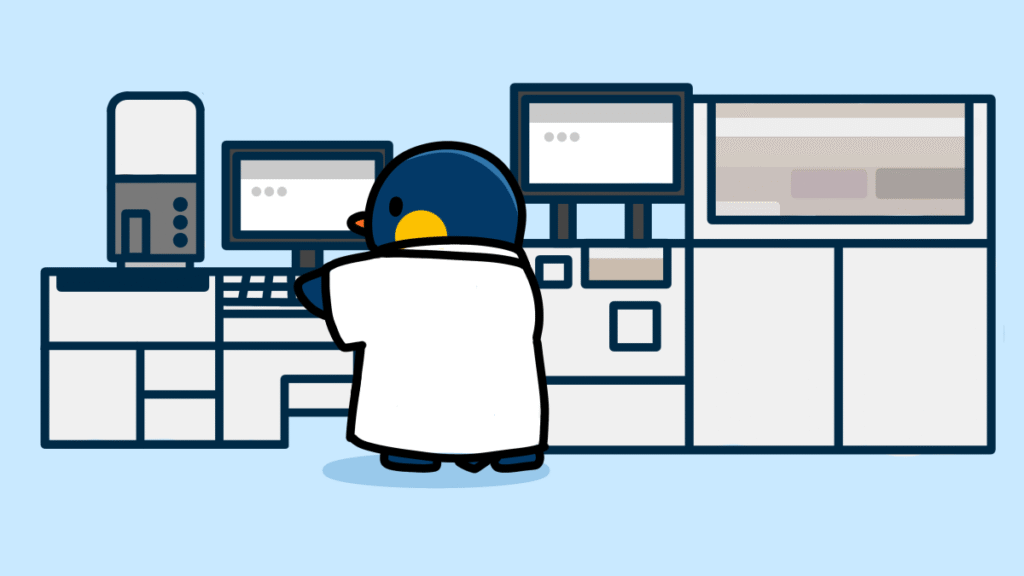
少し前のことですが、生化学検査を担当していた時のことです。検査結果を確認していたとろ、γ-GTの結果が800U/L程度の患者様がいました。消化器科の受診ではなく、他の結果を見てもこの値が飛び抜けて高値の印象でした。γ-GTの結果については緊急報告値として取り決めがあったわけではありませんが、診察後検査だったこともあり、一報だけでもと思い担当医師に連絡しました。

その時の医師の言葉が、「わかりました。ありがとうございます。」の後にぼそっと「大酒飲みなんだよね」と。「いやいや800ですよ・・・」と心の中で思いましたが、γ-GTについて印象的な経験でした。
他にも、一緒に仕事をしていた先輩が、健康診断の結果を見て「γ-GTが3ケタだ」とつぶやいているのを聞いたことがありました。毎日飲酒をされている方で、「ちょっとお酒をお休みしないとな」と言っていました。
肝臓のために
検査でわかること
採血による検査はさまざまなことを教えてくれます。
しかし、一つの結果だけで何かを決めることは難しいといえます。
肝機能に関することだけではありませんが、いくつかの項目の結果を総合的に判定することで、疾患を見つけるきっかけとなります。
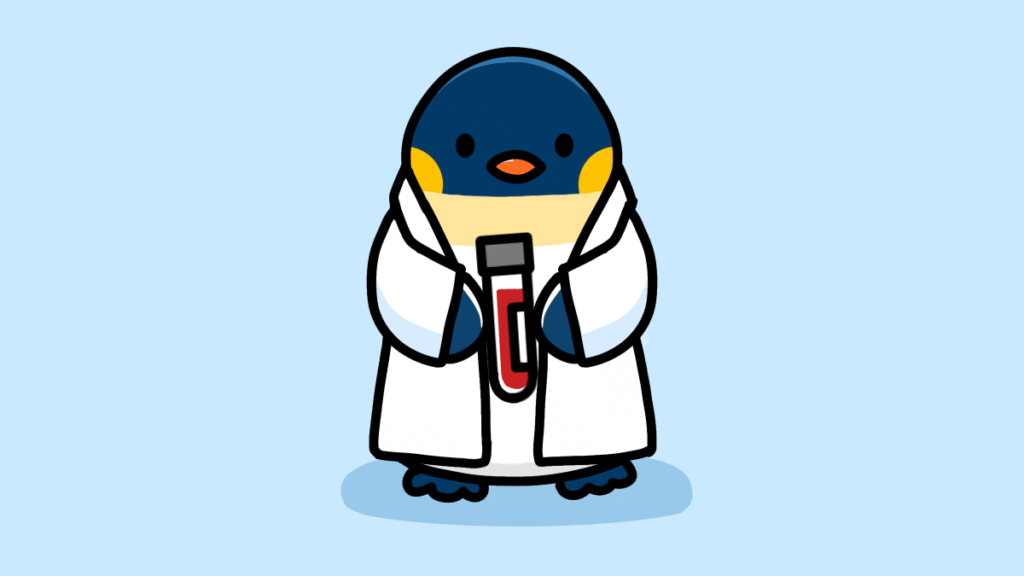
異常値というと高値のことばかりに目が行きがちですが、低値となっていることが重要な情報を示していることもあります。
基準値からどの程度逸脱していたら問題なのか、というのは難しいところです。
しかし、健康診断等で肝機能の異常を指摘されることがあったら、自覚症状の有無に関わらず、医療機関の受診をするべきです。

肝臓のために
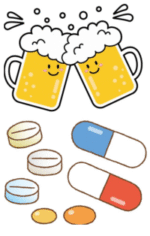
アルコール以外にも、薬剤などでも一過性に肝臓の障害が起こることがあります。それは軽く済むこともありますし、重篤になる場合もあります。
健康診断のタイミングで何か薬を服用していて、それが肝機能検査の数値に異常をもたらすこともあるかもしれません。
しかし、「お酒を飲みすぎたから」とか「薬を飲んでいたから」などと自己判断は禁物です。
きちんと調べて何ともなければそれで良し、自覚症状がない早期に異常を発見できれば治療も早く始められ、治癒に繋がるのです。
健康診断でも病院での検査でも、検査結果は医師に判断を仰ぎ、指示に従うことが大切です。
検査結果を考えるとき大切なことです
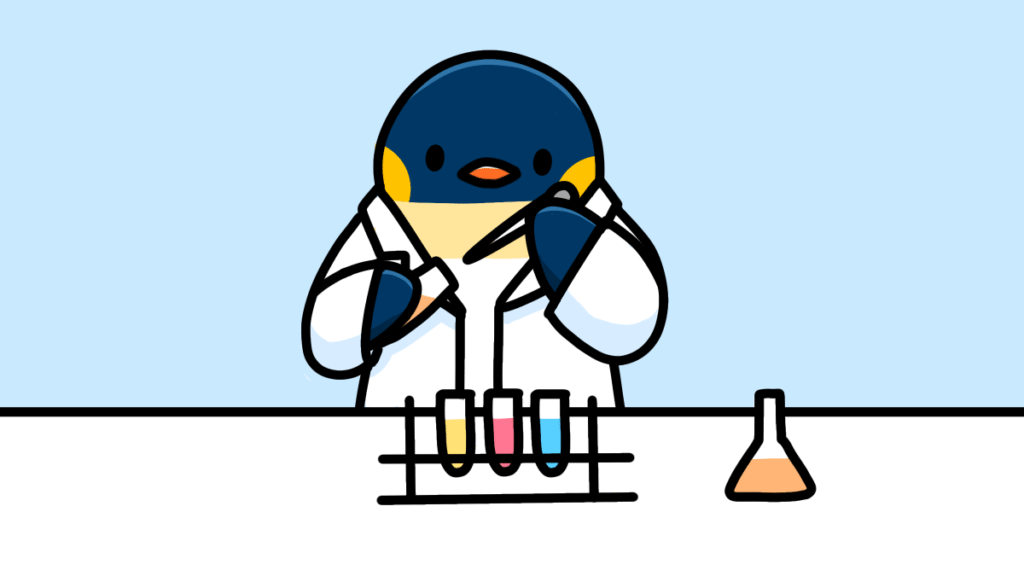
ほかの検査結果に関する記事はこちらからどうぞ

肝臓に関するサイトです


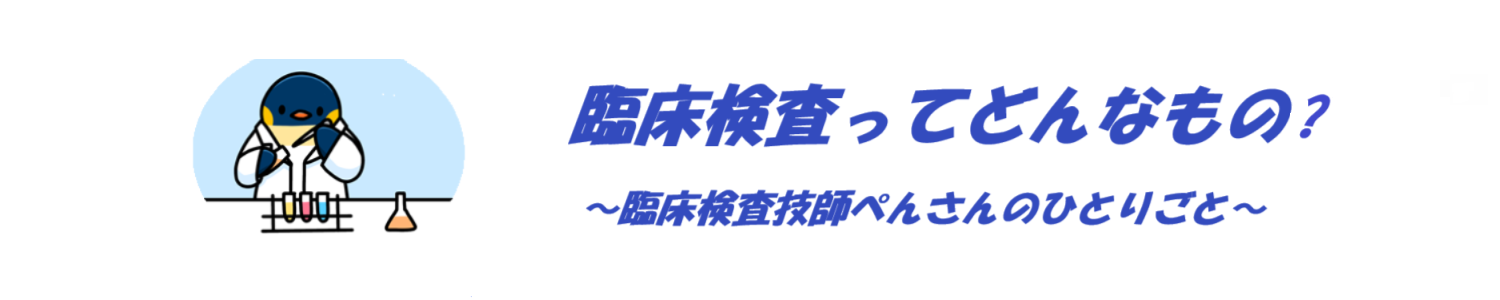


コメント