便潜血検査とは

便潜血検査って健康診断でよくやるけど、どんな検査なのかな・・・。
「便潜血検査」は、職場の健康診断や人間ドックなどでお馴染みの検査ではないでしょうか。
でも、どのような検査か、何に注意すればよいか、など、どのくらい正しく理解できているでしょうか。
「便潜血検査」について、あらためて考えてみます。

便潜血検査を受けるにあたって
便潜血検査とは
便潜血検査は、便に血液が混じっていないかを調べる検査です。
大腸がんや大腸ポリープなどの早期発見のためのスクリーニング検査として利用されています。
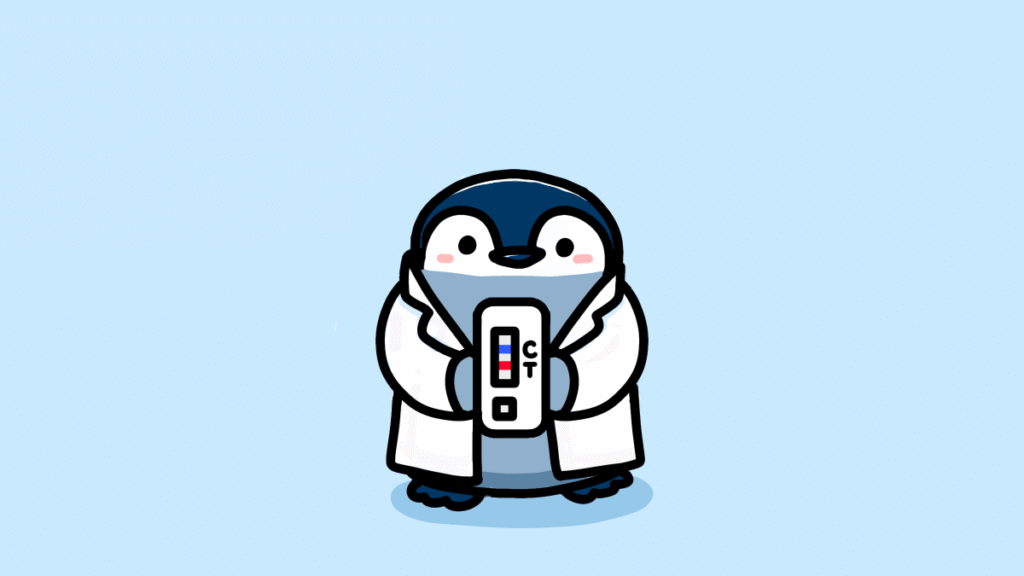
目に見えないような微量の血液が検出できるため、大腸がんの早期発見に役立つとされています。
通常は便に血液が混じることはないので、便潜血検査の基準値は陰性です。陽性の場合は、大腸がんなど何らかの異常があることが疑われます。

しかし、陰性だからといって、大腸がんや大腸ポリープなどがないとは言い切れないので注意が必要です。
便潜血検査の採便
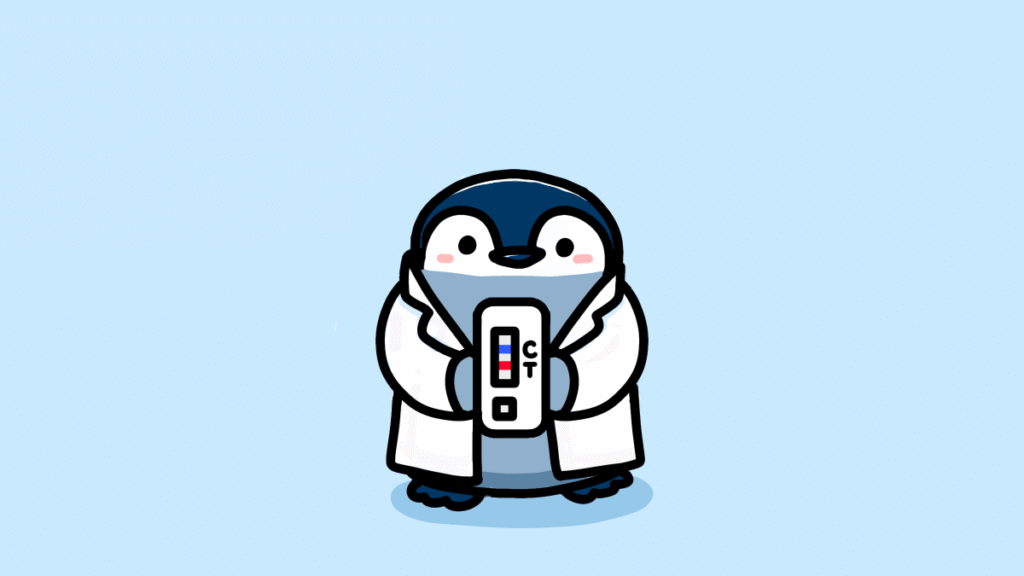
大腸の表面にポリープや癌があるとします。
その大腸の中を便が通る時に、表面をこすることによって、ポリープや癌から出血した血液が便の表面に付着します。
便潜血検査はこの血液を検出します。
採便にあたって注意すること
採便にあたっては、添付されている説明書をよく読んでいただくことが大切です。

採便する容器は、蓋にスティックが付いているタイプが一般的で、蓋はカチッというまで押し込むものやスクリュータイプのものなどがあります。容器の中には便を保存するための液体が入っていますので、それは捨てずに採便します。
一般的に気をつけたいことをいくつかあげてみます。
便潜血検査について
便潜血の検査法には化学的方法と免疫学的方法があります。

通常、健康診断や癌健診で実施されているのは免疫学的方法です。
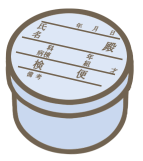
施設によって異なると思いますが、20年くらい前まで(正確ではありません。凡そです)は、便潜血検査というと、「お肉を控えてください」などというお食事に関する説明を必ずしていました。それは化学法で検査をしていたからです。
採便は、便をいれる容器を渡され、「親指の頭くらいの量を入れてください」などと説明されていました。

現在では免疫学的方法になり、採便容器も変わりました。
スティック状の採便棒が付属した細い筒状、あるいは細ながく平たい容器を渡され、食事の制限などもなくなりました。
こんなことがありました
便潜血検査もいろいろなことがありました。多くは、やはり採便に関してです。
以前の化学的方法の時は、便を直接検査用台紙に塗布するのですが、容器を開けてびっくり・・・ということは少なくなかったと思います。

容器いっぱいに採便されている場合は、容器の蓋の開け閉めにも神経を使いますし、逆に小さい堅い便がコロッと入っていると、検査用台紙に塗布するのに一苦労、などということもありました。「これでも入れたつもりなのだろうか」と思うほど少量のこともありました。
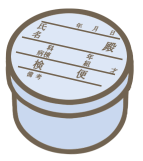
2法なので台紙の2か所に直接塗布して試薬を滴下するため、やはりある程度の量は必要で、少な過ぎるときちんと塗布できているのだろうかと不安に思うこともありました。結果が陽性であれば、とりあえず検査はできたと考えますが、2法とも陰性の場合は量不足とした方が良いか悩んだものです。

現在のような免疫学的方法が主流となっても、採便に関する問題はいろいろあります。

まず、見た目に便が確認できない時。この場合、採便忘れなのか採便量が少な過ぎたのかの判断に迷います。患者様から検体を受け取ってすぐに容器を確認すれば、その場でお聞きすることもできるのかもしれませんが、多くの場合、検査受付けなどで検体をお預かりしてあとからまとめて検査をするので、ご本人に確認することは難しくなります。

そこで、「とりあえず検査してみる」が発動します。これで陽性であれば検査としては完了です。陰性の場合は悩ましい・・本当に陰性なのか、検体が少な過ぎてきちんと検査できていないのか、あるいはそもそも検体が入っていないのか・・・。検査窓口に検体として提出されているので「検体が入っていない」という選択肢は(語弊があるかもしれませんが)正直なところ考えたくない。そこで「検体量が少ないため参考値」となる場合が多かったと思います。
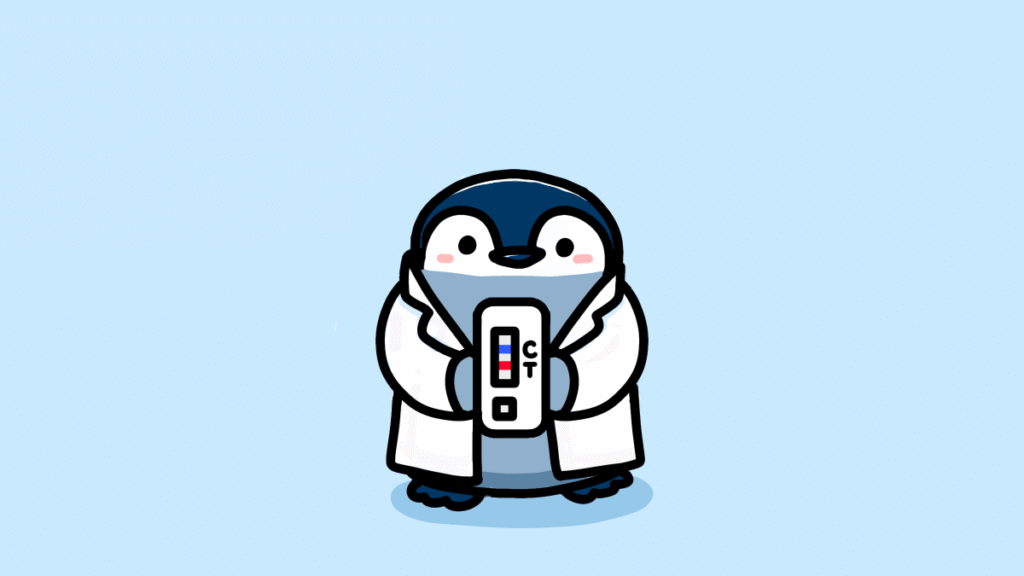
逆に多すぎるのも良くありません。免疫学的検査では、検査用プレートに、直接、採便容器から便懸濁液を滴下します。ヒトヘモグロビンに対する抗体を使った抗原抗体反応による検査なので、検査用プレートに滴下する便懸濁液には「適切な濃度」があります。それは、適切な量を採便すれば十分達成できるものです。採便量が多いと抗原量が多すぎることになり、正しく反応しなくなります。

ただ「適切な量」には幅があるので、それほど神経質にならなくても大丈夫です。問題となるのは、「どうしてこんなに入ってのだろう」と考えてしまうくらい多い場合です。このほか、採便容器の使い方が誤っている場合もありました。
どれも、添付されている説明書をきちんと読んでいただければ、ご理解いただけることなのではないかと思うのですが・・・。
便潜血の検査結果
便潜血の結果は「陽性」か「陰性」で判定されます。
便に血液が付着していなければ「陰性」となります。
基準値は「陰性」です。
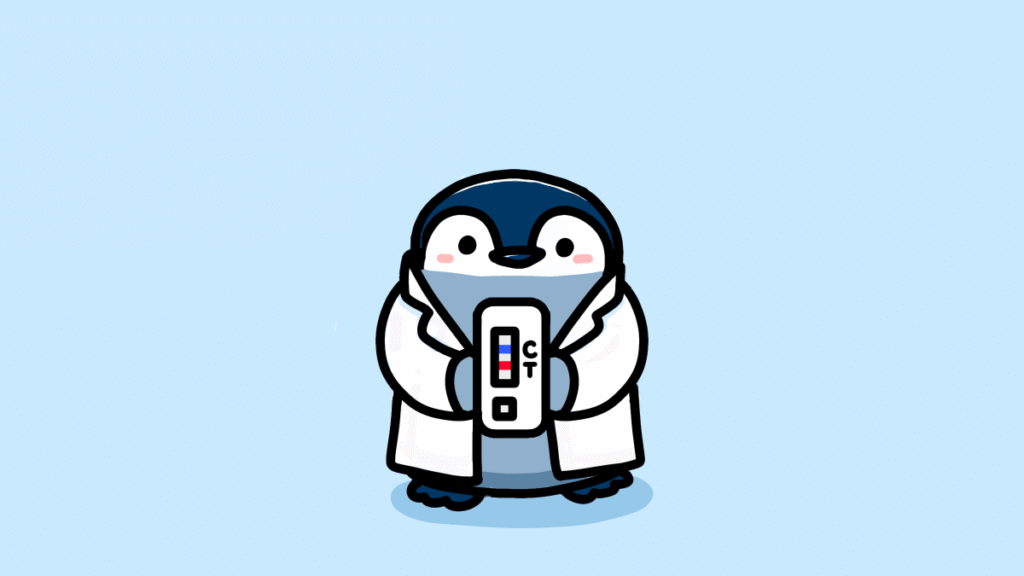
結果の意味
検査結果が「陽性」「陰性」で示される検査は、一般的に「偽陰性」「偽陽性」の可能性を考慮する必要があります。便潜血検査の場合も同様です。
「陽性」の結果
現在のように免疫学的方法によって検査を行う場合、化学的方法に比べて「偽陽性」は減ったと言われています。
免疫学的測定法は、ヒトヘモグロビンに特異的に反応します。
つまりヒト以外の血液に反応しないという点で、偽陽性は減ったといえます。
したがって、「陽性」の結果が出た場合、何らかの出血があるということになります。
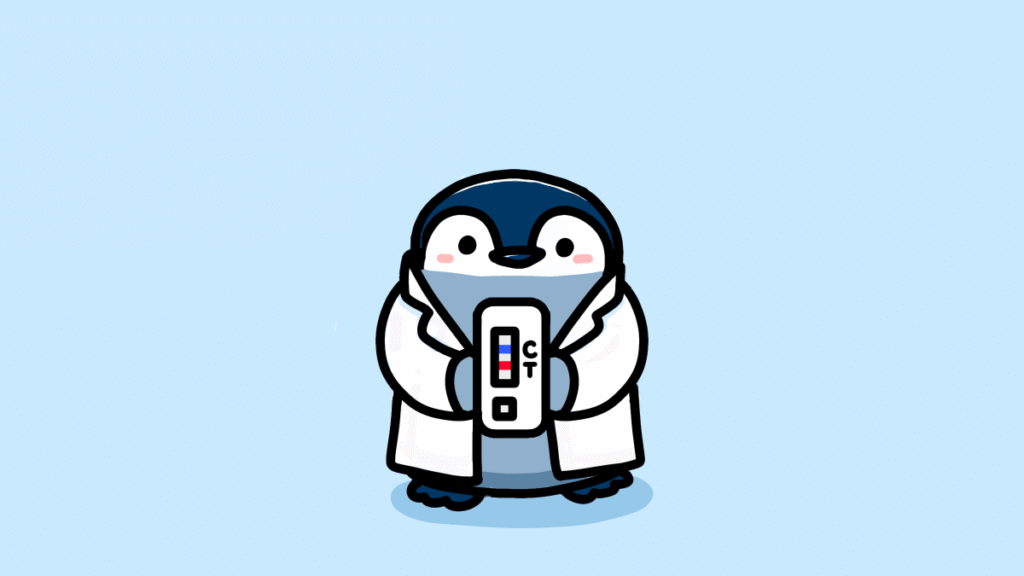
しかし、必ず大腸に癌やポリープがあるということではありません。痔などの出血かもしれません。
したがって、便潜血の結果が「陽性」だった場合には、再検査や精密検査を受けることが推奨されます。

「陰性」の結果
では「陰性」だった場合はどうでしょうか。
「陰性」は、あくまでもその便について、血液を認めないということです。

採便が、まんべんなく便の表面から適切に行われていたとしても、その時のその便には血液を認めないということです。
そもそも採便が、便の一部の部分からしか行われていなかったとしたら、その便の他の部分に血液があったかもしれないと考えられます。
また、検査に提出したその排便では、「血液が付着しなかった」ということも考えられます。
つまり、「陰性」は消化管に異常がないことの証明にはならないのです。
便潜血検査の意義
便潜血検査の有用性
便潜血検査は大腸がんのスクリーニング検査に有用だとされています。
「陰性」だからといって、消化管に異常がないことの証明にはなりません。こういうと、「検査を受けても意味がない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、毎年検査を受けることで大腸がんの死亡率が低下するという報告もあります。

検査の性質上、「陰性」だからといって「もう心配はない」と思ってしまうことには、あまり賛成できません。
しかしだからといって、必要以上に心配する必要はないと思います。定期的に検査を受け、専門医に判断してもらうことが重要といえます。
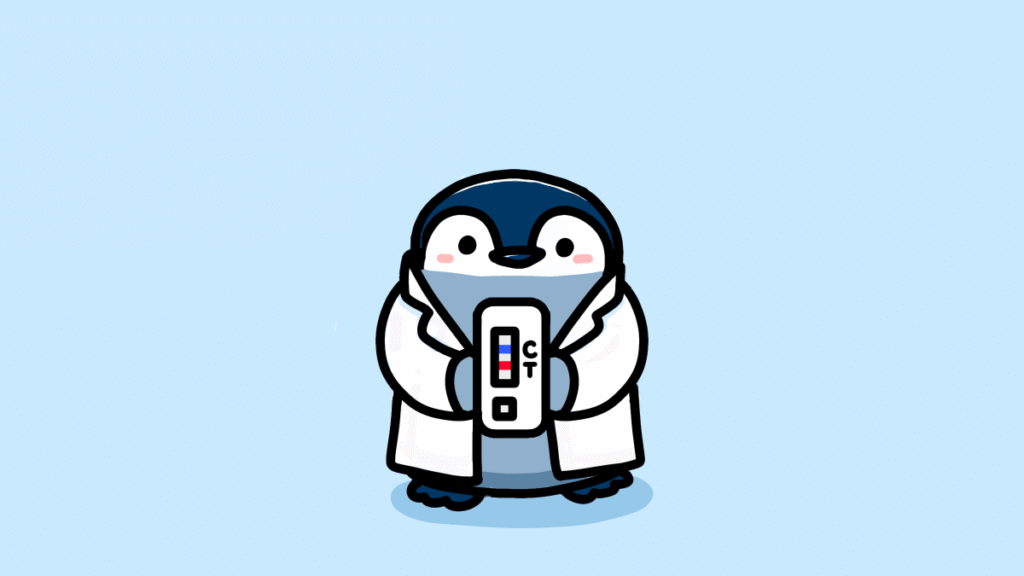
正しい結果を得るために
便潜血検も他の検査と同様に、検体採取からはじまっています。
検査説明や添付の説明書等を十分理解した上で、正しく採便することがまず第一歩です。

そして検査を受けたら、結果は自己判断は禁物です。
必ず医師の判断を仰ぎ、指示に従うことが大切なのです。
ほかの便の検査についてはこちらからどうぞ
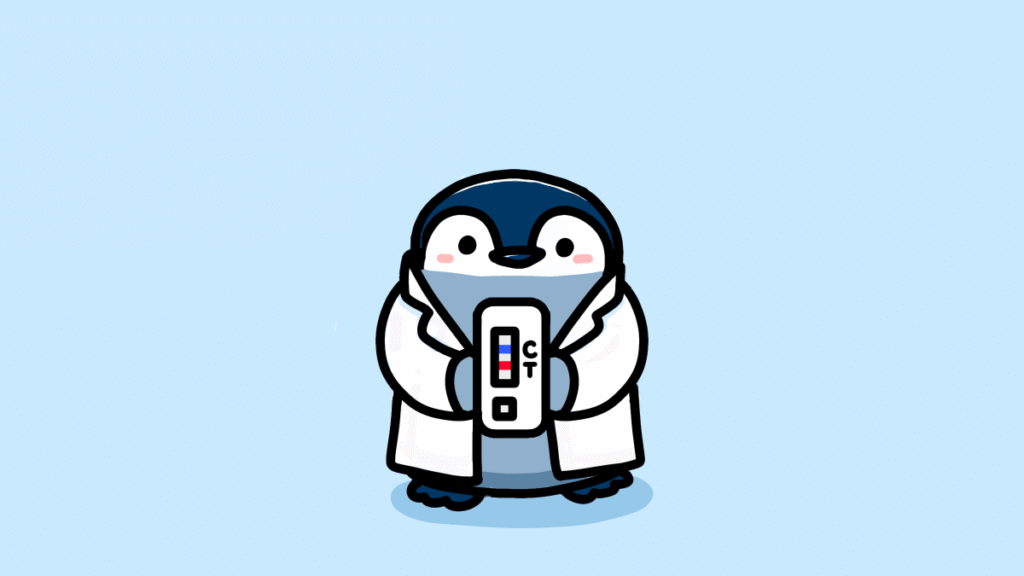
大腸がんについてのサイトです


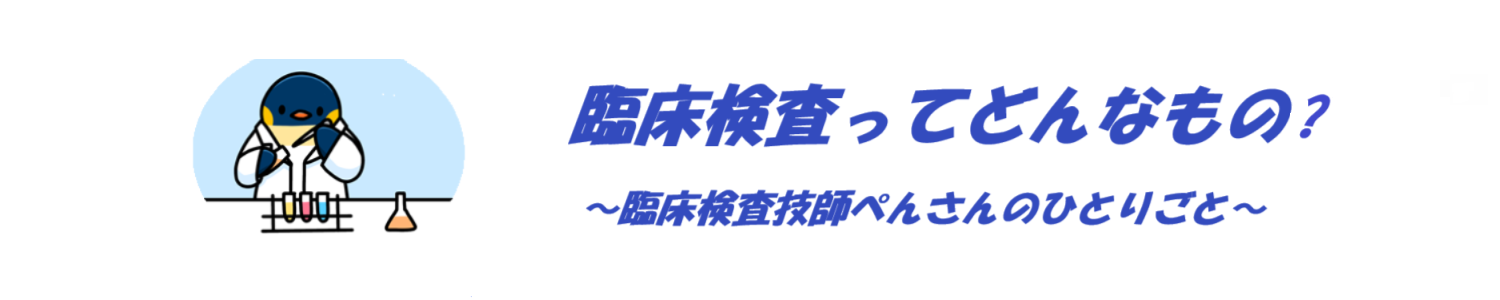



コメント