パニック値とは

「パニック値」ってなんだろう
「パニック値」は「生命が危ぶまれるほど危険な状態にあることを示唆する異常値で直ちに治療すれば救命しうるが、その診断は臨床的な診察だけでは困難で検査によってのみ可能である」と定義されています。
一般の方は聞きなれない言葉だと思いますが、結果を判定する上で見逃してはいけない値であり、対応の不備が医療事故の原因にもなりかねない値といえます。
ここでは、この「パニック値」について考えます。

パニック値と極端値
まず、パニック値を考える上で、区別しなければならない概念として「極端値」があります。
「極端値」とは、まれにしかみられない検査値です。
統計的には0.5パーセントタイル値~1.0パーセントタイル値以下、99.0パーセントタイル値~99.5パーセントタイル値以上を想定しています。
またこれには、検体採取条件などの分析前誤差や検査過誤に起因する異常値も含まれます。

パニック値は定義にあるように、「生命が危ぶまれるほど危険な状態にあることを示唆する異常値」なので、分析前誤差や検査過誤による異常値は当然区別されなければなりません。
こんなことがありました
こんな経験があります。
外来ですが他院から搬送されてきた患者様の採血検体を検査していたところ、グルコースが1000㎎/dl という値がでました。
この値は施設などに関係なくパニック値です。通常の検査の中では、あまり経験することのない異常値で、「こんな結果あり得ない」という技師もいるかもしれません。

この値を報告するにあたっては、検査過誤でないことを確認する必要があります。また、患者様が点滴をしていた場合、採血時にその点滴の薬剤が混入するとこのような値になることは知られていることなので、そのような事実がないかどうかも確認する必要があります。しかし、本当に患者様の値なのであれば、大至急に処置しなければなりません。

そこで、再検査をはじめつつ、提出医に連絡をしました。
「今再検をしているところで、第一報なのですが」と前置きをした上で、「グルコースが1000㎎/dlなのですが、先生、この患者様点滴していますか」と問い合わせました。
電話の向こうの医師は、一瞬固まった感じでしたが「いや、点滴はまだしていない」と即答でした。
そうすると、検査過誤でなければとんでもない値です。医師は続けて「とりあえずもう一回採血するよ」と。
再検査の結果は変わらず、また再採血も同様の結果で、すぐに処置がされました。
これは私が実際に経験した症例です。
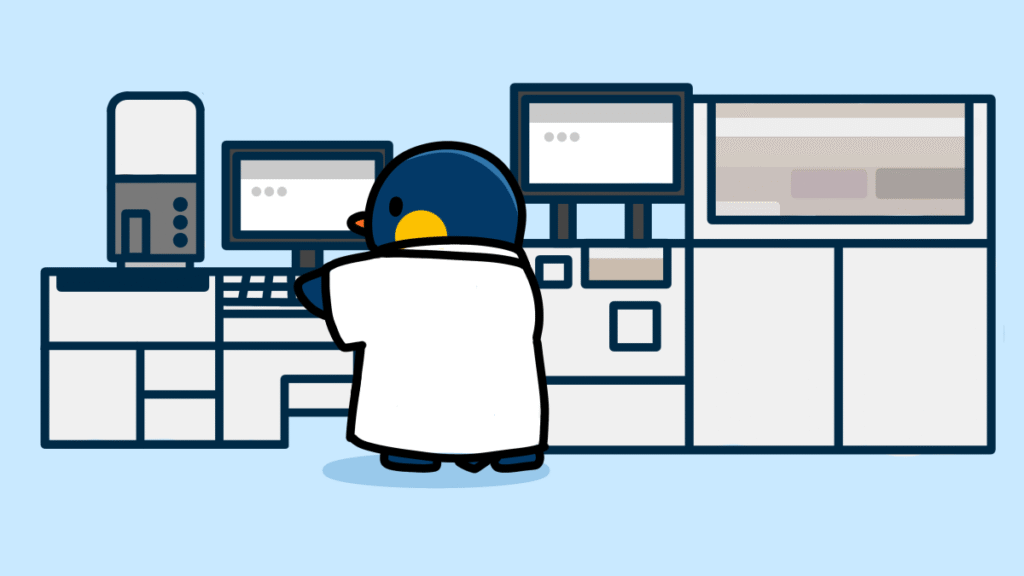
「点滴の混入」というのは、あってはならないインシデントなのですが、実際の医療の現場ではまま起きています。
たとえば採血した人が検査をしていれば、結果を見た時にすぐに思い当たるかもしれませんが、検査科で検体を受け取って検査をしている場合、採血時のインシデントは想像でしかありません。

また、点滴が混入した検体の検査を経験して、その影響について学習してしまった技師は、次に同様な結果を見た時に「これも点滴だろう」と勝手に思い込んでしまい、対応が後手に回る場合もあります。

真の「パニック値」は、分析前誤差や検査過誤と区別されなければなりません。しかし、測定値だけを見た時、その区別が難しいことが多いのも事実です。したがって、患者様の生命を守るためには、他の医療スタッフとのコミュニケーションも重要になります。

臨床検査技師は、検査過誤を起こさない努力とともに、思い込みも持たず、真摯に検査結果と向き合わなければなりません。「こんな結果あり得ない」と思うのではなく、なぜこの結果になったのかを考える姿勢も必要でしょう。
パニック値の設定
現場の事情
「パニック値」はその意味するところからして、迅速かつ確実に、提出医に伝えられなければなりません。

パニック値の報告は、診察前検査の至急報告などとは区別されるべきものです。
医師が救命のためにすぐに対処できるよう、確実かつ速やかな報告が必須です。
通常、直接の電話連絡などの手法で報告されます。

しかし、医師の状況を想像すると、診療中などで忙しい臨床医が電話を受けるのは、難しいことも多いと思われます。
また、電話する検査科にとっても、直接医師に電話をするという作業は、なかなか手間もかかりハードルが高いもので、正直なところ、できれば避けたい作業ともいえます。
パニック値の設定
一般的に、直接報告すべき「パニック値」は、項目を厳選して設定すべきとされています。
「パニック値」として報告が必要な値は、各施設の事情によって変わります。
そのため、それぞれの施設で臨床医と協議の上、その施設ごとのパニック値を決定すべきとされています。

「生命が危ぶまれるほど危険な状態にあることを示唆する異常値」として容認できる値は、ある程度は共通認識として設定することができます。
しかし、実際に運用するために細かく設定しようとすると、診療科ごと、入院・外来の別、こどもと成人の別、などさまざまな要因で、共通認識が崩れてしまうことになりがちです。

たとえば、各診療科からパニック値として報告が必要な値を収集したとします。そうすると、極端な言い方をすると、診療科が5科あれば、5通りの値が提示されることになります。

どの科の値が重要とか、そのようなことは当然ありません。
しかし、だからといって、すべてを網羅するような値を定めると、科によっては不要な連絡を受けるということも起こり得ます。

診療科ごとにパニック値を定めれば良いのではと、思われるかもしれません。そして患者様ごとに、きちんと診療科を確認して報告すれば良いだろうと、思われるかもしれません。
しかし、実際にそのような運用を、どんな時でも正しく実践することは不可能だと思います。

報告する側が間違いなく、見落とすことなく、パニック値を報告するためには、できるだけ単純明快な形で設定している必要があるといえます。
パニック値は、24時間365日、どのタイミングで検査したとしても確実に対応しなければなりません。施設によりますが、その検査をふだん担当していない当番の技師が対応する場合もあります。誰が担当しても正しい対応ができるような配慮も必要といえます。

パニック値の運用のために
検査科と各診療科との協議はなかなか難しく、全診療科が納得する値を設定することは正直困難だと思います。

しかし、迅速で適切な処置のため、また、患者様の生命を守るため、パニック値の設定は重要です。
パニック値の見落としや、伝達不備による医療事故も残念ながらなくなりません。

適切なパニック値を設定するため、関わるスタッフは、さまざまな情報を共有し、有用な議論を重ねるべきです。スタッフ間での多少の譲歩も必要かもしれません。
そしてすべての医療スタッフが、パニック値を正しく理解し共通の認識を持てるよう努めるべきだと思います。
さらに理解を深めるためにこちらもどうぞ






コメント