
「こんなことがありました」を集めた第2弾です。
臨床検査技師として仕事をしている中ではさまざまな出来事があり、そのひとつひとつが学びとなり大切な経験となっています。それらの中から記事の内容に関連したものを、「こんなことがありました」と題して書いています。
これを読んでいただくことで、僅かでも検査についての理解が深まれば良いと思っているのですが、とりあえずあまり難しく考えずに「ちょっと面白そうかも」と興味をもっていただければと思います。そしてそれぞれの記事を読むきっかけになると嬉しいです。
「γ-GTPが800U/L です」と医師に伝えたら
肝機能に関する検査項目はいろいろあります。その中で、アルコールの影響を受けやすいことが知られている項目としてγ₋GTがあります。健康診断の結果で思い当たる方もいらっしゃると思います。飲酒とγ-GTの結果について、分かりやすい経験をご紹介します。
γ-GTは肝臓の逸脱酵素の一つです。肝臓や胆道系に障害がある場合高値となることが知られています。特に、アルコールの影響を受けやすいと言われています。
健康診断の結果を見て「あっ」と思ったことがある方も多いかもしれません。毎日飲酒をしているような人は、γ-GTの結果が基準値以上の高値を示し、禁酒をすることによって急速に低下すると言われています。これはもちろん高値の原因がほぼ飲酒によるものの場合です。その他にもさまざまな要因が絡んでいる場合は、禁酒以外の治療なども必要となります。
ところで、飲酒による高値という観点で、こんな経験があります。少し前のことですが、生化学検査を担当していた時のことです。検査結果を確認していたとろ、γ-GTの結果が800U/L程度の患者様がいました。消化器科の受診ではなく、他の結果を見てもこの値が飛び抜けて高値の印象でした。γ-GTの結果については緊急報告値として取り決めがあったわけではありませんが、診察後検査だったこともあり、一報だけでもと思い担当医師に連絡しました。その時の医師の言葉が、「わかりました。ありがとうございます。」の後にぼそっと「大酒飲みなんだよね」と。「いやいや800ですよ・・・」と心の中で思いましたが、γ-GTについて印象的な経験でした。
他にも、一緒に仕事をしていた先輩が、健康診断の結果を見て「γ-GTが3ケタだ」とつぶやいているのを聞いたことがありました。毎日飲酒をされている方で、「ちょっとお酒をお休みしないとな」と言っていました。
これは、肝機能検査の中のγ-GTについて、飲酒との関係を示す印象的なエピソードです。医師が最後にボソッと言った一言が、核心を突いていると思った記憶があります。γ-GTが飲酒によって高値となるということを端的に表しているといえるのではないでしょうか。健康診断などでも検査することが多い項目について知ることは、健康管理にも役立つのではないかと思います。
記事では肝機能検査に関わる血液検査の項目について、主な項目の説明や結果の考え方などについて書いています。
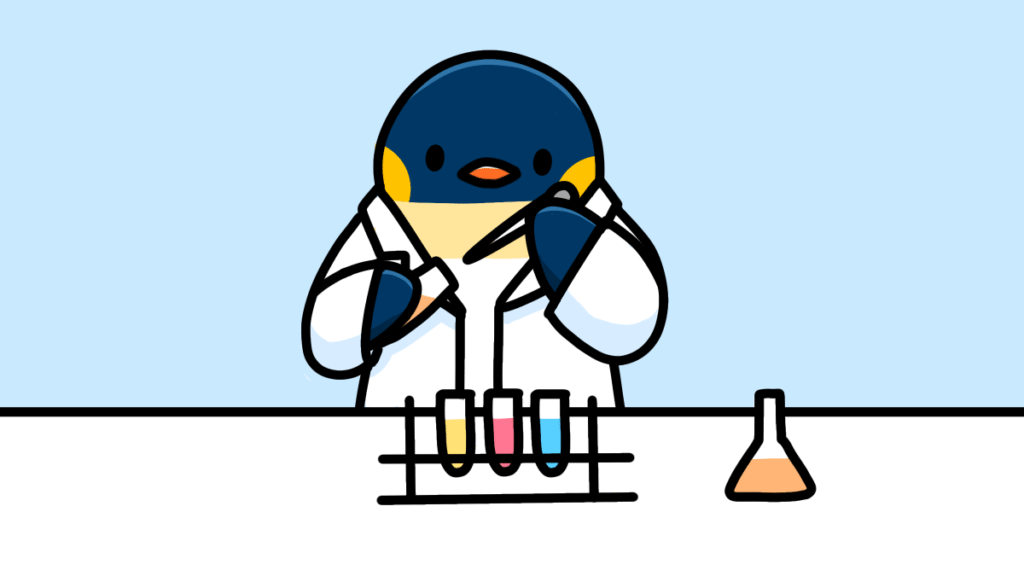
肝機能検査に関する血液検査について、次の記事で説明しています。
血糖値50mg/dl 、これは医師に連絡が必要な低血糖。でもHbA1cの値は・・・
検査項目は数多くありますが、その中で、同じような目的で検査している項目もあります。「血糖」と「HbA1c」も血糖値のコントロールという同じ目的の検査といえますが、それぞれの値が意味するところが異なります。意味が違うからこそ、同時に検査をしているともいえます。実際に検査室で経験した検査結果をご紹介します。
血糖値は食事の影響を受けるため、病院によっては、血糖検査の採血時には、何時に食事をしたかを確認する場合があります。しかし、採血時に食後何時間だったかわかったとしても、厳密な影響を推測することは難しいので、血糖値の評価には食事の影響を受けないHbA1cやグリコアルブミンも用いられます。
血糖の検査があるからといって採血前日や当日の食事を控えて行った結果、血糖の結果は正常だったとしても、HbA1cの値が高値では、食事の管理などができていないことが判明してしまいます。
具体的な数値は記憶していないのですが、たとえば、糖尿病で通院中の患者様。午後の受診で、15時ごろ来院、昼食はとらないまま採血となっていて、検査をすると、血糖値は50㎎/dl程度。これは低血糖で医師に報告が必要な値です。しかし同一患者様のHbA1cを見ると、9%で高値。意図してかどうかは不明ですが、血糖値があまりに高いと当然診察時に指導が入ります。患者様の心理としては「血糖値はクリアしたい・・・」というのでしょうか。しかしHbA1cの値で、血糖のコントロールがあまり上手くいっておらず、高血糖の状態が続いていたことが容易に推測されます。ちなみにこの場合、医師に血糖値の連絡はしましたが、患者様は採血後に食事をとって低血糖発作などには至りませんでした。こういうケースは、残念ながらそう珍しいことではありませんでした。もちろん低血糖は、不規則な食事だけでなく、インスリン注射のタイミングの問題など、いろいろな要因も関係します。ただ、健康診断などでも同様のことがいえます。健康診断は空腹時採血が行われることが多いので、血糖値は正常、しかしHbA1cは高め、というケースがあります。これは血糖とHbA1c、それぞれの特性の違いによるもので、複数の検査を組み合わせる意味の1つといえます。

血糖やHbA1Cなど、糖尿病に関わる検査の概要と結果の考え方などについて、次の記事で説明しています。
これは、血糖とHbA1cの違いを示すエピソードです。低血糖は命に係わる状況ですが、このような事例は、血糖値の管理で定期的に受診している患者様の場合には、さほど稀ではなく、2項目を検査する意味を再認識した出来事でもありました。この2項目の検査で、「今は血糖値が低いけれど、日々は高血糖が続いている」という状況が推測できるということが、少しご理解いただけるのではないかと思います。健康診断などでも馴染みのある項目について知ることは、結果を正しく理解し、健康について考える上でも役立つのではないかと思います。
記事では、糖尿病について、また糖尿病に関わる検査について、主な項目の説明や結果の考え方などを書いています。
提出された尿検体、無色透明、そしてやけに冷たい・・・
「尿検査」は、一般的に、検査を受ける側にとっては痛みを伴わない簡単な検査と思われていると思います。でも、採尿できない時、あるいは採尿したくない時、というのもあるでしょう。採尿に関する検査室での苦労を少し、経験の中からご紹介します。
採尿に関しては、こんな経験があります。
尿検査のため所定の場所に尿が提出されました。検査のため尿が入った尿コップを回収すると、まず、冷たい。尿を見ると無色透明。とりあえず定性検査を始めてみますが、結果はすべて陰性です。この場合何を疑うかというと、「水」の混入です。ご本人に確認をとるのが一番確実なのですが、これはデリケートな問題でなかなか難しいものです。それでも、ご本人とお話ができた時には、「コップをトイレの中に落としてしまい、すぐ拾ったけど水が入ってしまったかも」というのが多い返答だったと思います。さすがに手洗い用の水道で水を入れるわけではないのかと思いますが、「尿が出なくて水を入れてしまった」と言われたこともありました。ご本人とお話が難しい場合は、提出医にその状況を説明して対応を相談したこともあります。そうです。「水の混入」はもちろん日常的に起こることではありませんが、「非常に稀なこと」でもないのです。
また、便の混入も経験があります。これも採尿し直していただきたいのですが、このお話もデリケートな問題で、なかなか外来の待合室などで確認し難いものです。この場合はできる限り検査をしてコメントを付記したり、医師に直接説明をしたりして対応しました。
小児科の尿検査では、ガーゼの糸様のものが混入した尿を経験したことがあります。小児の採尿方法で示した方法で採尿した結果なのですが、これではやはり正確な検査結果は難しいと思います。
これは、尿検査をするにあたっての「困りごと」に関するエピソードです。検査をするのに採尿できない患者様の、心理状態を示した事例ともいうことができ、患者様への対応の難しさを感じた出来事でもあります。患者様にはけして真似をしていただきたくはありません。このような状況にならないような検査の進め方や雰囲気づくりを、私たちは考えていく必要があると気付いた事例でもありました。採尿の大切さを理解していただくことは、大事な尿検査を正しく受けることに繋がり、結果として、疾患の診断や健康管理に役立つと思います。
記事では、尿検査のための「採尿」について、方法や気を付けたいことなどについて解説しています。

尿検査の入り口である「採尿」について、方法や検査との関係などについて、次の記事で説明しています。
沈渣の上皮細胞、核が大きくて怪しい気がする・・・
尿沈渣検査は、標本を作って顕微鏡で観察するわけですが、教科書通りの細胞ばかりではありません。いろいろな状況を加味して観察することになります。疾患によっては悪性細胞と呼ばれる細胞も出現しますが、この判断もなかなか難しいものがあります。そんな尿沈渣検査をする上で考えていたこと、実践していたことを少しご紹介します。
・・・「こんなことがありました」というより「こんな風に考えていました」という方がよいかもしれませんが。
尿沈渣は、なかなか難しい検査です。というか、私は難しいと思っています。顕微鏡で観察する形態学的検査は、やはりある程度の熟練は必要です。細胞の形状や特徴を覚えていたとしても、実際にルーチン検査の現場で標本を見た時、なかなか教科書通りには判定できないことが少なくありません。
たとえば悪性細胞ですが、細胞の核の大きさや構造、細胞の形状などから判断していきます。しかし、尿沈渣の標本は、特定の細胞を特異的に染めるような染色法を用いているわけではなく、実際には細胞を特定するのが困難な場合も多いのです。しかし、尿沈渣検査を担当していると、あやしい細胞を認めることもあります。そのような時は、形態学的な特徴、例えば核が大きい、N/C比が大きいといった状況を報告して、病理検査室での細胞診検査の依頼をおすすめする、といった対応をすることがありました。尿沈渣検査で確定するのは難しいが、見逃すことはしたくない、といった所見を、さらに専門的な検査に繋げることで、臨床に有用な情報を提供できるようにするのです。実際、この対応で、悪性所見を速やかに報告することができた症例が何度かありました。
尿沈渣は、処理が特に難しく時間がかかる検査というわけはありません。スクリーニング検査として位置づけられる検査です。ですから「確定する」ことにこだわらず、「拾うこと」、「落とさないこと」、を大事にすべきかな、と検査をしていたように思います。もちろんこれは主に悪性細胞についてであって、赤血球や白血球、円柱、結晶など、その他の尿沈渣で判定すべき成分はきちんと検査した上でのお話です。

尿沈渣検査について、検査の概要と主な成分について、また結果の考え方などを次の記事で説明しています。
これは、尿沈渣検査をするにあたって、考えていたこと、心がけていたことをご紹介したものです。状況にもよりますが、「悪性」と判定することは容易いことではありません。もちろん事実は事実なのですが、尿沈渣検査だけで特定することは難しいのです。多くの場合、その結果だけで診断されることはなく、結果をもとにさらに詳しい検査することになりますが、どうすることが患者様にとってよりベストなのかを考えて検査をしていました。確定はできないが、あやしいと感じていることを医師に伝えるためには、医師との良好な関係も大切だと再認識もしました。検査技師がどのように考えながら検査しているかを少しでも知ることは、検査を身近に感じ、理解を深めることに役立つのではないかと思います。
記事では、尿沈渣検査がどのような検査か、尿沈渣の主な成分の説明や、結果の考え方などを解説しています。
「こんなことがありました」を振り返って

各記事の「こんなことがありました」の中から4つ紹介しました。すべて実際にあった事例です。
それぞれ、考えさせられ、新たな学びとなりました。また、コミュニケーションの重要さを再認識することができましたし、医師の考え方を知ることもできました。検体検査の検査結果は多くの場合、数値や、陰性・陽性といった形式で報告しますが、時折それでは伝えきれない情報がある場合もあります。これをどのように医師に伝えるかは、担当の技師の技量に委ねられているところが大きいように思います。

こういったすべての経験の積み重ねが、仕事に真摯に向き合い、自己研鑽を大事にし、医師や患者様とのコミュニケーションを大切にするなど、その後の仕事に生きていると思います。
一般の方にも、検査に興味を持っていただいたり理解していただく上で、きっかけになったり役立つ内容もあると思います。

検査の内容や結果の考え方を知ることは、健康について考えたり疾患に向き合うための助けになるのではないかと思います。検査の内容や検査を担当している技師の考えなどに僅かでもふれることで、少しでも検査を身近なものと認識していただき、健康について考えるきっかけになればと思います。
ぜひ、各記事も読んでいただきたいと思います。

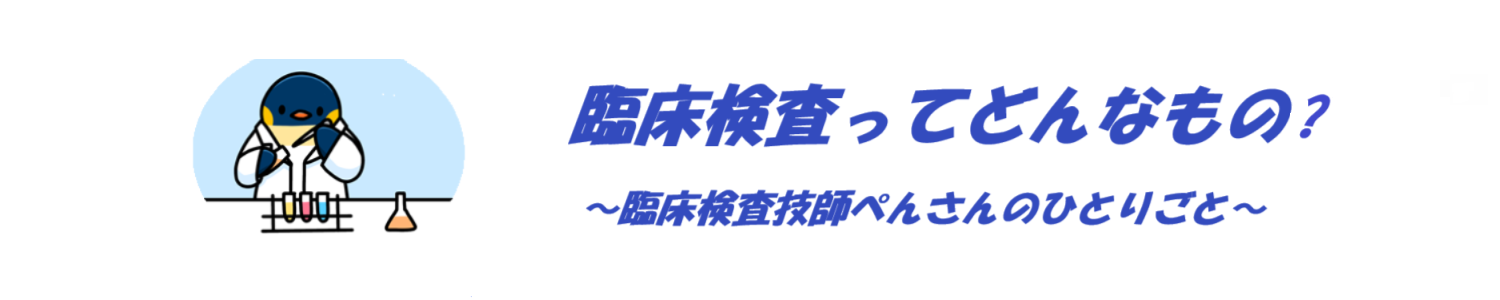



コメント