
「こんなことがありました」を集めてみました。
臨床検査技師として仕事をしている中ではさまざまな出来事があり、そのひとつひとつが学びとなり大切な経験となっています。それらの中から記事の内容に関連したものを、「こんなことがありました」と題して書いています。
これを読んでいただくことで、僅かでも検査についての理解が深まれば良いと思っているのですが、とりあえずあまり難しく考えずに「ちょっと面白そうかも」と興味をもっていただければと思います。そしてそれぞれの記事を読むきっかけになると嬉しいです。
「検体が固まっていたので取り直しますか」と連絡したら・・・
「検体が凝固していたので採り直しをさせてください」と言われた経験があるでしょうか。凝固してはいけない検体が凝固してしまった時、正しい結果を得るためには、再採血が正しい選択肢といえます。しかし、何も考えずに再採血をお願いしているわけではありません。医師や私たち臨床検査技師が様々な検討をした上での選択です。ここでは、再採血とはならなかった経験をひとつご紹介します。
私の経験では次のようなことがありました。
凝固検査の検体が固まっていたので医師に連絡しました。すると、「血が固まりにくいかもとスタッフに言われたので、確認のために採血したのだけど、固まったのなら大丈夫かな・・・。とりあえず今日は中止にして、日を変えて検査します」と言われました。これはこども病院での経験ですが、「凝固機能の確認をしたかったから、参考値でなく正しい検査結果がほしい。でも、現状、固まったのなら緊急性はなさそうだから、今日は中止にして、後日検査しよう」という感じでしょうか。小児だったということも大きいと思いますが、こんな判断もあるのです。
これは検体が凝固していた場合の、医師の判断の一例です。「血が固まったなら凝固検査の緊急性はない」というある意味理にかなった考え方で、ハットさせられたのを覚えています。「凝固してたら即再採血」なのではなく、ケースバイケースで、臨床検査技師だけでなく医師も含めて、考え、検討して決めているのです。そういう事情が垣間見える事例ではないかと思います。患者様にとっては「再採血」になりかねない検体の凝固ですが、その意味などを知ることで、検査に対する理解に役立つのではないかと思います。
記事では血液の凝固と検査について書いています。
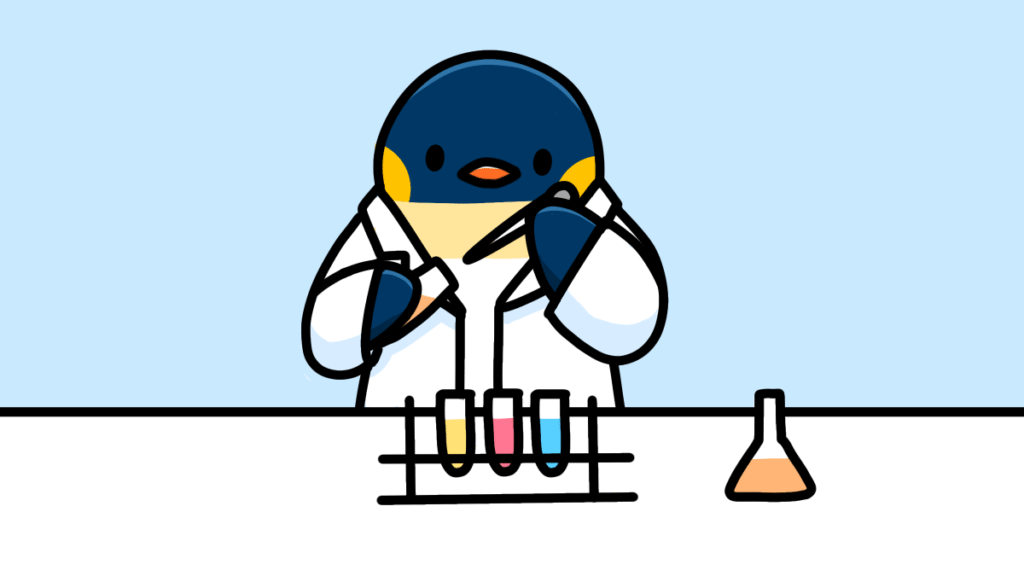
血液検体の「凝固」とはどういうことか、何が問題になるのか、次の記事で解説しています。
「グルコースが1000mg/dl なのですが・・・」
「パニック値」という言葉は一般の方には馴染みがないかもしれませんが、私たち臨床検査技師にとっては、結果を判断する上で非常に重要な、判断を誤ってはいけない値です。パニック値は、その値が正しく検査を行った結果であることの確認と医師への連絡を、迅速、的確に行わなければなりません。パニック値に遭遇した経験をひとつ、判断の難しさなどを交えてご紹介します。
こんな経験があります。
外来ですが他院から搬送されてきた患者様の採血検体を検査していたところ、グルコースが1000㎎/dl という値がでました。この値は施設などに関係なくパニック値です。通常の検査の中では、あまり経験することのない異常値で、「こんな結果あり得ない」という技師もいるかもしれません。
この値を報告するにあたっては、検査過誤でないことを確認する必要があります。また、患者様が点滴をしていた場合、採血時にその点滴の薬剤が混入するとこのような値になることは知られていることなので、そのような事実がないかどうかも確認する必要があります。しかし、本当に患者様の値なのであれば、大至急に処置しなければなりません。
そこで、再検査をはじめつつ、提出医に連絡をしました。「今再検をしているところで、第一報なのですが」と前置きをした上で、「グルコースが1000㎎/dlなのですが、先生、この患者様点滴していますか」と問い合わせました。電話の向こうの医師は、一瞬固まった感じでしたが「いや、点滴はまだしていない」と即答でした。そうすると、検査過誤でなければとんでもない値です。医師は続けて「とりあえずもう一回採血するよ」と。再検査の結果は変わらず、また再採血も同様の結果で、すぐに処置がされました。これは私が実際に経験した症例です。
「点滴の混入」というのは、あってはならないインシデントなのですが、実際の医療の現場ではまま起きています。たとえば採血した人が検査をしていれば、結果を見た時にすぐに思い当たるかもしれませんが、検査科で検体を受け取って検査をしている場合、採血時のインシデントは想像でしかありません。また、点滴が混入した検体の検査を経験して、その影響について学習してしまった技師は、次に同様な結果を見た時に「これも点滴だろう」と勝手に思い込んでしまい、対応が後手に回る場合もあります。
真の「パニック値」は、分析前誤差や検査過誤と区別されなければなりません。しかし、測定値だけを見た時、その区別が難しいことが多いのも事実です。したがって、患者様の生命を守るためには、他の医療スタッフとのコミュニケーションも重要になります。臨床検査技師は、検査過誤を起こさない努力とともに、思い込みも持たず、真摯に検査結果と向き合わなければなりません。「こんな結果あり得ない」と思うのではなく、なぜこの結果になったのかを考える姿勢も必要でしょう。

「パニック値」とはどういうものか、結果の判定にどのように重要なのかを次の記事で説明しています。
これは私たち臨床検査技師を悩ませるパニック値に関するエピソードです。検査結果の確認と患者様の命を守るための緊急性とのバランスの難しさと、担当医との良好な関係性がスムーズなやり取りに大切だということを、再認識した出来事でした。「パニック値」はあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、この事例から、少しでも知っていただければと思います。検査結果を報告する上で、こんな状況もあることを知っていただくことは、検査に対する理解を深めることに役立つのではないかと思います。
記事では、結果の判定の上で重要な「パニック値」について、その概要と難しさや問題点などについて説明してます。
「救急外来の患者様の生化学の検体、溶血していますが取り直しますか?」
「溶血したので採り直し」という経験をされた方もいらっしゃると思います。「溶血」は検査結果に影響を与えることが知られていて、対応としては「再採血」というのが正しい選択肢といえます。でも、「再採血のお願い」に至るまでには、私たち臨床検査技師はそれ相応の検討をしています。そこにはもちろん医師の判断もあります。溶血に対する判断の一例を経験をもとにご紹介します。
溶血を認めた場合、検査結果に影響があるので一般的には再採血が勧められます。しかしすべての項目が影響を受けるわけではありません。言い換えれば、項目によっては、再採血をせずにそのまま報告をしても臨床的に大きな問題にはならない場合もあります。
こんな経験があります。私がある病院で当直をしていた時のことです。救急外来からの採血検体を遠心分離したところ溶血していました。どれくらいの溶血だったかデータとして残っていないのですが、医師に連絡しようと思ったので、結構強い溶血だったと思います。採血をしたのは救急外来の看護師でしたので、その看護師に直接再採血を依頼するのも一つでしたが、夜間の救急外来でのこと、それほど忙しい日ではなかったと記憶していますが、再採血で時間をとるのは具合が悪くて来院した患者様にとっても好ましいことではありません。そこで私は担当医師に連絡をしました。「先ほどの患者様の生化学の検体ですが、結構溶血しているのですが、再採血しますか」と。すると医師は「CRP(C反応性蛋白)は溶血の影響ないよね。今日知りたいのはCRPだからそのままで測定していいよ」と即答でした。CRP以外の項目も依頼されていましたがそのまま測定することとし、「溶血参考値」のコメントを付記して報告しました。このケースは医師も検査について熟知していて、スムーズに話ができました。もちろんいつでもこのような状況になるわけではありませんが、溶血の影響を十分理解していれば、このような考え方もできるといえます。
これは、生化学検査の検体の溶血に対して「再採血はしない」という医師の明確な判断があった時のエピソードです。溶血の影響について明確な知識があってこそ、医師との相談も円滑に進むのだと再認識しました。医師の考え方やその検査の目的にもよると思いますが、「溶血したら必ず再採血」ということではなく、その都度考えて検討しています。ここから、そんな事情を少しご理解いただけると良いと思います。患者様にとっては「再採血」につながりかねない「溶血」について知っていただくことは、検査に対する理解を深めることにも役立つと思います。
記事では、検体がなぜ溶血するのか、どのような影響があるのか、また検査技師として注意したいこと、などを書いています。
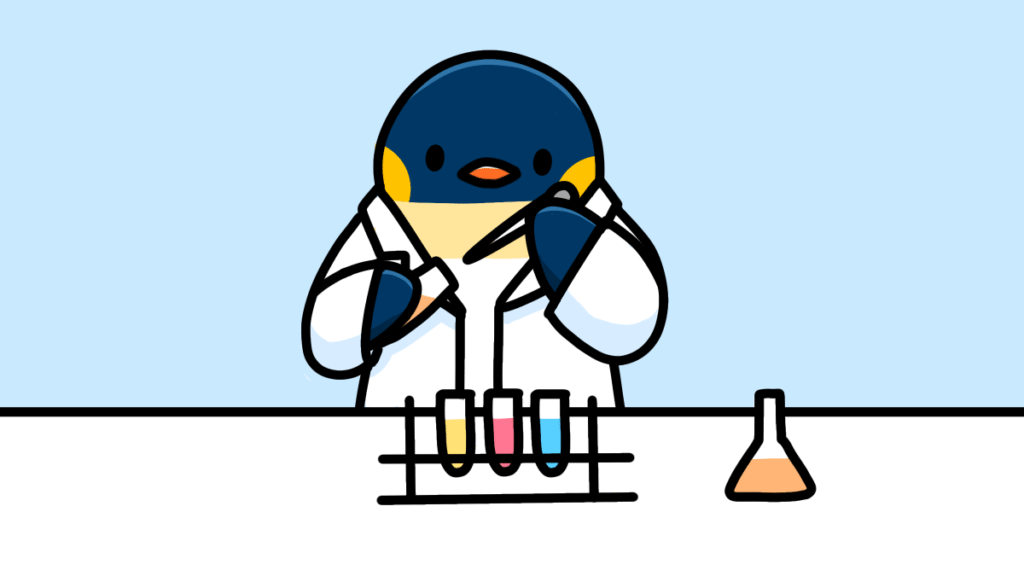
「溶血」とはどういうことか、何が問題となるのか、次の記事で解説しています。
「大変!この検体かなりの黄疸だ。肝機能が悪いかも・・・」と思ったら
私たち臨床検査技師は、検体の見た目から結果を想像できる時があります。例えば黄疸は、肝機能障害の存在を想像させます。しかし、黄疸は肝機能障害以外の状態でも起こります、したがって、当然のことながら、検査をする上で潜入観は禁物です。この戒めを込めてひとつの経験をご紹介します。
黄疸(黄色度)に関して、少し苦い?経験があります。かなり以前のことですが、ある病院で一人当直をしていた時のことです。救急外来から検体を受け取りました。血算、凝固、生化学だったように思います。検査の効率を考えて、まず私は生化学検体の遠心分離をしつつ、凝固検体の遠心分離と血算の検体の攪拌をはじめました。頭の中の段取りでは生化学の検体を測定機に架設してから血算と凝固検査をしようと思い、遠心機から生化学の検体を取り出しました。すると血清はかなりの黄疸。咄嗟に「これは肝機能がまずいかも」と思い、血清に余裕があったので、5倍だったか10倍だったかの希釈をした検体と元検体を一緒に装置に架設しました。そのあと血算の結果を見ると、かなりの貧血。この時点でピンとくれば良かったと思うのですが、当時の私はピンとこず・・・。そうこうするうち生化学の結果をみると、肝機能はほぼ正常。そうです。この患者様は溶血性疾患だったのでしょう。この後も血液型の検査での苦労もあったのですが、患者様は確定診断はされないまま、当直医の判断でより大きな病院へと搬送されました。
「黄疸が強い=肝機能障害あり」の思い込みで、バタバタと実際には不要の作業を行った事例でした。

血清検体の「見た目」である「血清情報」についての詳細は次の記事で説明しています。
これは、「検体の見かけに惑わされないように」という注意を込めたエピソードです。どんな仕事でも同じだと思いますが「思い込み」は良い結果を生まないのだと実感した出来事でした。もちろん、先入観に惑わされない人もいます。でも、「思い込み」がインシデントに繋がった例もあることは事実だと思います。医療従事者に限ったことではなく、ちょっと考えてみていただきたいと思います。また、血清情報について知ることは、検査結果を見る上でも役立つと思います。
記事では、検体の「見た目」ともいえる血清情報について、その概要と意味すること、注意事項などを書いています。
「こんなことがありました」を振り返って

各記事の「こんなことがありました」の中から4つ紹介しました。すべて実際にあった事例です。
それぞれ、考えさせられ、新たな学びとなりました。検査結果の影響する因子をきちんと理解していなければ、医師や患者様ににきちんと説明することはできません。また、コミュニケーションの重要さを再認識することができましたし、医師の考え方を知ることもできました。
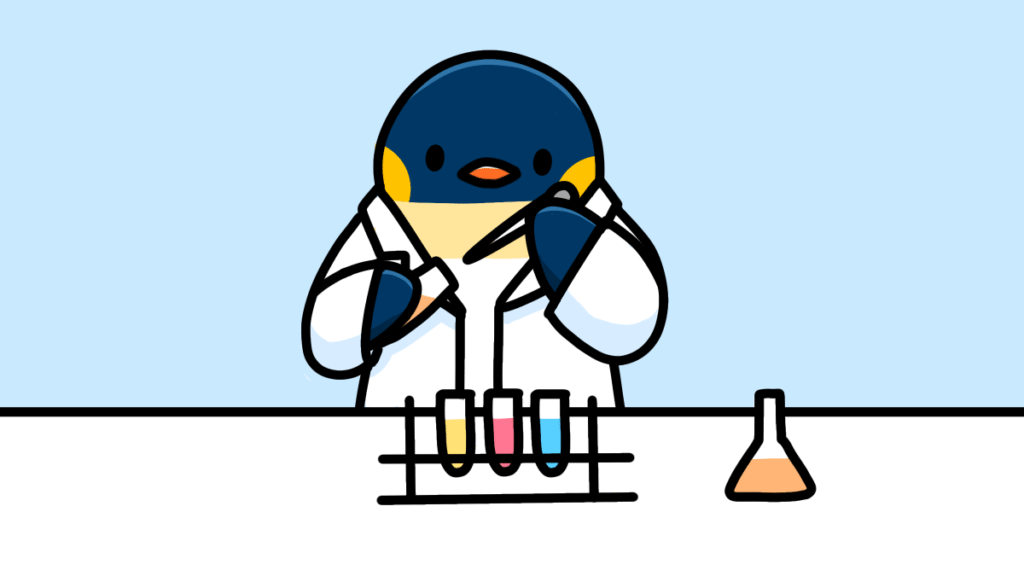
こういったすべての経験の積み重ねが、仕事に真摯に向き合い、自己研鑽を大事にし、医師や患者様とのコミュニケーションを大切にするなど、その後の仕事に生きていると思います。
一般の方にも、検査に興味を持っていただいたり理解していただく上で、きっかけになったり役立つ内容もあると思います。

検査の内容や結果の考え方を知ることは、健康について考えたり疾患に向き合うための助けになるのではないかと思います。検査の内容や検査を担当している技師の考えなどに僅かでもふれることで、少しでも検査を身近なものと認識していただき、健康について考えるきっかけになればと思います。
ぜひ、各記事も読んでいただきたいと思います。

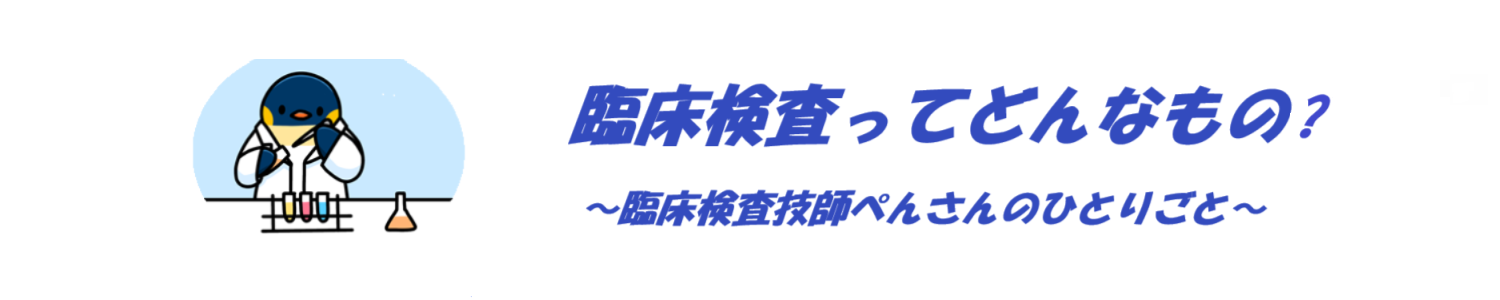




コメント