臨床検査技師になるには

臨床検査技師ってどうやってなるのかな
臨床検査技師は国家資格です。したがって、厚生労働大臣によって定められた養成課程を修めた後、臨床検査技師国家試験に合格し、免許の申請をして、臨床検査技師免許を得ることになります。
臨床検査技師はどのような勉強をして免許を取得しているのか、説明したいと思います。

国家試験受験資格を得るためには
臨床検査技師の国家国家試験の受験資格を得るためには、高校卒業後、臨床検査技師の養成課程がある学校に入学し、必要な過程を修了しなければなりません。

臨床検査技師養成課程のある学校は、大学、短期大学、専門学校などがあり、全国でおよそ100校程度あります。大学は4年制、短期大学、専門学校は3年制です。また、専門学校には2部(夜間部)があるところもあります。

対応する学部・学科は、保健科学部、医学部、歯学部、臨床検査科、医療検査学科、臨床検査技師科、保健学科、健康医療科、など各学校ごとに様々です。
どのようなことを学ぶのか
臨床検査技師養成課程のカリキュラムは、厚生労働省の規則によって定められています。主な内容は、基礎教育科目、専門基礎科目、専門科目、臨地実習などです。

これらのカリキュラムは2022年入学者から適用されているものです。
臨床検査項目の増加、臨床検査機器の高度化、また、チーム医療の推進など、臨床検査技師に求められる役割や知識などの変化に対応するため、厚生労働省主導のもと検討・議論がなされました。
そして、それ以前の学習内容が改正され、新カリキュラムの導入に至ったものです。

どこで学ぶのか
臨床検査技師になるためには、国家試験受験資格を得るため、定められた教育課程を修めなければなりません。そのためには学校に行くことになりますが、これには、大学、短期大学、専門学校などいくつか種類があります。

大学、短期大学とも、国公立と私立があり、学費(入学金、授業料、設備費、など)も様々です。短期大学と専門学校は3年制です。専門学校は私立で学費もまちまちです。

国公立か私立か
どこで学ぶかを考えた時、まず国公立か私立か、が最初の選択肢となるでしょう。
経済的な問題は、時として大きい理由となると思います。
単純に学費だけを考えれば国公立が圧倒的に有利となるでしょう。ただ、学校数は私立の方が多いですし、偏差値など学力的なレベルの問題もあると思います。
したがって、志望校選択において、どのような理由が大きな比重を占めるのかを見極めることがまず重要となるでしょう。

大学か短大・専門学校か
次の選択肢は3年制か4年制か、だと思います。

短期大学と専門学校は3年制です。
短期大学は単科であることも少なくなく、その学校生活の中で、専門教育以外の経験も積みたいと考える場合、少し物足りないと感じるかもしれません。
また、3年間ですべてのカリキュラムを学ぶというのは、時間的にはかなり過密とも考えられます。
そういった意味では、4年間学ぶ大学の方が、より幅広く余裕を持って学ぶことができるといえるかもしれません。
各学校ごとの特色もありますので、興味のあるところは見学をしたり、卒業生に話を聞くなどしてみるのも良いかと思います。
3年でも4年でも、大切な時間です。ご家庭の事情も考慮して上で、じっくり考えて選んでいただきたいと思います。
こんなことがありました
短大卒と大学卒の違いに関するひとつの意見です。
30年以上も前の話です。「短大卒はすぐ使える。大学卒はすぐには使えないが、考える力があるので将来的には有望かも。」という評価を聞いたことがあります。
全体の評価がこのようなものだったかはわかりません。あくまでもその方の私見だと思います。
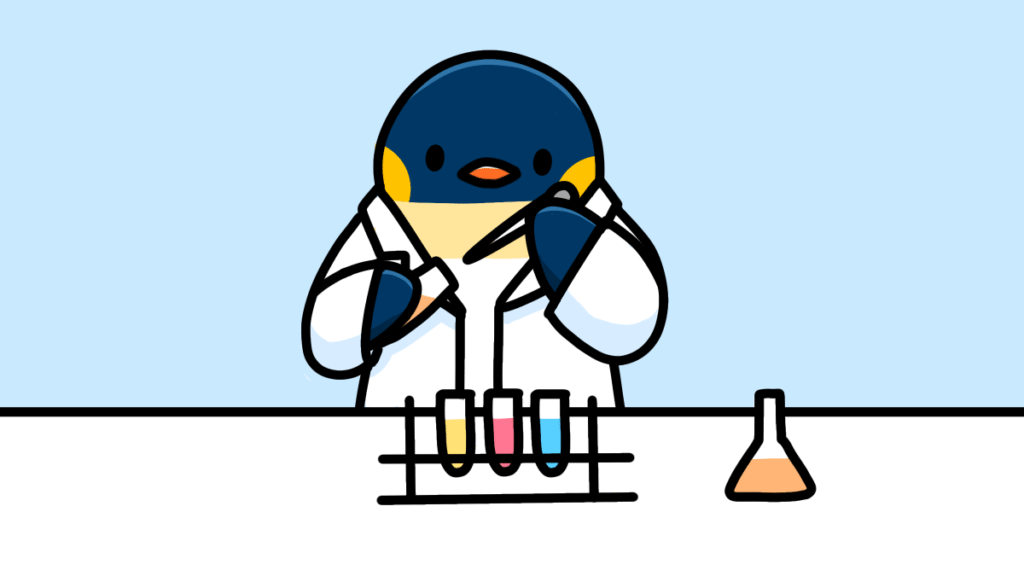
ただ、当時の短大は、現場で検査ができる技師の育成を目指して、少数の学生の教育をしていました。実習時間なども多く、人任せではなく必ず自分が関わらなければならない状況でした。それで、新卒でも多少は役に立ったのかもしれません。
でも、個人差が大きいかったようにも思います。
大学卒でももちろん優秀な方は多くいたと思います。
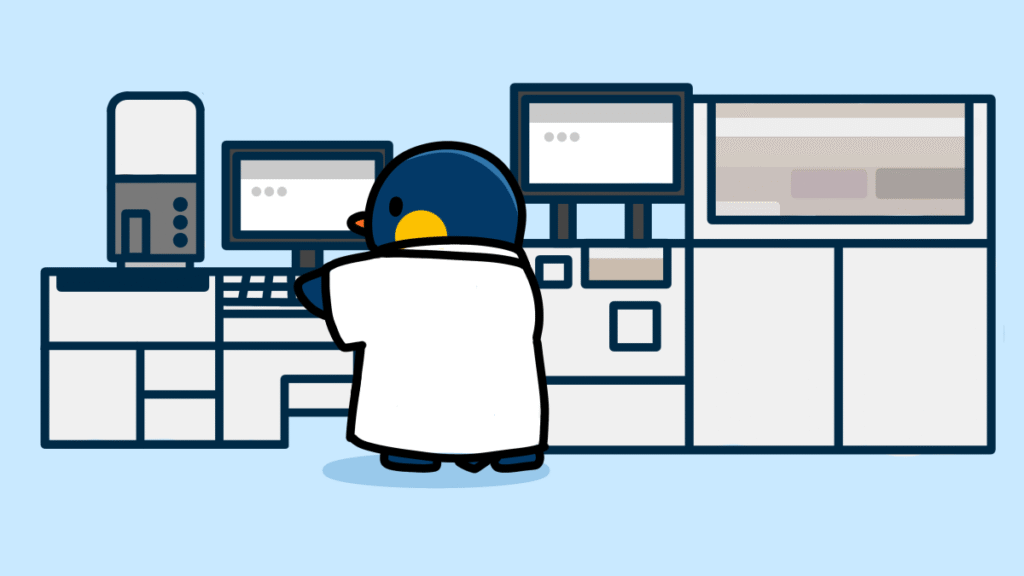
当時のカリキュラムは現在のカリキュラムとはまったく異なっており、それぞれの特色があったので、ある意味、その差を言い当てていたのかと思います。現在は状況も変わっていますので、あくまでも過去のエピソードとご理解いただければ・・・。
どんな人が向いているか
臨床検査技師にはどんな人が向いているか・・・これはなかなか難しい問題だと思います。
いろいろな考え方があると思いますので、かなり個人的な見解であることをお断りさせていただいて、少し考えてみます。

文系が得意よりは理系が得意、コンピューターや実験などが苦にならない、などが基本的には必要な資質かもしれません。

ただ、絶対に必要かといわれると、必ずしもそうではないように思います。養成課程のある学校に入学できる学力があれば、とりあえず得意教科が文系でも理系でも、それほど大きな問題はないと思います。

コンピューター関係は、現在ではどのような職種でもある程度は必要だと思います。臨床検査技師の仕事では、もちろんプログラミングをするわけではありませんし、絶対に長けていなければならないことはないと思います。しかし、検査に関わるシステムや機器の取り扱い、検査データの処理等、コンピューターが関わることは多く、全く疎いと少し大変かなと思います。

実験に関しては、臨床検査は理科の実験とはもちろん異なりますが、私たちは「技師」なので、基本的な手技は必要だと思います。実際の仕事では、学校の授業とは全く異なる技術や作業が必要とされたりするのですが、養成課程の中で学ぶ技術は、基本的な手技として重要だと思います。
これらのことは努力で補うことが可能かとも思います。ですから、例えば「不器用」を理由に最初からあきらめる必要はないように思います。
チーム医療の一員として
「どんな人が向いているか」を考える上で、別の側面として「チーム医療」について少し説明しましょう。

チーム医療とは
臨床検査技師はコメディカルに含まれます。
コメディカルとは医師、歯科医師以外の医療従事者で、医師と協力して医療に携わる職種の総称です。これには、臨床検査技師のほか、看護師、助産師、薬剤師、理学療法士、診療放射線技師、臨床工学技士、その他、凡そ30種類の職種が含まれます。

患者様に質の高い医療を提供するためには、「チーム医療」の体制が不可欠となっています。
医師とコメディカルの各専門職が対等に連携することにより、患者様中心の質の高い医療が実現しようとするのが「チーム医療」です。
そのため各専門職は、それぞれの専門性を高めるとともに、他職種との円滑な連携のため、他の職種をリスペクトし柔軟な協調性を持つことが必要といえます。
臨床検査技師も例外ではありません。

臨床検査技師にとって大切なこと
臨床検査技師や臨床検査に対して、一般の方がどのようなイメージを持っていらっしゃるのかわかりませんが、実際のところ地味な仕事です。

さまざまな検査によって臨床に有用な情報を提供する仕事ですから、高い専門的知識や技術が要求されます。
そして、チーム医療を担う一職種ですが、医師の指示の下検査を行う技術屋です。この点の理解は重要かなと思います。
検査に関するプロフェッショナルとしてのプライドを持つことは必要ですが、医療、診療、治療を支える仕事だという意識は持っていた方が良いかと思います。
地道に仕事をこなすことができる、高い知識や技術を習得するための自己研鑽に努めることができる、協調性がある、このようなことが、意外と大切ではないかと思います。
そしてやはり、人の命に係わる仕事をしているという自覚を持つこと、これが重要でしょう。
「どんな人が向いているか」という問いに対する答えにはなっていないかもしれませんが、少しでも参考になればと思います。
臨床検査技師への道

臨床検査技師になるためには、臨床検査技師の養成課程のある学校に入学し、定められた課程を修め、国家試験に合格しなければなりません。
そこには向き不向きが多少はあると思いますが、例えば高校生の段階で、それを見極めるのは難しいようにも思います。
「なりたい」という気持ちと努力で、ある程度は補うことができるようにも思います。こういうと精神論のように思われ、今どきの考え方ではないと言われるでしょうか。
ただ、人の命に係わる仕事だという意識は強く持っていただきたいと思います。

「人は誰でも間違えることがある」と言います。
確かにそうだと思います。
でも、医療従事者はやはり、「間違えてはいけない仕事」だという意識を持って欲しいと思います。
どれだけ注意していても間違いは起きてしまいます。
しかし、最初から、「間違えても仕方がない」とは考えていただきたくはないと思います。
臨床検査技師になりたいと思っている方、またそのご家族に、僅かでも参考にしていただけると嬉しいです。

臨床検査技師についてこちらの記事もぜひ読んでください
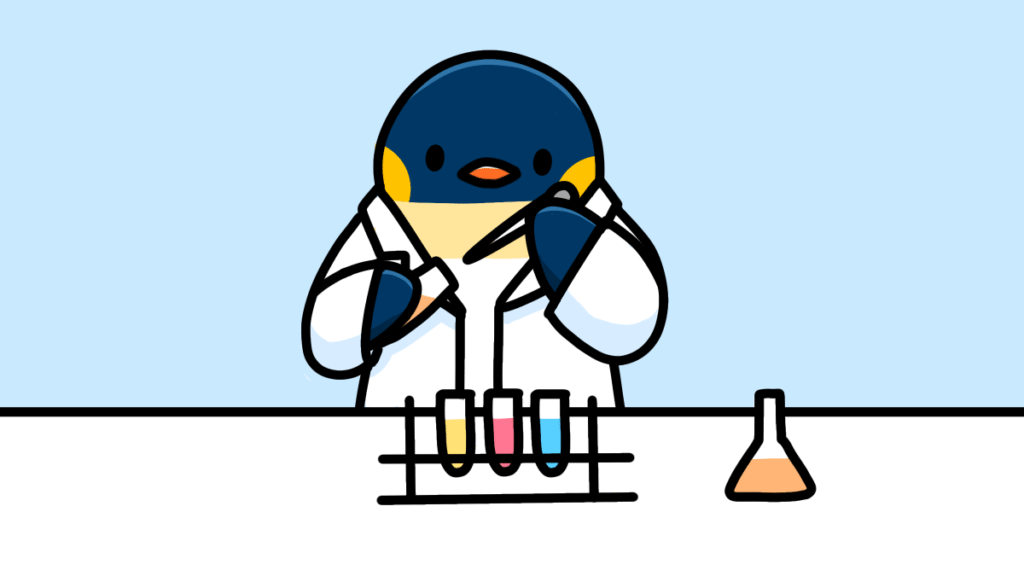
臨床検査技師教育を担う団体と国家試験に関するサイトです


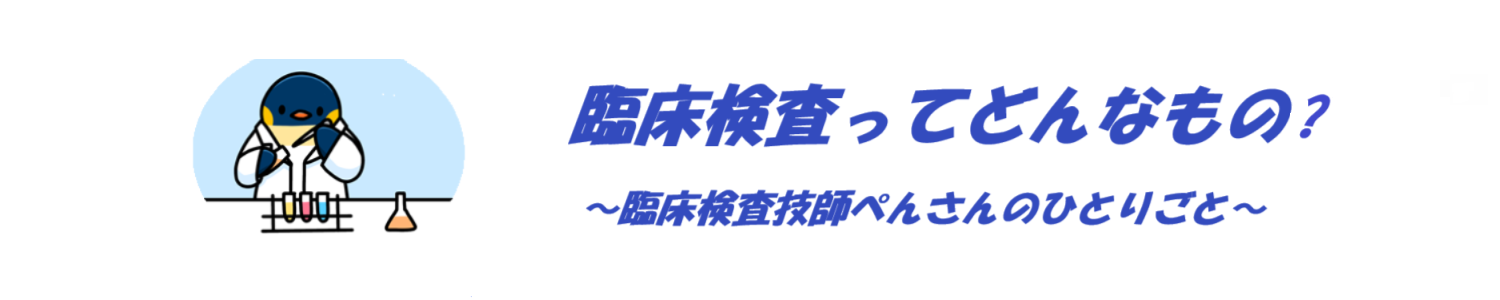



コメント