基準範囲

検査結果を見たら「基準範囲」ってあるけど、これは何?
自分の検査結果と数値が違うのがあるけど大丈夫かな・・・
健康診断や病院の検査結果を見ると、結果の隣に「基準値」や「基準範囲」という欄があるのをご覧になったことがあるのではないでしょうか。
「検査結果の考え方」の最初として、この「基準範囲」について考えてみたいと思います。

「基準範囲」あるいは「基準値」とは「正常な人の95%が当てはまる値」と定義されています。以前は「正常値」という言葉が使われていましたが、現在ではこの言葉は必ずしも正しくないという見解で使用されなくなっています。
健康な人を検査してその結果を統計学的に処理したとき、上限と下限の2.5%ずつを除外した残りの95%の人の値を「基準範囲」としています。言い換えると「健康」と思われる人の中で5%の方は「基準範囲」から外れることになります。ではこの5%に入る方たちが「異常」なのかといえばそういうことではありません。このことが「正常値」という言葉を使わなくなった理由ともいえます。
基準範囲の設定
基準範囲の定義は決まっていますが、各項目の基準範囲の値そのものは、使用する機器や試薬によって異なります。したがって、基準範囲をもとに検査結果を評価する時には、当然その施設の基準範囲を用いなければなりません。
基準範囲は各施設で設定することが望ましいとされていました。
しかし、病院で基準範囲を求めるというのはあまり現実的ではありません。そもそも病院で「健康な人」という集団を確保するのは難しいのです。職員などの協力が得られれば不可能ではありませんが、採血して測定し、統計学的処理をするのは手間も時間もかかります。
また、項目によっては値に男女差があるものもあり、その場合は当然男女別に提示する必要があり、自施設で求めるにはさらにハードルが上がるといえます。
もちろん大学病院や規模の大きい施設では、自施設の基準値を提示しているところもあります。
自施設で基準範囲を算出することが難しい多くの施設では、「メーカー推奨値」と呼ばれる値を使っています。つまり使用している機器・試薬メーカーが提示する値を基準範囲として設定しています。この場合、試薬等を変更した時には基準範囲も見直さなければなりません。
また、項目や試薬によっては「メーカー推奨値」が提示されていない場合もあります。その場合は「文献値」として、さまざまな文献に記載された値を、出典を明示した上で使用することもあります。
同じ項目でも使用する試薬や測定機器によって、測定値が異なることがあります。したがって、基準範囲も試薬や機器によって異なることになります。測定結果を判断するときには、その施設の基準範囲を用いればもちろん大きな問題はないのですが、試薬等が変更されるたびに基準範囲を見直すのは煩わしさもあります。
「どこで測定しても同じ結果」を目指し、測定法等の標準化が進む中で、個々の医療機関における基準範囲の代用として、「共用基準範囲」が2019年に関連学会等によって設定され、使用が推奨されています。これは、測定法の標準化がある程度達成された一般的な臨床検査項目の中で、40項目について設定されたもので、日本医師会なども賛同しています。
これを採用した施設は、検査値の評価基準も統一されることになります。現在では全国で多数の施設が「共用基準範囲」を採用していると思います。
成人と小児
ところで、基準値は多くの場合、成人を対象として設定されています。「共用基準範囲」も同様です。したがって小児の場合は事情が変わってきます。
小児はの測定値は、多くの項目で月齢・年齢によって変化し、成人とは異なる値を示します。小児の検査だからといって、目安となる基準範囲が必要ないというわけでは、もちろんありません。しかし、小児の基準範囲の設定は多くのこども病院で課題となっていて、現状では文献値を使用している施設が多いと思います。

検査結果を正しく評価するために
基準範囲は、検査結果を評価するために設定されています。しかし、あくまでも目安であるともいえます。
そもそも健康な人の95%の値なのであって、健康であっても基準値範囲から外れている人もいるわけです。しかしだからといって、基準範囲から外れている項目があった時、それを放置して良いというわけではありません。
基準値と自身の検査結果を照らし合わせて一喜一憂するのではなく、正しく医師に判断を仰ぐことが必要といえます。


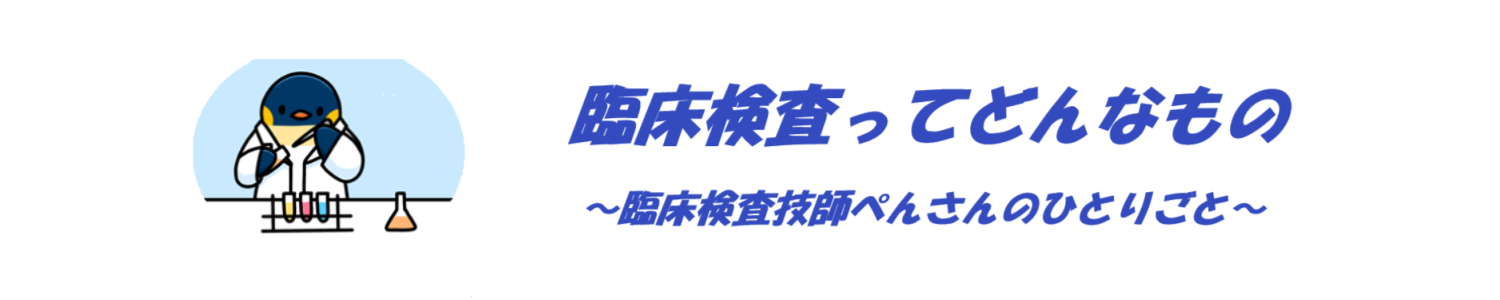

コメント