再採血

なんだかもう一回採りたいって言われたんだけど・・・
再採血の経験はありますか。
「ただでさえ採血は嫌いなのに、もう一回って何?」と思われる方もいらっしゃると思います。
今回はこの「再採血」について考えてみましょう。

なぜ再採血になるのか
再採血とは
「再採血」とは、その字の通り、もう一度採血をすること、言い換えれば、「採り直し」です。

その場で言われる時は、採血量が明らかに不足しているなど、そのまま検査に提出するのが難しい明白な理由がある場合といえます。
一方、検査結果を待っている時、つまり少し時間が経ってから呼ばれる時は、検査を始める段階で不具合が判明した場合といえます。
その場でもう一回と言われるとき
その場で「もう一回」と言われる場合は、たとえば、採血中に血液の流出が止まってしまった時などです。

血管に針がきちんと入って血液が採血容器に流出しはじめても、急に出なくなる場合があります。
採血者は針の角度や深さを調整するなどの策を試みますが、それでも回復しない場合は採血をいったん終わりにして針を抜くことになります。
この時、採血量が規定量ではないが何とかなりそうで、ほかに明らかな問題がない場合は、そのまま終了となります。

採血担当者が判断可能な明らかな問題がある場合は、その場で「もう一回」となります。
少し時間が経ってから呼び出されるとき
採血後の検体は検査科に運ばれ、まず、採血管が正しいか、検体量は十分か、凝固の有無、などの確認が行われます。
採血管
「採血管」は採血の時、血液を入れる容器のことです。
採血管は、大きさや、中に入っている薬剤の違いなどで、何種類もあります。
検査の内容によって、使用する採血管が決まっています。
これが間違っていると正しい検査はできません。

つまり採血管の間違いは、再採血の理由となります。
検体量
「検体量」、つまり採血して採血管に入れる血液の量は検査によって決まっています。
たとえば赤血球や白血球の数を算定する血液検査では、多くの場合2ml~3ml程度の血液を必要とします。腎機能や肝機能などを調べる生化学検査では、3ml~5ml程度が必要量とされます。
実は検体量に関しては、話が少し複雑になります。
必要量として公表されている量は、再検査や追加検査等なども考慮して設定されています。
純粋に1回の検査に必要な量は、実施する検査の内容や検査法、使用する機器等によって異なります。
必要量の設定は、「1回の検査に必要な量+α」であり、各病院、各検査室によって変わってきます。

また、血清量は、通常、全血の量のおよそ半分程度ですが、これは個人差があります。多血症などの場合はもっと少ないですし、貧血の場合はもっと多くなります。
採血での必要量は、血清の比率が一般的な場合を想定して設定しています。
したがって採血量としては十分採ったつもりでも、想定よりも少ない血清しか採れず、検査には量不足となる場合もあるわけです。
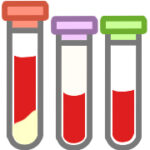
採血量が規定の量に満たない場合、諸々の事情を考慮した上で、再採血を要求しなければならない量不足かどうかの判断をします。極論をいえば、最低1回の検査に足りれば「良し」としている場合もあると思います。
血液が凝固しているか
一般的に、血液は時間が経つと凝固します。これは日常で経験することだと思います。
検査するために採血した血液も、何もしなければ固まってしまいます。
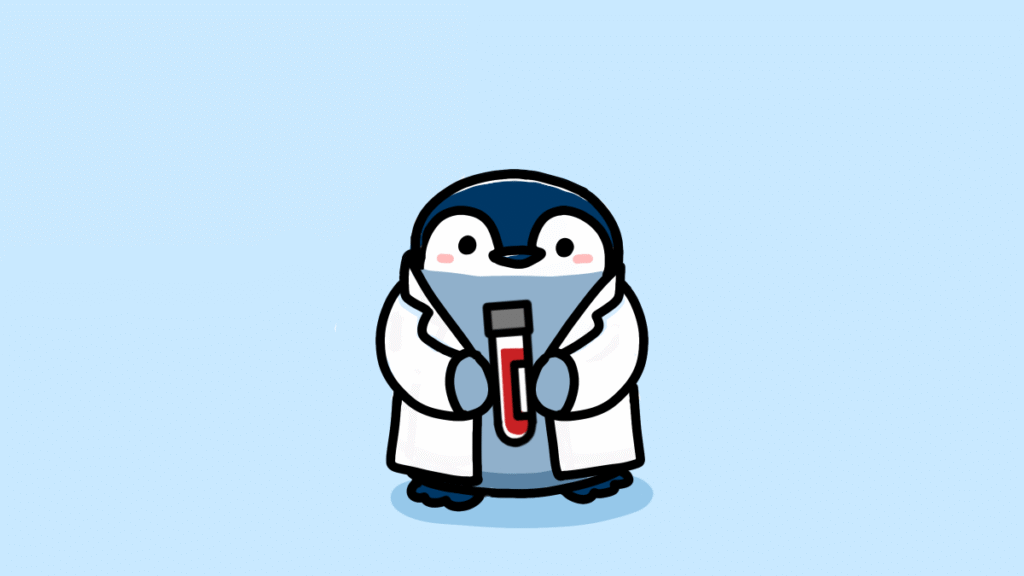
検査の内容によって、凝固してはいけないものと凝固してほしいものとがあります。凝固してはいけない検査の場合は、抗凝固剤といって固まらないようにする薬剤が入った採血管を使用します。
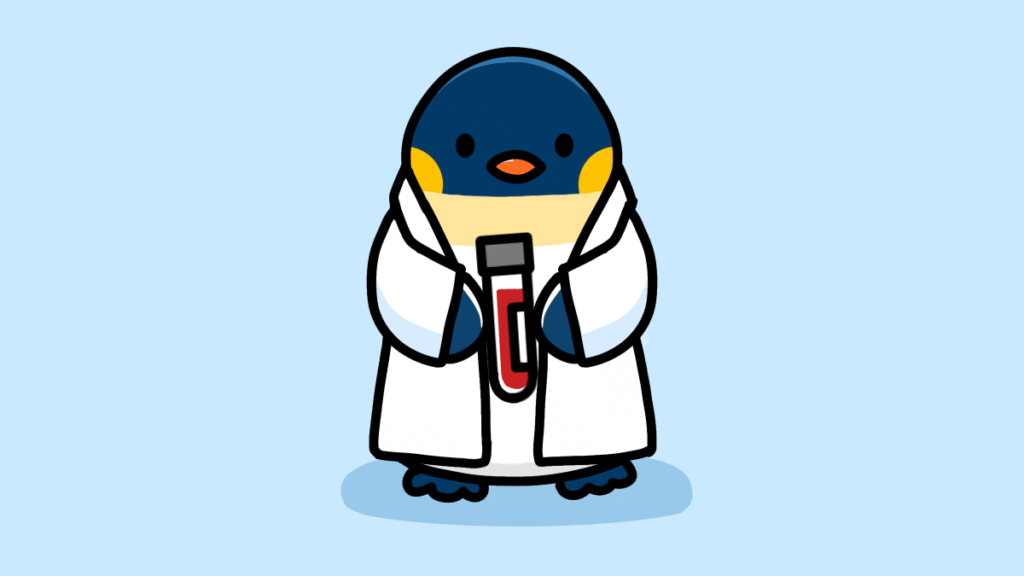
たとえば赤血球や白血球の数を算定する血液検査では、凝固は不可、つまり固まっていてはいけません。
一方、肝機能や腎機能などを調べる生化学検査では、血液が凝固した後遠心機で遠心分離をして得られる「血清」で検査するため、凝固していることは問題ありません。
検体に凝固が認められた場合、それが血液検査なら「検体不適」、生化学検査なら「問題なし」ということになります。他の検査でも同様のことがあり、凝固の有無は重要なチェックポイントとなります。
溶血があるか
「溶血」とは赤血球が破壊された状態をいいます。
血液を遠心分離して得られる「血清」は、通常は黄色味を帯びた透明な液体です。
これが溶血すると赤血球の赤色となります。
生化学検査では、色調が赤いことで、検査に影響がある場合があります。また、赤血球が壊れることで、本来の血清の成分の量が変わってしまう場合があります。
いずれにしても、検査結果に影響がでることになります。

溶血しているかどうかは、採血後、遠心分離をしないとわかりません。
生化学検査の検体の場合は、この溶血も再採血の要因となるのです。
再採血の判断
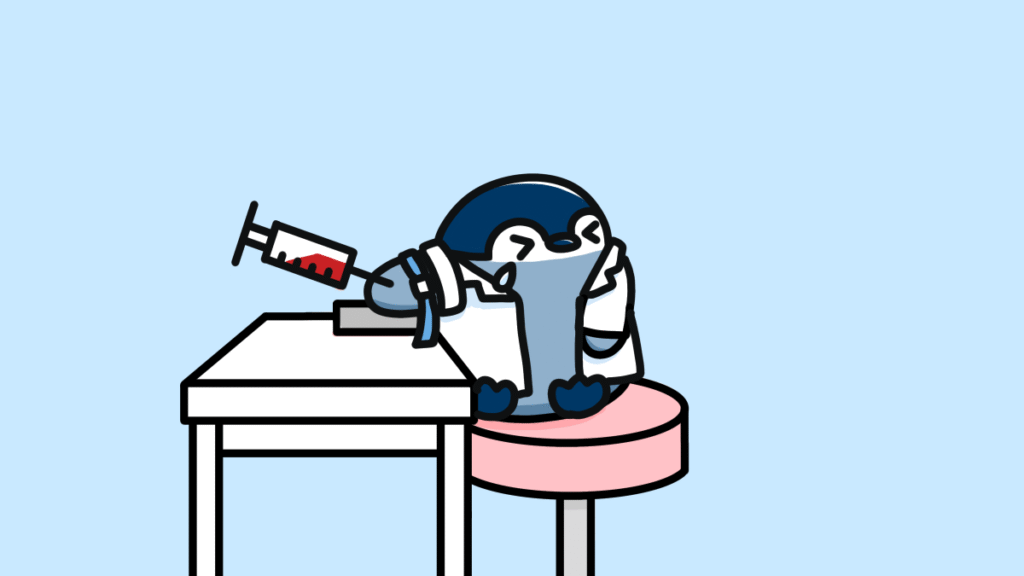
検体が凝固しているか、検体量や血清量が検査に十分足りるか、溶血があるか、などは検査室で判断することになります。
場合によっては、検査の提出医師に相談して再採血をするか決めることもあります。
このような場合、「採血後少し時間が経ってから呼び出される」ということが起こることになるのです。
再採血には理由がある
その場で「もう一回」と言われても、後から呼び出されても、再採血は嫌なものです。できればそのような目には合いたくないものです。
採血する側も同様で、再採血はできれば避けたいものです。

でも、それ相応の理由があっての「再採血のお願い」です。
正しい結果を得るために必要なことと理解していただけると良いと思います。

もちろん、疑問や不安、納得がいかないことがある場合は、担当の医師に相談していただくことも大切なことだと思います。

再採血になる理由についてはこちらの記事で
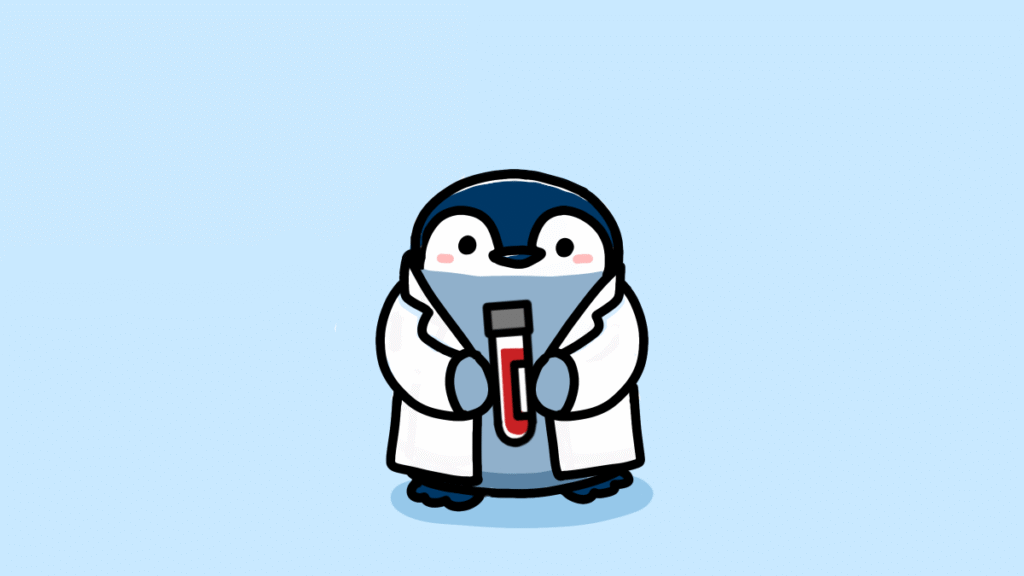

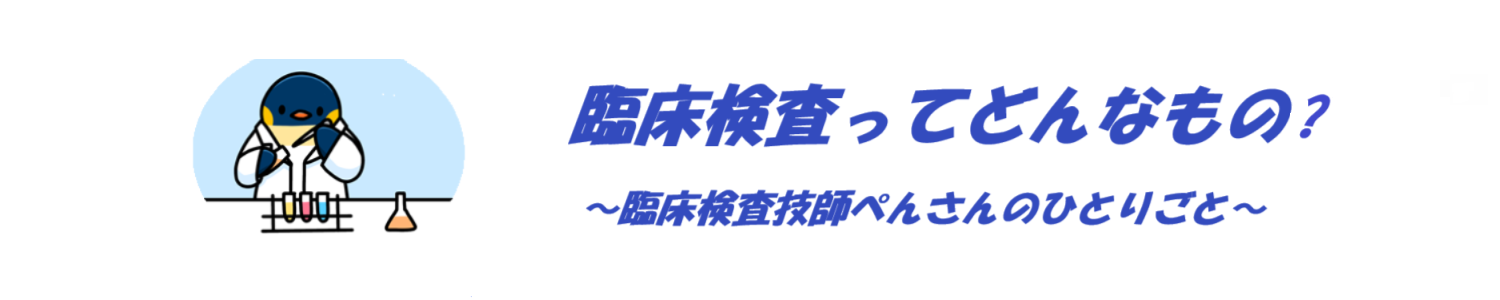


コメント