臨床検査の種類

臨床検査ってどんな種類があるのかな
臨床検査技師の仕事は多岐にわたりますが、大きく2つに分けることができます。
主として血液や尿、便、喀痰、また脳脊髄液や胸水、腹水など、患者さんから採取された検体を検査する「検体検査」と、心電図や脳波、肺機能検査や超音波など、患者さん自身を対象として検査をする「生理検査」です。

検体検査とは
検体検査の対象となる検体とは、人体から排泄または採取されたもので、 血液、尿、便、脳脊髄液、胃液、十二指腸液、胸水、腹水、喀痰、細胞など多くの種類があります。
そして、この中で何を対象としているか、またはどのような検査をするか、などによって、血液検査、生化学・免疫検査、一般検査、細菌検査、輸血検査、病理検査など、いくつかの分野に分けられています。
検体検査は扱う検体の種類によってこのようにいくつかの分野に分かれますが、多くの病院ではこの中で、血液検査、生化学・免疫検査、一般検査を「検体検査」としています。
そしてそれぞれを独立した検査室として「血液検査室」「生化学・免疫検査室」「一般検査室」などとしている病院と、3分野をまとめて「検体検査室」としている病院があります。
正確な検査結果のために
「検体検査」、「生理検査」はどちらも、現在の診療体制の中で、診断、治療に欠かせない情報を提供しています。
病院を受診した時、診察前に採血や採尿をして、その検査結果を待って診察となることがあると思います。夜間でも休日でも同様でしょう。この時の検査は臨床検査の中の「検体検査」です。
「検体検査」は多くの場合24時間365日体制で、正確かつ迅速な結果が求められます。そこには高い専門知識や技術が必要となります。そのため担当している臨床検査技師は、日々研鑽を積み頑張っています。
検体検査は一部形態学検査もありますが、多くは専用測定機器で測定します。この機器分析は、「誰が担当しても同じ」と捉えられがちですが、実はそうではありません。専門の知識や技術がなくては、正確で迅速な結果を報告することはできません。測定機器の操作そのものは「簡便」とされるものが多くなっていますが、正確な値を出すためには、きちんとした管理が必要です。そのためには、やはり専門的な技術や知識が必要とされるのです。
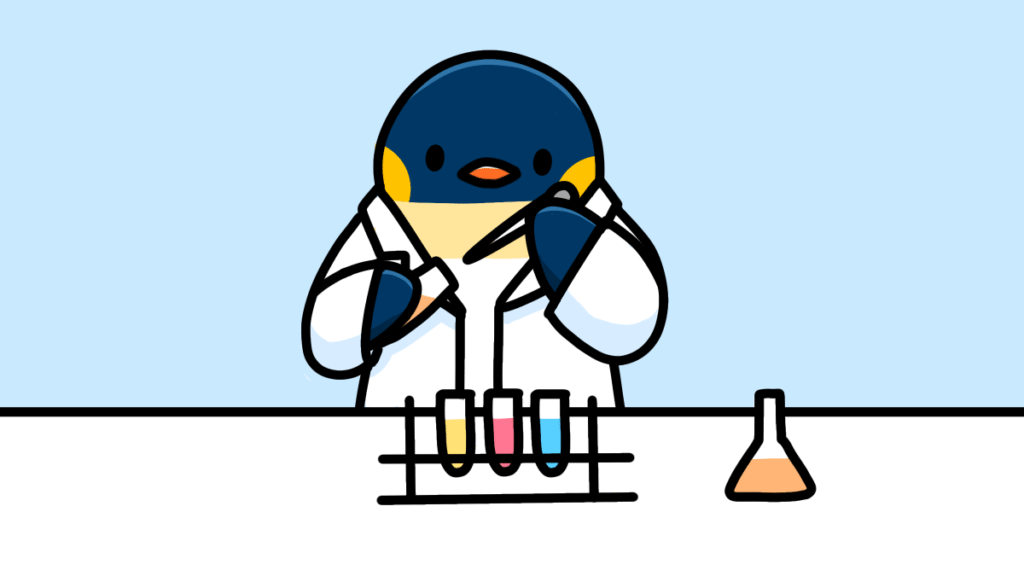

機器で測定し数値データとして報告されることが多い検体検査は、顕微鏡を用いて細胞を観察する形態学的検査と比較され、あたかも形態学検査の方が難易度が高いかのように言われることがあるのですが、これは必ずしも正しくはないと思います。形態学検査はその習得にもちろん時間がかかります。細胞を観察して分類して数を数える、あるいは良性細胞か悪性細胞かを判定する、など、高い専門的知識が要求されます。しかし、だからといって機器分析の方が容易いということはありません。
測定機器を正しく稼働させなければ正しい結果は得られません。正しく稼働させるためには、正しく管理しなければなりません。操作そのものは簡便になってはいますが、だからといって管理が容易いわけではなのです。また機械は、始動時に正常に動いていたからといって、その状態が永遠に続くとは限りません。きちんと管理していても、分析中に状態が変わることもあり、オペレータはそれを察知して、測定結果に影響があるか、測定を続行できるか、などを見極めなければなりません。そこには、専門的な知識や技術、経験が必要になります。
臨床検査の中でどの分野が簡単でどの分野が難しいということはありません。もちろん個々の臨床検査技師に得手不得手はあるでしょう。形態学検査を得意とする技師と、機器分析を得意とする技師がいることは事実です。人を相手にする生理学的検査と検体を対象とする検体検査を比較しても、もちろん同様のことがいえます。
どの分野であっても同様に、高度な専門的知識や技術が必要をされるのです。
24時間365日体制
検体検査は、24時間365日、つねに正しい結果を迅速に報告しなければなりません。
病院によって事情は異なると思いますが、多くの病院では夜間や休日は当番制をとっていること多く、つまり普段は別の検査を担当している技師が担当している場合もある、ということになります。
そこで、検体検査を専門に担当している技師は、夜間休日も正確な値が報告できるよう、さまざまな準備や当番のための教育などを行っています。
平日の日中と全く同じにはできていない病院も多いとは思いますが、夜間休日であっても、正しい結果を迅速に報告できるような体制を整えているのです。


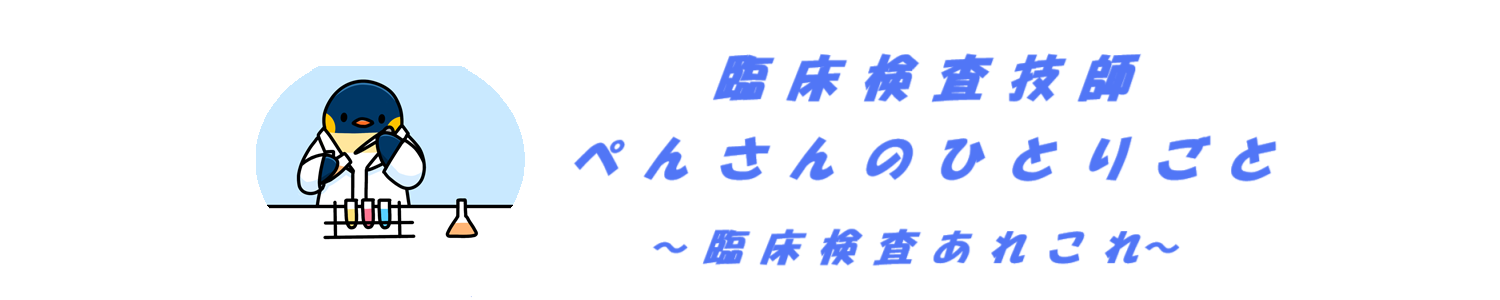


コメント