尿沈査検査

「尿沈渣」の結果をもらったけど、これは何の検査?
尿検査をした時、結果の中に「沈渣」という項目を見たことはありますか。病院では、定性検査と尿沈渣検査をセットで行っている場合もありますし、定性検査の結果によって沈渣検査が追加される場もあります。
「尿沈渣検査」は、尿を遠心分離して得られた沈殿物を顕微鏡で観察し、尿中の細胞や結晶などの有無、数量、種類などを調べる検査です。この尿沈渣について考えます。

尿沈渣検査について
尿沈渣とは
尿沈渣は、尿を遠心分離して得られた沈殿物を顕微鏡で観察する検査です。腎臓や尿路系の病気の診断や病態の把握、治療効果の判定などに有用とされています。
- 尿をよく攪拌して、先端の尖ったスピッツに10ml分取します
- 500g 5分間遠心します
- デカンテーションによって上清を除去し、沈渣量を0.2mlとします
- 沈渣をよく攪拌し、スライドガラスに15μl採量、その真上から18㎜×18㎜のカバーガラスを載せます
- 顕微鏡で弱拡大(100倍)で全体を確認します(全視野:whole field ; WF)
- 弱拡大(100倍 : Low power field ; LPF)で鏡検します
- 強拡大(400倍 : High power field ; HPF)で10視野以上鏡検します
- 細胞、その他の成分の有無、視野ごとの数等を報告します
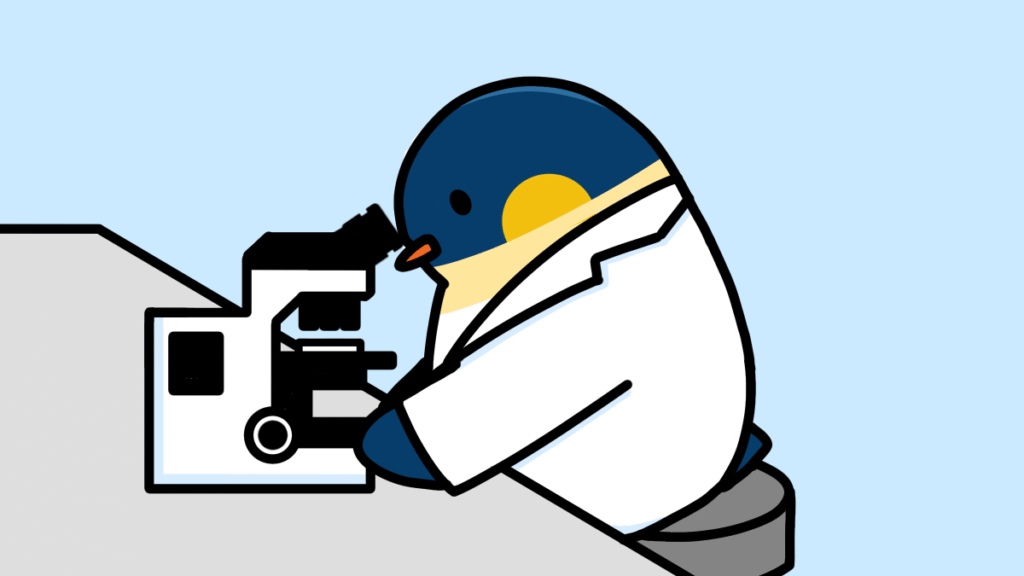
尿沈渣検査で観察できる成分
尿沈渣検査ではさまざまな成分を観察することができます。
主な成分をあげてみます。

尿沈渣検査からわかること
尿沈渣にはさまざまな成分が認められます。健康な人にも認めるものもありますが、病的な状態や特定の疾患を示唆する成分もあります。また、少数なら問題なくても、多数検出された場合は病的な意味がある場合もあります。
尿沈渣検査は、最初から定性検査と一緒に依頼される場合も多いですが、最初は定性検査だけ行い、「蛋白陽性」や「潜血陽性」などの場合に尿沈渣検査が追加されることもあります。蛋白や潜血が陽性の場合にはその原因を調べる必要がありますが、これに尿沈渣検査が有用だからです。尿沈渣を顕微鏡で観察する時には、必ず尿定性検査の結果を確認しながら、つまり、㏗や糖、蛋白、潜血などの結果を参考にして行います。ただ、尿沈渣の結果は、定性検査の結果を裏付けるだけでなく、尿沈渣を観察してはじめて明らかになる事実もあります。

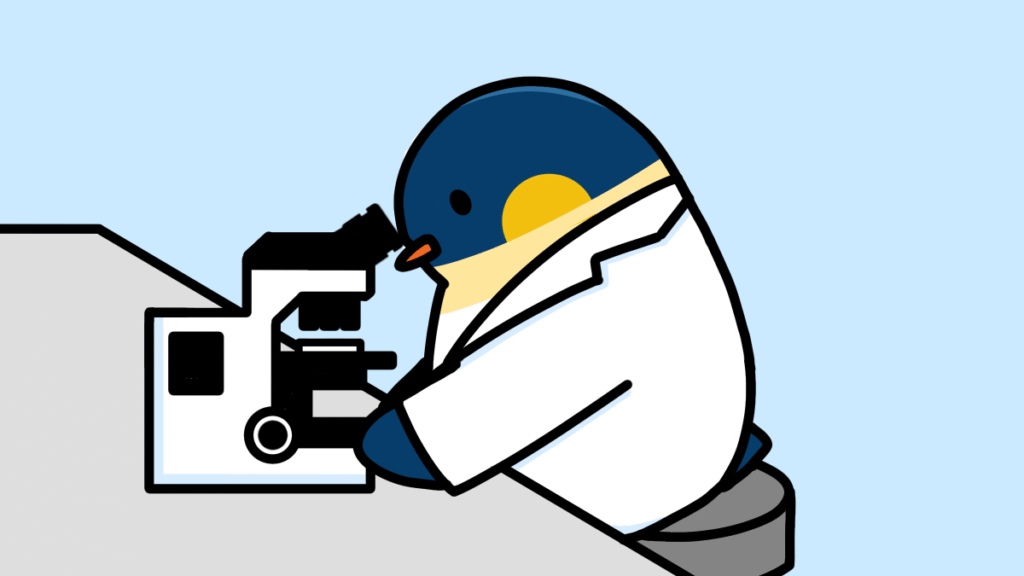
潜血が陽性で沈渣で赤血球が検出されれば、見た目に赤くなかったとしても「血尿」と判断できます。血尿のガイドラインでは、尿沈渣で赤血球5個/HPF以上認めるものを血尿と定義しています。見た目で赤い「肉眼的血尿」は自分で気付くことができますが、見た目ではわからない「顕微鏡的血尿」は健診などで発覚することが多いと言われています。血尿は、尿が作られてから排泄されるまでの経路のどこかで出血していることを示しています。顕微鏡で尿沈渣を見ると、実は尿中の赤血球はいろいろな形をしています。その形によって、腎臓からの出血(糸球体性血尿)か、尿路からの出血(非糸球体性血尿)かを、ある程度推定することが可能です。出血の原因はさまざまですが、腎臓や尿路の結石、炎症、感染症、腫瘍、また前立腺の疾患などが疑われます。
潜血が陽性にもかかわらず、尿沈渣で赤血球が認められないこともあります。赤血球が何らかの理由で壊れてしまった場合や、溶血性疾患で見られるミオグロビン尿の場合、また、試験紙の偽陽性の場合などが考えられます。
逆に潜血が陰性にもかかわらず、尿沈渣で赤血球を認める場合もあります。これは試験紙の偽陰性の場合が多く、アスコルビン酸(ビタミンC)を多量に摂取した場合に起こることが知られています。
上皮細胞は、扁平上皮細胞や移行上皮細胞以外にも、尿細管上皮細胞や円柱上皮細胞、卵円形脂肪体、封入体細胞、異形細胞など多くの種類があります。尿沈渣中の上皮細胞は、腎臓から尿路系のいずれかの部位から剥離したものです。どの細胞が検出されたかによって、どの部分に病変があって剥離したかをある程度推測することできます。また、卵円形脂肪体は、腎臓の疾患の中でも特にネフローゼ症候群に認められるもので、ネフローゼ症候群の診断基準の参考所見とされています。悪性細胞の検出は、尿路系に悪性腫瘍があることが疑われます。
円柱は、硝子円柱のほかに、その内部の成分によって名前がつけられている、赤血球円柱、白血球円柱、上皮円柱、顆粒円柱などがあります。赤血球円柱は腎臓での出血を示唆しています。上皮円柱は腎臓の尿細管の障害が、顆粒円柱は腎実質の障害があることが疑われます。また、ろう様円柱と呼ばれる円柱は重篤な腎疾患で認められるとされています。重症の糖尿病性腎症では空胞変性円柱と呼ばれる円柱が認めらます。

結晶は、必ずしも病的な要因で出現するわけではありませんが、シスチン尿症で認められるシスチン結晶のように、特定の疾患にみられる病的な結晶もあります。結晶は、鑑別のための試験をすることもありますが、多くの場合特徴的な形状をしていて、沈渣の観察である程度特定することができます。

尿沈渣の各成分は、それだけで疾患の診断を決定付けることはできないかもしれませんが、補助的診断として有用なものが多く、また、検出することでさらに詳しい検査に繋げるスクリーニング検査としても、意味が大きいといえます。
こんなことがありました
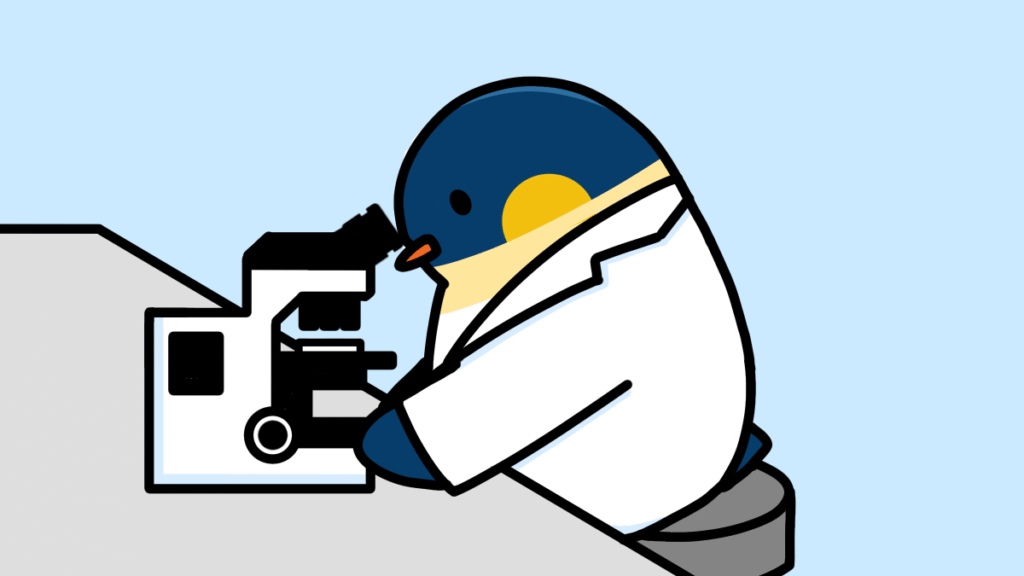
・・・「こんなこことがありました」というより「こんな風に考えていました」という方がよいかもしれませんが。
尿沈渣は、なかかなか難しい検査です。というか、私は難しいと思っています。顕微鏡で観察する形態学的検査は、やはりある程度の熟練は必要です。細胞の形状や特徴を覚えていたとしても、実際にルーチン検査の現場で標本を見た時、なかなか教科書通りには判定できないことが少なくありません。
たとえば悪性細胞ですが、細胞の核の大きさや構造、細胞の形状などから判断していきます。しかし、尿沈渣の標本は、特定の細胞を特異的に染めるような染色法を用いているわけではなく、実際には細胞を特定するのが困難な場合も多いのです。しかし、尿沈渣検査を担当していると、あやしい細胞を認めることもあります。そのような時は、形態学的な特徴、例えば核が大きい、N/C比が大きいといった状況を報告して、病理検査室での細胞診検査の依頼をおすすめする、といった対応をすることがありました。尿沈渣検査で確定するのは難しいが、見逃すことはしたくない、といった所見を、さらに専門的な検査に繋げることで、臨床に有用な情報を提供できるようにするのです。実際、この対応で、悪性所見を速やかに報告することができた症例が何度かありました。
尿沈渣は、処理が特に難しく時間がかかる検査というわけではなく、スクリーニング検査として位置づけられる検査ですから、「確定する」ことにこだわらず、「拾うこと」、「落とさなこと」、を大事にすべきかな、と思って検査をしていたように思います。もちろんこれは主に悪性細胞についてであって、赤血球や白血球、円柱、結晶など、その他の尿沈渣で判定すべき成分はきちんと検査した上でのお話です。
尿沈渣検査
尿検査は非侵襲的検査として、痛みを伴わない負担の少ない検査です。
尿の定性検査からも様々な重要な情報を得ることができますが、尿沈渣検査は、さらに詳細な情報を得ることができます。実際に検査をする際には、定性検査の結果を参考にしながら顕微鏡で観察していきます。蛋白が陽性であれば、どのよな成分を認めるか、「上皮細胞の種類は?」、「円柱はあるか?」、などというように観察していきます。また、通常、尿沈渣検査は10mlの尿を用いて遠心分離をし、上清を捨ててその沈渣を観察します。採尿時の尿量が少ない場合、少ないなりに検査をすることはありますが、当然、検出感度は劣ることになります。例えば、悪性細胞の原因となる悪性腫瘍があった時、尿中に排泄される細胞の数が少ない場合には、「10mlの尿では検出できたとしても5mlの尿では検出できない」、といったことが生じるのです。

尿検査は、スクリーニング検査として、また、疾患の診断、経過観察などに有用な検査です。尿の定性検査と尿沈渣検査を合わせて検査することでさまざまな情報を得ることができます。疾患の特定に特徴的な事実を得ることができることもあります。
尿検査をすることになったら、正しく採尿して検査を受けていただきたいと思います。(尿検査のこと1[採尿])そして尿沈渣の結果を見る場合は、定性検査の結果と合わせてみてください。(尿検査のこと2[定性検査])
もし健診などで尿検査について何か指摘をされたら、必ず一度は医療機関を受診していただきたいと思います。検査結果については、けして自己判断することなく、医師の判断を仰いでいただきたいです。


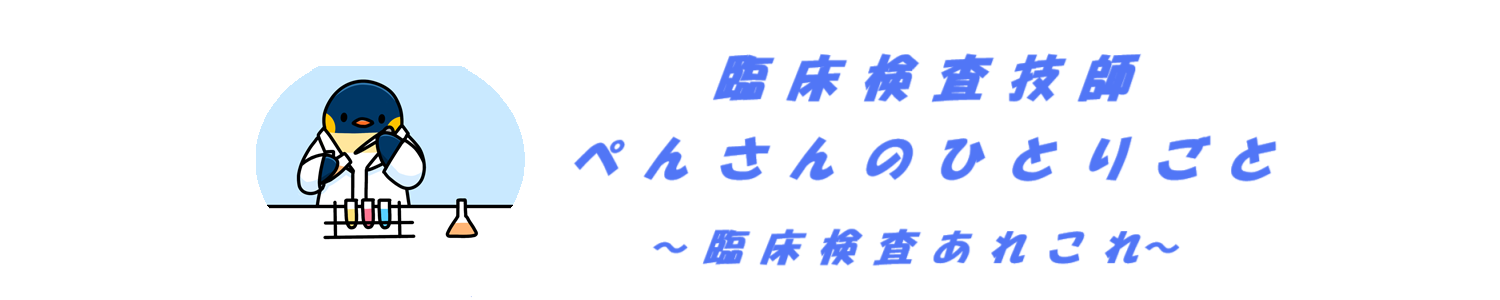



コメント