採尿

「採尿してください」って、このコップに尿を採ればいいんだよね・・・
健康診断や病院で、「尿検査をするので尿を採ってください」と言われた経験は、誰でもあるのではないかと思います。また、「朝一番の尿を持ってきてください」と言われた経験もあるかもしれません。でも、採尿の正しいやり方や、どんな意味があるのか、などについてどれくらい知っていますか。
尿検査のための「採尿」について考えます。

採尿と検査
採尿の種類
採尿には、採尿時間による分類と採尿方法による分類があります。
採尿時間による分類では、大きく分けて「早朝尿」と「随時尿」があります。また採尿方法によるものでは「自然尿」「カテーテル尿」「膀胱穿刺尿」などがあります。


尿の種類と検査の関係
通常「尿検査」といって行われている検査は、「随時尿」による「定性検査」だと思います。
「定性検査」は、尿中のさまざまな成分を調べる検査で「試験紙」を使用します。試験紙を尿に浸してその色の変化を見ることで、蛋白、糖、潜血、pH、比重そのほかさまざまな成分の有無や、おおよその量を調べることができます。試験紙は蛋白や糖など単項目用のものと、10項目程度が一度に検査できるものがあります。腎臓や尿路系、また糖尿病などの疾患のスクリーニング検査として多用されています。参考:尿検査のこと2[定性検査]

病院の来院時、診察前や診察後の検査として、あるいは健康診断の際、その場で採尿して検査するため、尿コップを渡されて採尿する尿が「随時尿」です。時間に関係なく採尿する随時尿での検査は、比較的手軽に検査ができるためよく使われます。検査する時にその場で採尿するので、新鮮な尿で検査することができますが、水分の摂取量や排尿のタイミングなどによって、いわゆる「尿の濃さ」が変わるため、検査結果も変動する場合があります。
一方「早朝尿」は異常を検出し易いと言われています。寝ている間は尿量が減少するため、朝一番の尿を採る早朝尿は、尿中の成分が濃縮していると考えられるからです。また、寝ているということは「安静」といえるので、体動や運動の影響を除外することができます。尿蛋白の検査などに用いられます。
目的とする検査の内容によって、随時尿と早朝尿は使い分けをされてます。また、起立性蛋白尿の確認のためなど、早朝尿と来院時尿(随時尿)を両方検査する場合もあります。
早朝尿や随時尿に対し、「蓄尿」は全く別の目的で使われます。多くの場合24時間ですが、24時間尿を溜めることで、尿の1日量を知ることができ、成分の1日排泄量を求めることができます。また、腎臓の濾過機能などを調べるために有用なクリアランス検査も、24時間蓄尿を用います。随時尿では排泄量の変動が大きいさまざまな成分を、24時間蓄尿を測定することで正確に把握することができるのです。
尿の採取方法
早朝尿や随時尿は特に指示がない場合、「中間尿」を採取します。中間尿は部分尿の一種で、排尿の最初と最後の尿は採らず、中間部分の尿を採るものです。尿道や外陰部の細菌が混入するのを防ぐための採取法です。検査の内容によっては、最初の部分を採取する「初尿」を採る場合もあります。
採取する容器は、いわゆる「尿一般検査」の場合は「尿コップ」と呼ばれるコップですが、細菌検査の場合は「滅菌コップ(滅菌カップ)」になります。滅菌コップは滅菌処理されたプラスチックの蓋つきの容器で、個包装になっているのものが一般的だと思います。

蓄尿の場合は、「蓄尿瓶」や「蓄尿バッグ」などと呼ばれる容器に溜めていきます。蓄尿瓶は、蓋つきのプラスチック製容器で2ℓから3ℓ程度の容量があります。蓄尿バッグは、主に膀胱留置カテーテルを使用している場合に、カテーテルに直接連結して尿を溜めるものです。

カテーテルは細い管状の医療機器で、尿カテーテルは尿道から膀胱まで挿入し尿を排出させるものです。管の先端にバルーンがあり、膀胱内でこれを膨らませることで抜けないように固定したものが膀胱留置カテーテルです。細菌検査などのために導尿をすることがあります。採取時の細菌の汚染を防ぐため、カテーテルを膀胱まで挿入し尿を流出させ、尿が採取できたらカテーテルを抜去します。このほか、何らかの理由で自分で排尿できない場合、カテーテルを自分で膀胱まで挿入し尿を排出させる「自己導尿」という方法もあります。
また、何らかの理由で尿道カテーテルの挿入が困難な場合は、腹壁から膀胱を穿刺して尿を排出させる「膀胱穿刺」という処置で尿を採取することもあります。
乳幼児の採尿
乳幼児からの採尿は、意外と難しいものです。おむつが外れている場合は、大人が介助してトイレでコップに採尿することが可能ですが、それでもなかなか上手くいかないものです。おむつが外れていない場合は、さらに大変です。トイレでの採尿は当然できないので別の方法をとることになります。

採尿で気を付けたいこと
採尿するにあたって、いくつか気を付けたいことがあります。
採尿の際、必要な量は検査によって変わります。検査の際に指示がありますので、それをよく聞いていただくのが良いと思います。通常の検尿では25ml程度あれば十分ですが、検査の内容によってはもっと少なくても大丈夫な場合もありますし、いくつかの検査をする場合などにはもっと多く、30mlから50ml程度必要な場合もあります。必要量が足りないと、正しい検査ができなくなる場合もありますので、注意が必要です。
また、便が混入しないような注意も大切です。体調などによって、便が混じってしまうようなこともあるかもしれませんが、少量でも便が混入すると正しい結果を出すことができません。おむつの中で採尿する場合も便の混入には注意が必要です。
こんなことがありました

採尿に関しては、こんな経験があります。
尿検査のため所定の場所に尿が提出されました。検査のため尿が入った尿コップを回収すると、まず、冷たい。尿を見ると無色透明。とりあえず定性検査を始めてみますが、結果はすべて陰性です。この場合何を疑うかというと、「水」の混入です。ご本人に確認をとるのが一番確実なのですが、これはデリケートな問題でなかなか難しいものです。それでも、ご本人とお話ができた時には、「コップをトイレの中に落としてしまい、すぐ拾ったけど水が入ってしまったかも」というのが多い返答だったと思います。さすがに手洗い用の水道で水を入れるわけではないのかと思いますが、「尿が出なくて水を入れてしまった」と言われたこともありました。ご本人とお話が難しい場合は、提出医にその状況を説明して対応を相談したこともあります。そうです。「水の混入」はもちろん日常的に起こることではありませんが、「非常に稀なこと」でもないのです。
また、便の混入も経験があります。これも採尿し直していただきたいのですが、このお話もデリケートな問題で、なかなか外来の待合室などで確認し難いものです。この場合はできる限り検査をしてコメントを付記したり、医師に直接説明をしたりして対応しました。
小児科の尿検査では、ガーゼの糸様のものが混入した尿を経験したことがあります。小児の採尿方法で示した方法で採尿した結果なのですが、これではやはり正確な検査結果は難しいと思います。

正しい尿検査のために
尿は多くの場合、採血のように痛みもなく、自分で採取できる検体であり、この尿の検査からさまざまな情報を得ることができます。しかし、採尿し難い方もいらっしゃいます。「病院のトイレでは採尿したくない」とおっしゃる方もいらっしゃいました。また、トイレのタイミングが悪くて、検査の時は採尿できないという場合もあります。尿が出ないとおっしゃる方には、「お水を飲んで、少し時間をおいてから採尿してください」などと説明します。しかし、「尿が出ない」と思ってしまった方にとっては、「採尿」という言葉はおそらく苦痛以外の何物でもないのかもしれません。そういう意味で、採尿は「簡単なようで簡単ではない」のです。

採尿が難しい方、今は採れないという方は、担当医師や受診科の看護師などのスタッフ、検査の窓口のスタッフなどにお話ししてみて下さい。
たかが採尿、されど採尿。正しく検査には正しい採尿が必要なのです。




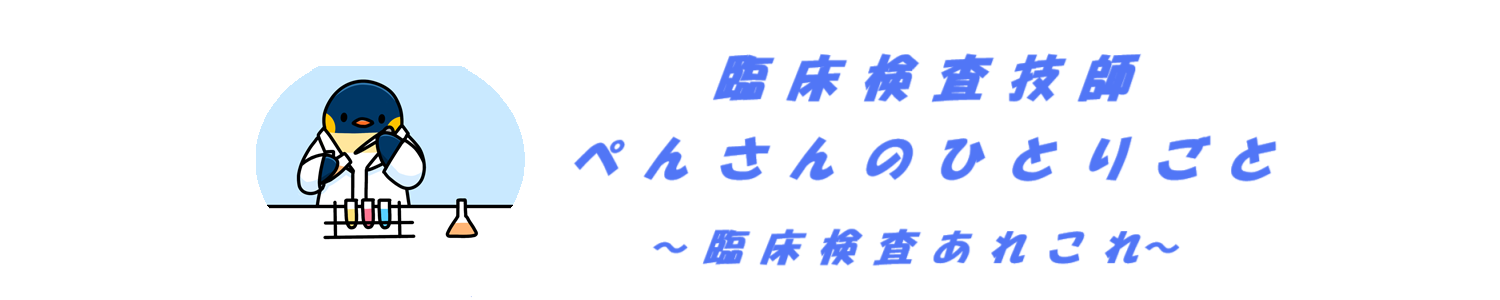

コメント