腎機能

腎機能って何を見ればわかるの?
「腎機能」はどの検査を受ければわかるのかご存じでしょうか。
「腎機能」は腎臓の働きのことです。腎臓は血液を濾過して老廃物を尿として排泄したり、水分や電解質のバランスを調節したりします。また、赤血球の生成を促すホルモンや血圧を調節するホルモンなどを産生、分泌、また、ビタミンDの活性化などをしています。
腎臓の働きが低下すると、老廃物や水分が排泄できなくなったり、貧血や高血圧、骨の弱体化などが起こります。また、腎機能がある程度まで低下してしまうと完全に回復することが難しいと言われています。したがって、腎機能の低下はできるだけ早期に発見し、治療を始めることが重要となります。
腎機能検査は血液検査以外に、尿検査、超音波検査、CT検査、MRI検査、腎生検などがあります。
ここでは血液検査と尿検査について考えていきます。

腎機能に関わる項目
腎機能の検査というと、やはり尿検査が最初に思い浮かぶでしょうか。学校健診などでも行われていますし、誰もが受けたことがある検査といえるかもしれません。
血液検査では、尿素窒素、クレアチニン、尿酸など腎臓で尿に排泄される物質を測定します。また、腎臓が1分間にどれだけ血液をきれいにしているかの指標として「クレアチニンクリアランス」を測定することもあります。
腎機能に関わる代表的な検査項目をあげてみます。

腎機能の検査項目の考え方

BUN、クレアチニン、尿酸はいずれも尿に排泄されます。腎臓の機能が低下して濾過機能が低下すると排泄が滞り、その結果として血中の濃度が高くなります。したがって、この3項目は腎臓の機能に状態を反映して、大まかには同様の動きをすると考えられます。ただ、それぞれの項目の特性があるので注意も必要です。
BUNは蛋白質の分解産物なので、高蛋白食や脱水などでも上昇します。共用基準範囲では8㎎/dL~20㎎/dLで男女差はありませんが、加齢とともに上昇すると言われています。
クレアチニンは筋肉の分解産物です。共用基準範囲では男性0.65㎎/dL~1.07㎎/dL、女性0.46 mg/dL~0.79mg/dLと男女差があります。これはクレアチニンが筋肉量が多いと高くなる傾向があるためです。また、加齢とともに上昇する傾向はありますが、個人の生理的変動幅は比較的小さい項目だと思います。BUNとクレアチニンを比較すると、値の変動の幅はBUNの方が大きいですが、クレアチニンの方が腎機能の低下を反映しやすいと言われています。クレアチニンの小さな上昇でも、腎機能低下を疑うべきといえるかもしれません。
尿酸はプリン体の分解産物ですが、高尿酸血症による「痛風」のイメージが強いかもしれません。高尿酸血症はプリン体を多く含む食品やアルコールの過剰摂取により起こると言われていますが、これは尿酸が過剰に生産されるためです。しかし、高尿酸血症の原因にはもう一つ、排泄が不十分な状態があり、これが腎機能の低下にあたります。つまり、尿酸が単独で高値の場合と、BNUやクレアチニンも同様に動いいている場合では、結果が示す身体の状態が異なると考えられます。
eGFRとクレアチニンクリアランスは、どちらも腎臓の濾過機能を示しているといえます。eGFRは採血だけで評価できるのに対し、クレアチニンクリアランスは採血と採尿が必要になります。しかも、24時間クリアランスを求める場合は、24時間尿を貯める「蓄尿」をしなければなりません。外来でも蓄尿用の容器をお渡しして24時間の蓄尿をしていただくケースもありますが、患者様に蓄尿をしていただくのは、間違い、勘違い等もあり、なかなか正確にできない場合あります。入院して実施するにしても、患者様と医療スタッフの双方に負担がかかります。ただ尿を貯めるだけといえばそうなのですが、なかなか難しい問題もあるのです。一方eGFRは血清クレアチニンを測定すれば計算で求めることができるので、クレアチニンの依頼があると自動的にeGFRを算出して報告している施設も多いと思います。
シスタチンCは腎機能を評価する検査項目で、腎機能の低下を早期に発見できるともいわれています。また、クレアチニンより筋肉量の影響を受け難く、より正確な腎機能評価ができるとされています。ただし甲状腺機能や一部の薬剤など、影響を受ける要因もあるので注意は必要です。シスタチンCでeGFRを求めることもあります。


尿蛋白の検査は学校健診などでも実施されていますが、「尿蛋白が陽性」と言われる場合は、通常、「試験紙」による「定性検査」の結果です。この定性検査が陽性でも、直ちに「病気」というわけではありません。一過性である場合もあるからです。ただし、これを自分で判断してしまうことは間違いです。必ず医療機関などで再検査を行い、場合によっては「定量検査」をして蛋白がどのくらいの量出ているのかを調べるべきです。尿蛋白は腎機能低下の早期発見に役立つと言われています。
尿潜血は尿に血液が混じっているかどうかの検査です。尿に血液が混じった「血尿」には、尿が赤いなど、血液が混じっていると目で見てわかる「肉眼的血尿」と、色の変化はわからないが顕微鏡で見ると赤血球が確認できる「顕微鏡的血尿」があり、どちらの場合でも「潜血陽性」となります。血尿となる要因は、腎臓から膀胱まで、尿が作られてから体外に排泄されるまでのすべての経路上にあるので、「潜血陽性」がそのまま腎機能低下というわけではありませんが、いずれにしても何かしらの疾患が隠れていると考えるべきでしょう。医療機関の受診が必要です。
腎蔵のために
肝臓と同様に腎臓も「沈黙の臓器」と呼ばれています。腎臓は、病気があっても進行するまで症状が出難いと言われる臓器の一つなのです。しかも腎臓は、ある程度機能が低下してしまうと元に戻り難いとも言われています。したがって、機能低下の早期発見は非常に重要といえます。
腎機能を評価する検査項目は、今回取り上げた項目以外にもたくさんあります。しかし、通常の健康診断で検査する項目の中にも、腎機能低下を見つける糸口になる項目がいくつかあります。自覚症状がなければなかなか受診はし難いかもしれませんが、健康診断で指摘されたら、とりあえず1回は医療機関に足を運ぶべきです。それが、腎機能低下の早期発見、早期治療に繋がり、慢性腎臓病や維持透析などに至らずに過ごすことに繋がるのです。
また、検査結果に関しては、自己判断は禁物です。必ず医師の判断を仰ぎましょう。



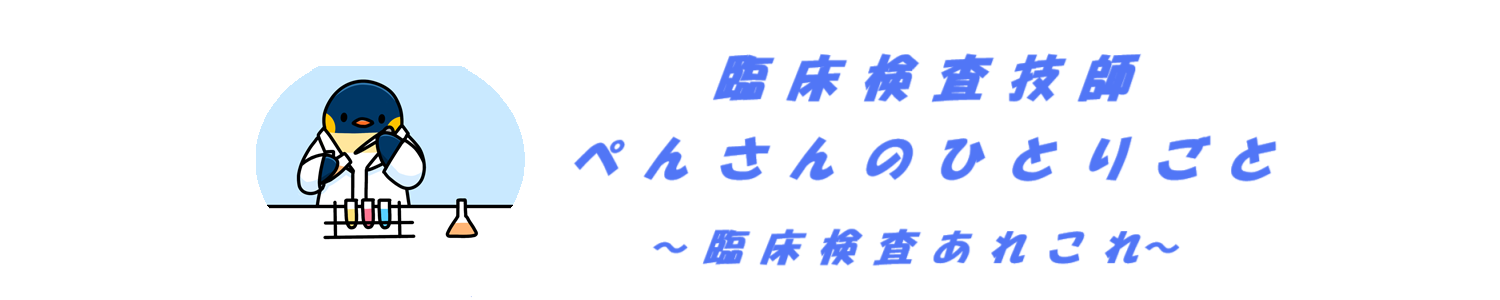


コメント