検体検査における血清情報

検査結果を見ると最後の方に「H、I、L」とあってそれぞれ数字が0とか1とか入っているね。これは何?
生化学の結果を見た時、下の方に「H」とか「L」「I」が書いてあることがあると思いますが、見たことはあるでしょうか。これは「血清情報」とよばれるもので、それぞれ「溶血・乳び・黄疸」を指します。簡単にいうと「血清の色」の「赤・白・黄」の度合いを数値で示したものなのですが、今回はこの「血清情報」について考えます。

血清情報とは
生化学検査では血清のいわゆる「見た目」も重要な情報となるので、溶血の赤色、乳びの白色、黄疸の黄色を「血清情報」として提示することが多いです。
「溶血 H」は赤血球が壊れた状態で、検査結果に大なり小なり影響を与えます。検査結果の考え方 3[溶血の影響]
「乳び L」は「混濁」と言われることもあり、血清中に主に食事中の中性脂肪が残っているため白濁して見えるものです。健康な人でも認めることがありますが、検査結果に影響を与える場合があります。「黄疸 I」は「黄色度」とも呼ばれ、主にビリルビン濃度が高くなって黄色になっている状態です。
乳びについて
乳びとは
「乳び」は血清が乳白色に濁って見える状態です。主に中性脂肪(TG)の濃度が高く、分解されずに血清中に浮遊しているために起こります。その主な原因は、食事の影響と脂質代謝異常があげられます。食事の影響は、食後、時間を置かずに採血した場合や、特に脂肪分の多い食事を摂った後などに見られます。また、高脂血症などのような脂質代謝異常がある場合には、食後に限らず空腹時であっても乳びを認めることがあります。

乳びの影響

血清の濁りは、検査の測定原理上妨害になったり、光学的測定法に干渉するため、測定結果に影響を与える場合があります。乳びはそもそも血清中にカイロミクロンなどのTGが多く存在している状態と言えるので、TGは高値となります。食事の影響を受けて一時的に乳びとなっていた場合、その人の通常のTGの値より高値を示すということです。総蛋白(TP)やビリルビン、尿酸など比色法を原理としている項目は、測定時に濁りの干渉をうけて偽高値となる場合があります。
検体の状態が検査結果に影響を与えるのは生化学検査に限ったことではありません。凝固検査の項目であるプロトロンビン時間(PT)、活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)、フィブリノゲンなども、光学的測定原理を用いているため測定に影響を受ける場合があります。特にPTは、強乳びで測定不能になる場合もあります。
乳びを回避する方法
乳びはさまざまな項目に影響を与えますが、溶血を認めた時のように再採血の対象とはなりません。それは乳びが採血の時に起こるものではないからです。高脂血症など脂質代謝異常ではない場合、採血前の食事の影響を考えます。一般的に乳びは、食後4時間がピークでその後徐々に低下すると言われていますが、採血は採血前12時間の絶食が望ましいとされています。
最近では測定試薬や測定機器に、乳びの影響を回避できるような工夫がされていて、以前ほど測定結果に与える影響は大きくない印象です。しかし、特に脂質代謝異常などがなければ、食事に関して注意をすることで、乳びの影響は回避可能です。このことは認識しておくに越したことはないと思います。
検査担当者としての乳びに対する対応
乳びは、採血前の食事を注意することや試薬や機器の性能によりある程度は回避できますが、それでも乳びによって検査結果に影響が生じ、検査担当の対応が必要になる場合があります。
まず、影響を受けた項目に対して別法での測定が可能であれば、それも一つの手段となります。
強乳び検体で、血液凝固検査のPTが測定不能となった場合、用手法で測定することにより解決できる場合があります。ただ、用手法はそれなりの技術や準備が必要で、もちろん対応可能な施設も多くあると思いますが、機器分析が主流となった現在では、その技術水準の維持や必要な器具の準備など、急には対応が難しいという現実もあります。


生化学の項目では、超遠心分離が効果的と言われますが、これは通常の検査室にはあまり準備のない特別な遠心機が必要であり、あまり現実的ではありません。
比較的簡便なのは、すべての項目に適しているわけではありませんが、血清を希釈して濁りを薄めることで影響を小さくし、測定結果を求めるものです。また、脂質除去試薬、混濁血清処理剤、乳び除去試薬といった市販試薬を使用する場合もありますが、これもすべての項目に適用できるわけではなく、特性を理解して使用する必要があります。
乳びについて考慮すべきこと
乳びは、多くの場合食事の影響によるものと考えて間違いはないと思います。しかし、医療現場では食事以外にも乳びを引き起こす要因があります。点滴や薬剤などです。たとえば中心静脈栄養法(IVH)あるいは完全非経口栄養法(TPN)は、高カロリー輸液を血管から直接投与するものですが、栄養補給のために投与される脂肪乳剤の影響で乳びとなることがあります。また一部の薬剤では、大量投与により乳びとなるものや、脂肪代謝に影響し結果として乳びとなるものなどもあるようです。
通常の食事の影響であれば、場合によっては、次回の採血時に絶食指示をして乳びを回避するということも可能ですが、IVHなどの場合は採血条件による回避はなかなか難しいでしょう。しかし強乳びの検体では、項目によっては測定不能も致し方ない場合があります。なぜ測定できないのか、乳びによってどのようなことが引き起こされているのか、を的確に医師に説明することができるスキルが必要といえるでしょう。

黄疸(黄色度)について
黄疸(黄色度)とは
黄疸(黄色度)は、黄色の度合いであり、通常、ビリルビンの血中濃度の上昇に伴って強く現れます。血中のビリルビンの値が高値となるのは、肝機能障害や胆道系の障害が疑われる場合で、関連する検査項目も高値となります。したがって検査結果を確認して状況の整合性が認められれば、黄疸の度合いが強いことの説明になるといえます。
黄疸(黄色度)が高くなる理由
ビリルビンが増加する要因には、溶血性疾患、遺伝性疾患、新生児黄疸、ストレス、薬剤、などもあります。また、ビリルビン以外にも、ニンジンやカボチャ、柑橘類などに含まれるカルテノイド色素を大量に摂取した場合などには、血清が黄色味を帯びることがあると言われています。
ビリルビンは赤血球が壊れた時に生成されます。通常は肝臓で処理されて排泄されますが、肝臓が上手く処理できなかったり、排泄が滞った場合に体内に蓄積して血中のビリルビン濃度が高くなり、血清が黄色くなります。溶血性疾患で赤血球が大量に破壊された場合も、肝臓でのビリルビンの処理が追い付かず、結果として血清の黄色が増すことになります。

黄疸(黄色度)の影響

黄疸(黄色度)が強い場合、吸光度測定を原理とする測定系に干渉し、他の検査項目の測定結果に影響を与える場合があります。最近では、試薬の改良などさまざまな工夫によって、その影響は受け難くなっている印象ではあります。たとえばクレアチニン測定法の一つ「ヤッフェ法」は、ビリルビンの干渉を受けると言われています。ヤッフェ法は、以前はクレアチニン測定の代表的な方法でしたが、現在では他の方法が主となっていて、ビリルビンのの影響も回避されています。
黄疸(黄色度)が強くても、当然再採血の対象にはなりません。しかし、患者様の状態によっては黄疸(黄色度)はかなり強くなる場合があるので、測定系への干渉が起きている可能性も視野にいれて、検査結果を見ることも必要だと思います。
こんなことがありました
黄疸(黄色度)に関して、少し苦い?経験があります。かなり以前のことですが、ある病院で一人当直をしていた時のことです。救急外来から検体を受け取りました。血算、凝固、生化学だったように思います。検査の効率を考えて、まず私は生化学検体の遠心分離をしつつ、凝固検体の遠心分離と血算の検体の攪拌をはじめました。頭の中の段取りでは生化学の検体を測定機に架設してから血算と凝固検査をしようと思い、遠心機から生化学の検体を取り出しました。すると血清はかなりの黄疸。咄嗟に「これは肝機能がまずいかも」と思い、血清に余裕があったので、5倍だったか10倍だったかの希釈をした検体と元検体を一緒に装置に架設しました。そのあと血算の結果を見ると、かなりの貧血。この時点でピンとくれば良かったと思うのですが、当時の私はピンとこず・・・。そうこうするうち生化学の結果をみると、肝機能はほぼ正常。そうです。この患者様は溶血性疾患だったのでしょう。この後も血液型の検査での苦労もあったのですが、患者様は確定診断はされないまま、当直医の判断でより大きな病院へと搬送されました。
「黄疸が強い=肝機能障害あり」の思い込みで、バタバタと実際には不要の作業を行った事例でした。

検体の「見た目」

検体の「見た目」はいろいろな情報を与えてくれます。これを数値で示しているのが「血清情報」です。
通常は生化学の測定機で処理されて数値として表現されます。担当医師や患者様はこの数値で検体の状態を把握することになります。しかし、私たち検査を担当する検査技師は、検体を肉眼で確認することができる数少ないスタッフの一人です。自分の目でしっかり検体を見ることは重要です。思い込みは避けるべきですが、見て得た情報とともに検査結果を考えることは重要だと思います。
検査結果を報告書で確認する時には、「溶血・乳び・黄疸」の数値にも目を向けて、検査結果を確認していただくと良いと思います。今まで見えなかったことにも気付くことができるかもしれません。ただし、検査結果に対して自己判断は禁物です。あくまでも医師の判断を仰ぎましょう。


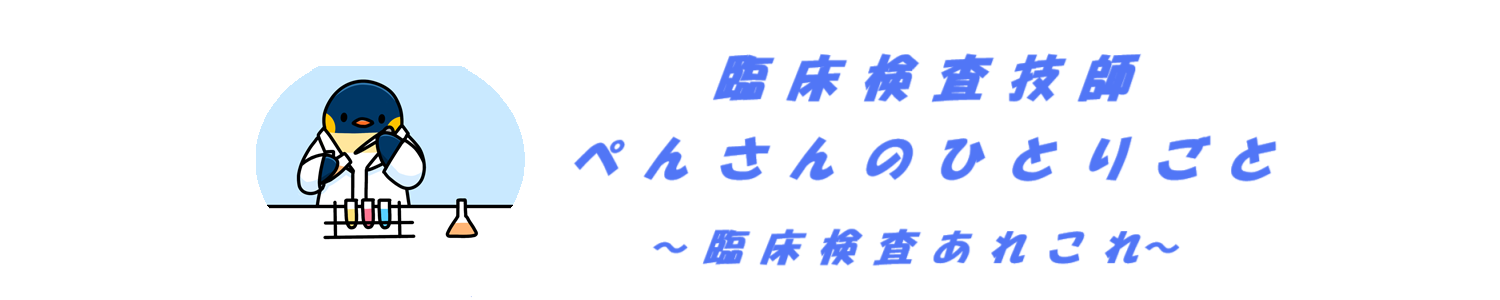


コメント