検査結果が基準範囲を外れたとき

悪い結果だったら早く教えてくれるのかな・・・
診察後に、「採血して帰ってください。結果は次回の診察で。」と言われることがあると思います。この時、自分では気になる症状などがあって検査結果も心配だったりすると、「次の予約まで時間があるけど大丈夫かな。もしも悪い結果だったら早く教えてくれるのかな」などど考えることはありませんか。
今回は、検査結果が悪かったときの対応について考えます。

検査結果は基準範囲を参考に判定しますが、検査結果には生理的変動と呼ばれる個人差的な要素や、採血条件などが影響するので、これらを考慮する必要があります。また、項目によってはいわゆる基準範囲ではなく、「臨床判断値」、「カットオフ値」、「治療閾値」などが設定されており、必要に応じてこれらも参考にして判定することになります。検査結果の判定1 [基準]
基準範囲から逸脱した結果があった時
実際の検査結果がこれらの基準とする値から逸脱していた場合、さまざまな対応をとることになります。
どのような対応をするかは、病院での検査であれば、担当医の判断となります。また健康診断でも、逸脱の程度によると思いますが、原則は再検査や精密検査の指示が出されることになります。
軽度の逸脱であれば、「経過観察」という対応が多いかもしれません。項目によっては早期に再検査をして、変わらず軽度の逸脱であれば、たとえば次回検査を3か月後、半年後、1年後、といった具合に設定して経過観察が提案されることになります。また、軽度あるいは中等度の逸脱の場合、「精密検査」と言われるような詳しい検査を行って確認し、その時点で治療が必要な病態が確認できなければ、やはり次回の検査までの間隔を決めて経過観察となります。
大きく逸脱していた場合は、項目にもよると思いますが、なるべく早く再検査やより詳しい検査をすることになります。「なるべく早く」については、医師の判断によるところが大きいと思いますが、たとえば次回の予約が1か月後だった場合、結果が報告された段階ですぐに連絡をする場合もありますし、予約通りに1か月後に再診をし、その時に追加の検査をする場合もあると思います。

ただ、1回の検査結果で何かを確定することは基本的にはないと思います。診断を確定するにしても、治療開始や経過観察を決めるとしても、再検査や関連する項目の検査を行い、総合的に判断することになります。
いずれにしても、もし万が一病院から次回の再診予約より前に来院するよう連絡があった場合は、当然のことながら速やかに対応する方が良いといえます。
検査科での対応
検査科での結果報告までの流れ
検査科では検体を受け取ると、到着確認や遠心分離などの処理後、各測定機器に架設します。
各測定機器は、メンテナンスや較正、精度管理物質の測定など、検体測定前に実施すべき準備を行い、検体の測定に備えています。
問題なく測定が終了すると、結果を確認して報告します。検査結果の確認は、各項目の基準範囲や、その個人の前回の測定結果、また関連項目の結果などを参考に行います。特に問題がない場合はそのまま報告しますが、基準範囲から逸脱していたり、前回の結果からの変化が大きかったり、関連項目間に違和感があるような場合は、再測定をして確認をします。そして再測定後、必要に応じて「再検済」などのコメントを付記して報告します。
検査科での結果の判断
検査科では、患者様の状況はわかりません。医師など患者様と直接接してい医療るスタッフから情報を得たり、最近では電子カルテが導入されていて、検査科でもカルテの記載事項の閲覧が可能な場合もありますが、基本的には検体のみで判断し対応します。あくまでも測定結果の数値を見て判断をすることになるのです。したがって、たとえば医師にとっては想定内の異常値でも、検査科では「再検査をして報告する」ということになる場合もあります。

検査結果の異常に対して

ところで、検査結果の異常は、さまざまな要因によって起こります。患者様の状況によるものを第一に考えますが、検査機器で測定する場合には、さまざまなイレギュラーも想定しておく必要があります。機器の故障という場合もありますが、測定中の検体の状態だったり、採血時の問題が原因となる場合もあります。検査科では、そういったさまざまな要因も加味しながら結果を判定する必要があります。機器や検体の状況は、検査科内の事情なので分かりやすい面もありますが、採血時の問題はすぐに判明しないことが多く、測定値自体の確認をしたあと、採血時の状況を確認するといった対応になります。このようなすべての状況を総合的に判断して結果を判定し、その数値をそのまま報告値とするか、医師に連絡をするか、といった判断をしていきます。
医師に連絡する測定結果
多くの施設で電子カルテが導入されている現在、通常検査結果は、検査科のシステムから電子カルテに送信されるかたちで報告されます。しかし、何らかの問題がある場合、提出医に直接連絡をすることがあります。
検体に問題がある時
検査科では解決できない問題が検体に生じている場合、検査結果と状況を医師に直接報告します。たとえば、血小板の値が5×10⁴/μLだった場合、これは異常低値ですが、検体の一部に凝固が認められる場合、血小板が消費されて検体が凝固し低値となったことも想定されるので、その状況を医師に伝える必要があります。したがって、直接連絡をとることになります。

検査結果に異常がある時

検体や測定上にこのような問題が認められず、検査結果が基準範囲や個人の前回値から大きく逸脱している場合、医師に直接連絡するという選択をすることがありす。それは、直接連絡をとった方が医師に早く伝わるからです。
診察前検査であれば、遅かれ早かれ医師は確認するわけですが、それよりも早く確認した方が良いと判断した場合は、結果が確定した段階で速やかに連絡をします。
診察後検査の場合は、その日のうちに医師が結果を確認しない場合が多いので、直接連絡をして、検査結果の確認を促す場合もあります。そうすることによって、医師が次回の診察予定より前に結果を確認し、その結果として患者様に早めの来院を促す、といった対応になる場合もあります。
検査結果に対する担当検査技師の責任
基準範囲からどの程度の逸脱で連絡をするかということは、施設ごとの取り決めがある場合が多いでしょう。いずれにしても、原則として、何らかの速やかな対応が必要と思われる結果の場合直接連絡をすることになります。
検査科で検査結果を見る臨床検査技師は、誰よりも一番最初に結果を見ることになります。その時の担当技師の対応の仕方によって、患者様に対する診断や治療の開始が「最速」になったり「遅れて」しまったり、ということが起きるかもしれません。検査を担当する臨床検査技師は、その責任も理解していなければならないといえます。

検査結果が基準範囲から逸脱している場合の対応
検査結果が基準範囲を逸脱するのはさまざまな要因があります。
検査科では、患者様の状態以外の理由があるかどうかの判断が必要とされます。そこを踏まえた上で、担当医師へ、状況に応じた連絡をとります。
検査科からの連絡を受けて、あるいは医師自身が結果を確認して、より迅速な対応が必要と考えれば、担当医師から患者様に連絡をするという対応になる場合もあると思います。次回の診察の時で良しとなれば、そのような対応になるでしょう。
いずれにしても、検査を受けたら、結果は必ず聞きに行くことはもちろん、万が一呼び出されるようなことがあれば、速やかに対応することが大切といえます。自己判断は禁物です。必ず担当医師の判断を仰ぐことが重要です。


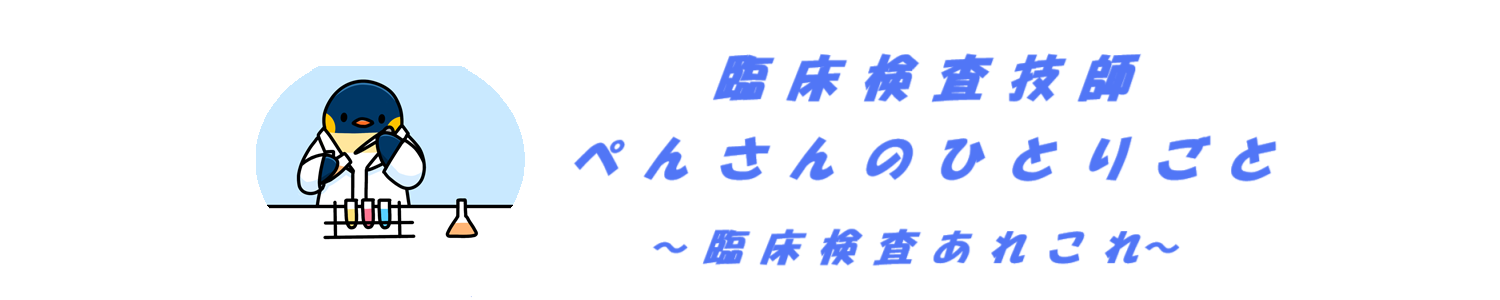


コメント